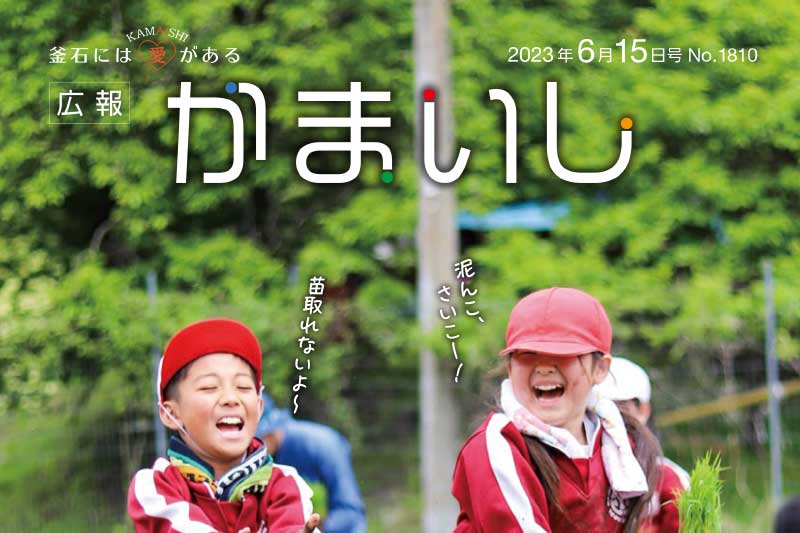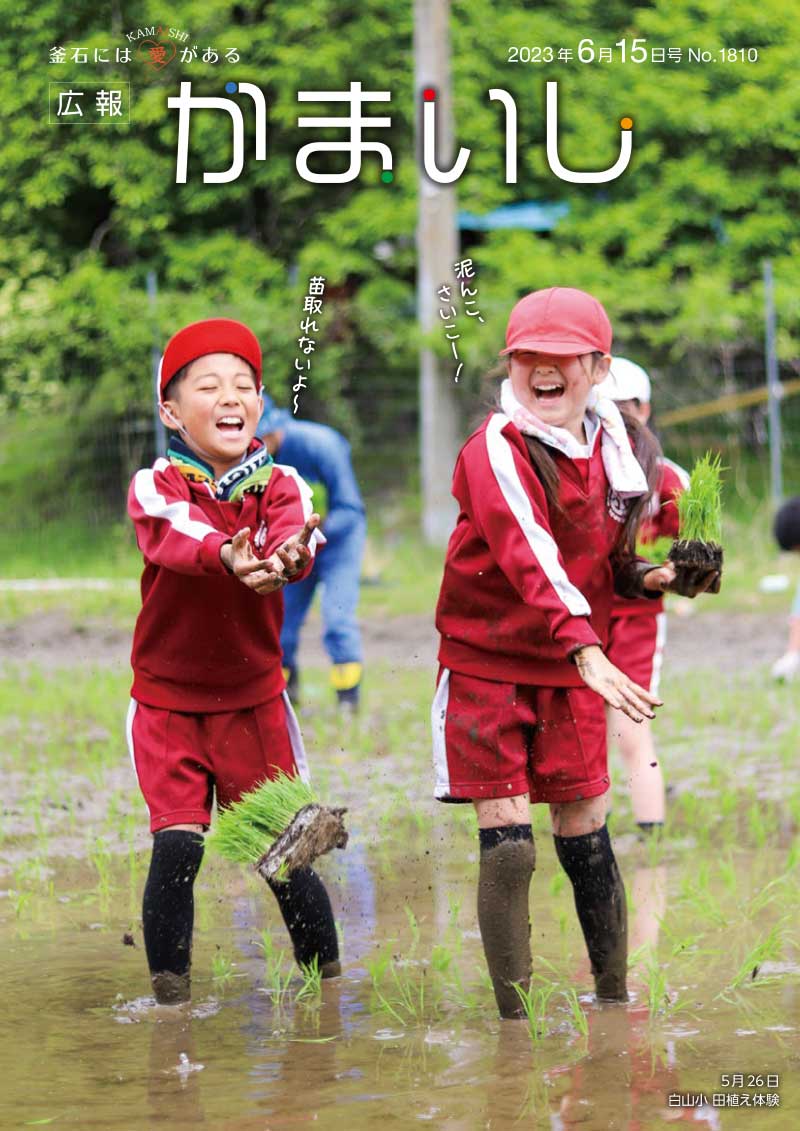釜石ワインの新酒を待ちわびた市民ら
釜石産ブドウを100%使ったワイン造りに取り組む「ソーシャルファーム&ワイナリー」は16日、2022年産新酒のお披露目会を釜石市港町のイオンタウン釜石で開いた。今季の「釜石ワイン」は混醸(こんじょう)の白2種に仕上げ、計約100本限定で販売。軽食とともに試飲した市民らは「心のこもった深い味わい」に酔い、次々と“お買い上げ”した。
ソーシャルファームは、遠野市のNPO法人遠野まごころネット(小松正真理事長)が東日本大震災の被災地の活性化、被災者や障害者らの雇用創出などを目的に創設した事業の一環。釜石・甲子町で運営する障害者自立支援施設「まごころ就労支援センター」(山本智裕施設長)の農福連携事業として、14年からブドウを育て、ワイン造りに取り組んでいる。
昨秋は約20アールの畑から約130キロを収穫した。シャルドネやリースリングなど6種の白ブドウを混醸させた「釜石ブラン」はすっきりした飲み口が特徴で、食前酒におすすめ。白、赤ブドウを同じタンクで「マロラクティック発酵」(乳酸菌がワインに含まれるリンゴ酸を乳酸と炭酸ガスに分解する発酵)させた白「釜石アッサンブラージュ」はまろやかだが、キリッとした酸味が感じられる一品。いずれも、750ミリリットル入りで価格は2500円。

「乾杯!」。お披露目会で新酒を楽しむ参加者
お披露目会には新酒を楽しみにしていた市民や関係者ら約50人が集った。小松理事長(44)は「この地でブドウ栽培、ワイン造りに挑戦し、間もなく10年になる。心の込もった味わいを楽しんでほしい。これからも、地域発展の力になるよう取り組んでいく」とあいさつ。釜石ワインのほか、遠野産の3種類も紹介され、参加者が飲み比べを楽しんだ。
毎年味わっているという鵜住居町の佐々木博幸さん(67)は「年数がたって、いい味になってきた。品種をミックスして、あっさりしながら深みもある味わい。乳酸菌発酵という新たな試みで、いろんな味を楽しめるようになっている」と堪能した。

「新酒をどうぞ」。関係者がおもてなしした
ファームでは、同センターを利用する10~50代の30人ほどがブドウ栽培に携わる。畑の草刈りやせん定、収穫などの作業に一丸となって取り組んでいて、施設利用者の佐藤弘一朗さん(28)は「大変なこともあるけど、ブドウたちの成長を見ながらできるから楽しい。みんなの協力があってこそのおいしいワインができたので、たくさんの人に味わってほしい」と願った。ラベルやチラシのデザインも利用者が担当。「釜石と言えば」をテーマにしたラベルでは、海やウミネコなどがモチーフになった。

釜石ワインの新酒に目を細める関係者や市民ら

会場で販売された釜石産、遠野産ワイン
醸造を担当した同センターの職業指導員荒川哲也さん(35)は「おいしい」との声を聞き、「受け入れられて、ほっとした。今季のワインはアルコール度数が9%程度だが、醸造の技術を磨いて度数を上げたり、スパークリングにも挑戦してみたい」と意欲を高めていた。
今季の釜石産はお披露目会で多くの人が手に取っており、品薄になっているとのこと。購入などの問い合わせは、まごころ就労支援センター(電話0193・55・5100)へ。