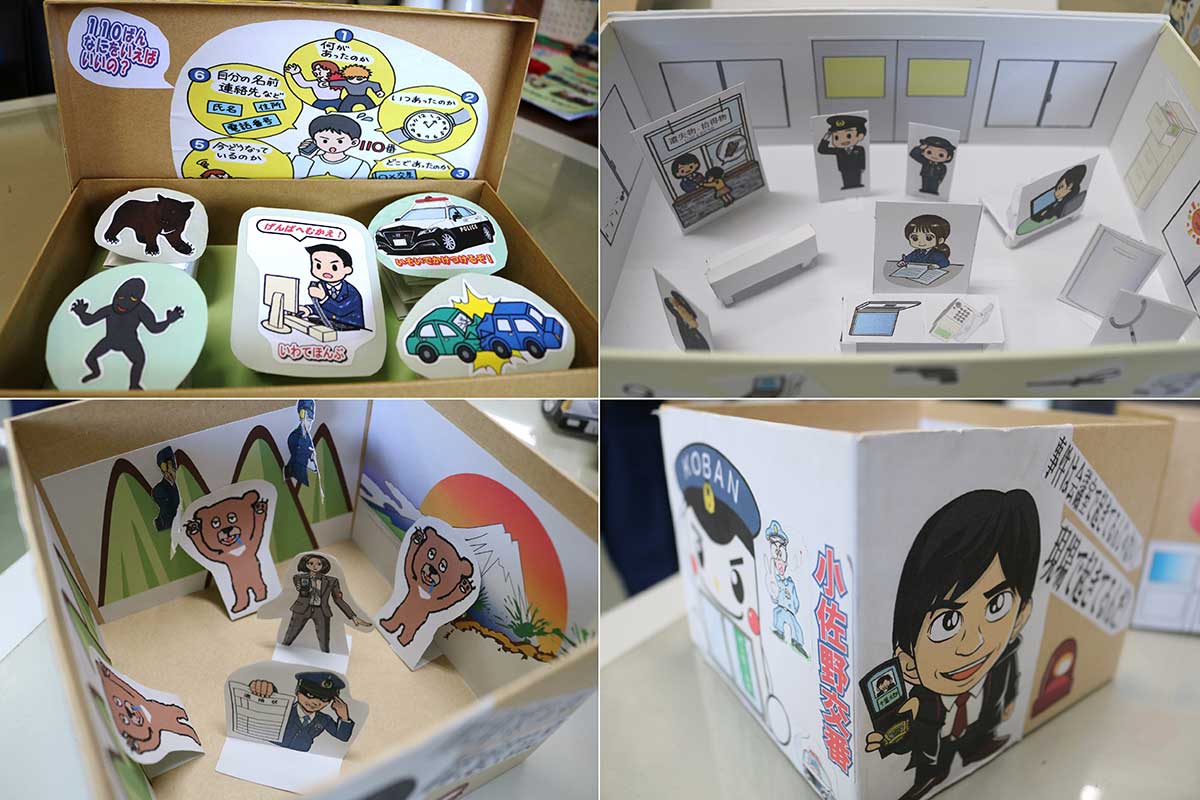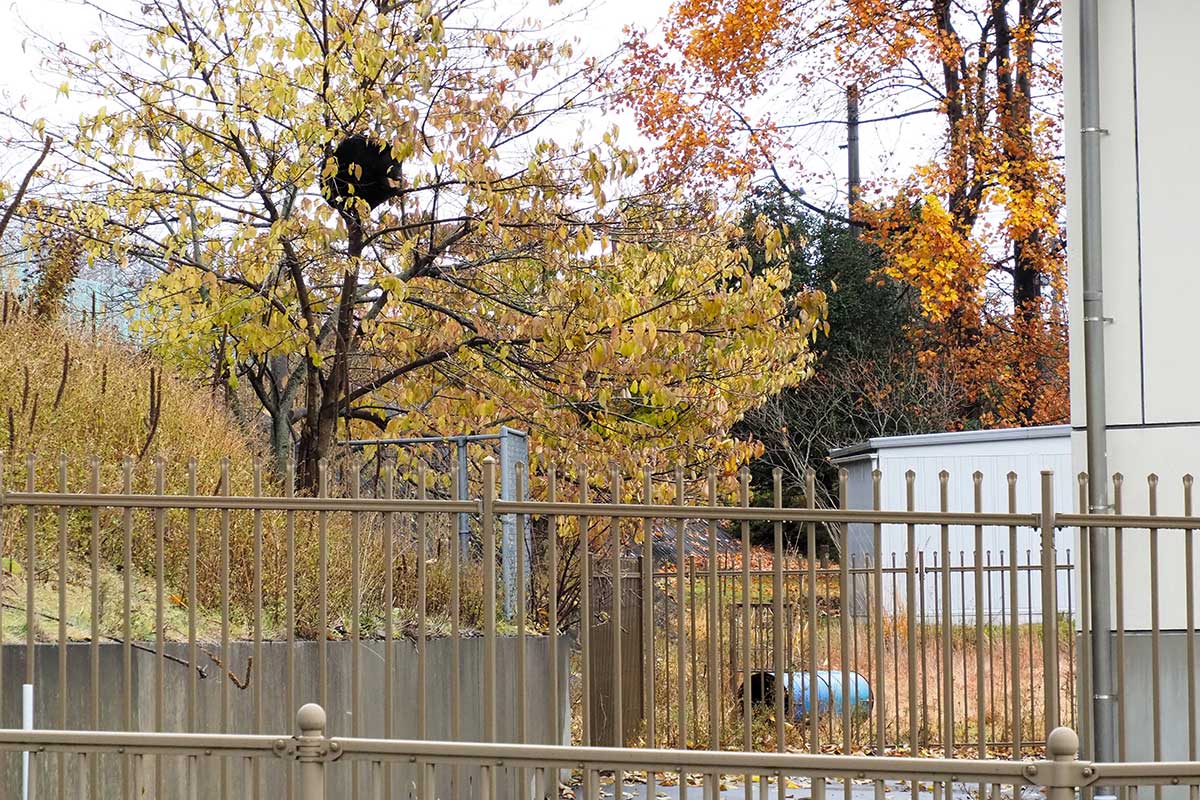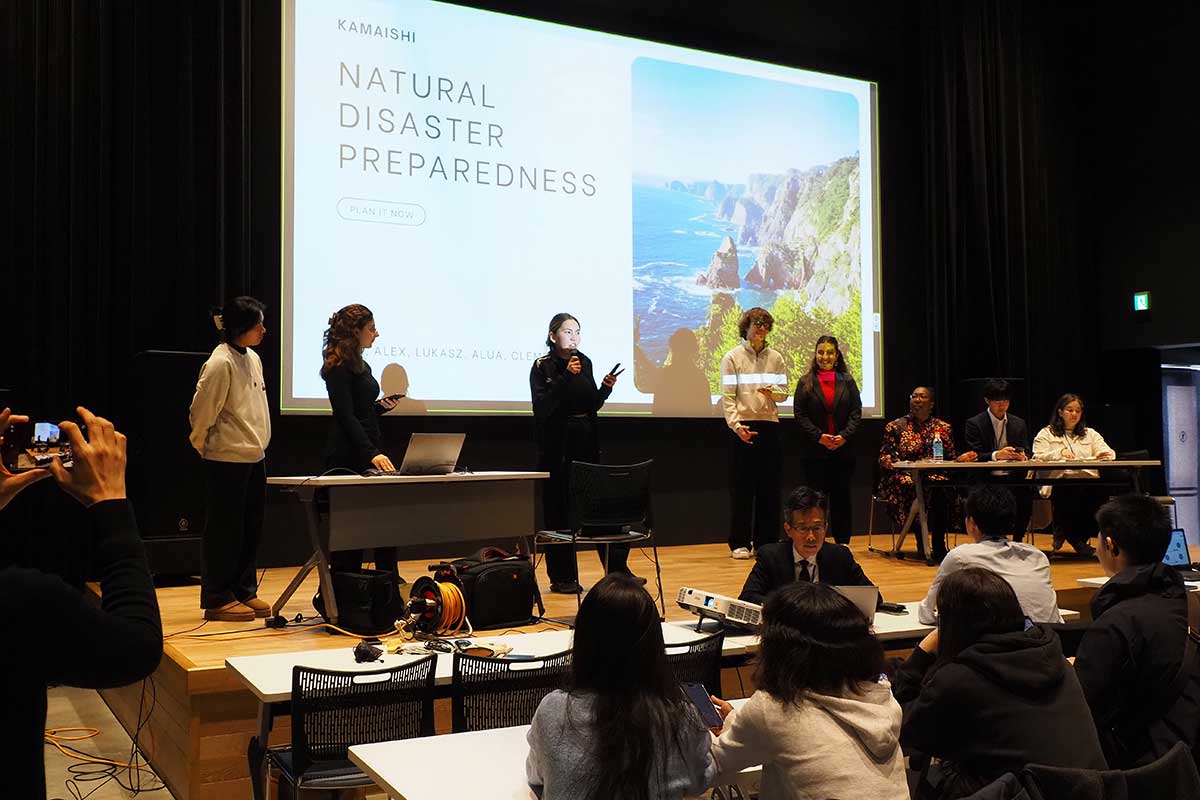自分たちで作った竹灯籠の前で…/14日、点灯式(根浜津波避難階段)
東日本大震災の津波で大きな被害を受けた釜石市鵜住居町根浜地区。来月11日で発災から15年となるのを前に、地区内の高台につながる津波避難階段に今年も竹灯籠が設置された。震災犠牲者を追悼し、命を守る行動の意識啓発を図る5年目の取り組み。3月までの土日祝日と震災命日の11日に午後5時から同7時まで点灯される。
竹灯籠の製作から点灯まで一連の活動を続けるのは、根浜キャンプ場などを管理する同市の観光地域づくり法人かまいしDMC。製作は地元町内会の「根浜親交会」と一般向け体験会の参加者の協力で行われる。今年は1月31日、2月1日に製作体験会が開かれ、市内外の家族連れなどが参加した。参加者は市内の竹林から切り出された竹に、さまざまな模様がプリントされた型紙を貼り、電動ドリルで穴を開ける作業を体験した。

好みの模様の型紙を選んで竹に貼り付ける/1日、製作体験会(根浜シーサイド・レストハウス)

子どもたちも電動ドリルの使い方を教わって穴開けに挑戦!
釜石市の法人スタッフの男性(37)は「自分で作ったものは記憶に残るし、津波や防災のことを知る良いきっかけになる」と取り組みの趣旨に共感。震災ボランティアが縁で同市に移住した。仕事で子どもたちと関わるが、「自然の中で活動することも多い。楽しさだけでなく、時には怖い面も持ち合わせていることを知ってほしい」と自然災害への心構えも伝えていきたい考え。
北上市の羽藤翔さん(38)は家族ぐるみで初めて作業を体験。「誰よりも夢中になっています」とドリルを動かした。子どもたちは震災を知らないが、「昨年12月の大きな地震は怖かったよう」。その時に沿岸には津波もあることを教え、「震災や防災のことも勉強しに来たいと思っていた。今回はとてもいい機会。楽しみながら学んでもらえたら」と期待を寄せた。

模様にそって大小の穴を開ける。ここから明かりが漏れるしくみ

今年は竹の耐久性を高めるために背面にあらかじめ切り込みを入れる工夫も(左)。先端を斜めに切ったことで右下のようなデザイン(ニコちゃんマーク)も可能に
多くの人たちの手で完成させた竹灯籠54本は、キャンプ場から高台の市道箱崎半島線につながる津波避難階段に取り付けられた。今月14日に点灯式が行われ、製作に関わった人たちなど約30人が集まった。発電機のスイッチを入れると、竹の中に仕込んだLED電球の明かりが漏れ、“命を守る道”が浮かび上がった。親子らが自分たちで作った灯籠を探しながら、階段を上り下り。美しい光景を写真に収め、「津波時は高台へ―」という避難行動の基本を改めて脳裏に刻んだ。

みんなでカウントダウンをして竹灯籠に点灯。子どもたちがさっそく駆け上がる。階段は111段

実際に避難階段を歩いてみる。いざという時の「命を守る行動」を体験

「あなたもにげて」「上へ上へ」と文字を浮かび上がらせる灯籠も。高台避難の大切さを伝える
家族4人で製作にも参加した大槌町の男性(44)は「それぞれデザインが違う。いっぱいあると、こんなにきれいになるんですね」と驚いた様子。震災の津波で同町の実家が被災し、祖父母が犠牲になった。当時、自身は仙台市に住んでいたが、実家の再建のため3年後にUターンした。「あっという間の15年。震災で人生も大きく変わった…」。4歳の娘にも震災のことを伝えているが、「(避難訓練をしていることもあり)どうやら理解しているよう」。震災を経験していない世代が着実に増えていく中、「こういうイベントで、みんなの思いが形になるのはすごくいいこと」と、震災を“忘れない”思いを共有する。

階段を上がった先には複数の竹を組み合わせたものも。子どもたちの目もくぎ付けに…
津波避難階段は2021年に完成。キャンプ場や芝グラウンドがある観光施設「根浜シーサイド」から迅速な高台避難が可能。同DMC地域創生事業部の佐藤奏子さんによると、施設利用者には受付時に必ず、同階段の存在といざという時の避難について口頭で説明している。夜間は施設スタッフがいなくなるが、キャンプ場利用者とは連絡が取れる態勢を取っており、昨年、夜に地震が発生した際は「この階段を上がって避難した」との連絡があった。毎年の竹灯籠設置効果もあり、「階段の周知が進み、避難への意識付けも図られている」という。

写真上部に点在するのはキャンプ場の照明。津波の恐れがある時はこの避難階段を使っていち早く高台へ!
佐藤さんは「皆さんが変わらず、追悼の思いを持って作ってくれた」と竹灯籠作りへの協力に感謝。点灯期間中、多くの人に足を運んでもらい、「追悼、震災伝承、避難の大切さをみんなで共有し、いざという時に命を守れるようにしてほしい」と願う。点灯のための発電機の燃料には、地域の廃食油を精製したバイオディーゼル燃料が使われていて、太陽光発電も活用し、未来の持続可能な地域づくりにも貢献する。