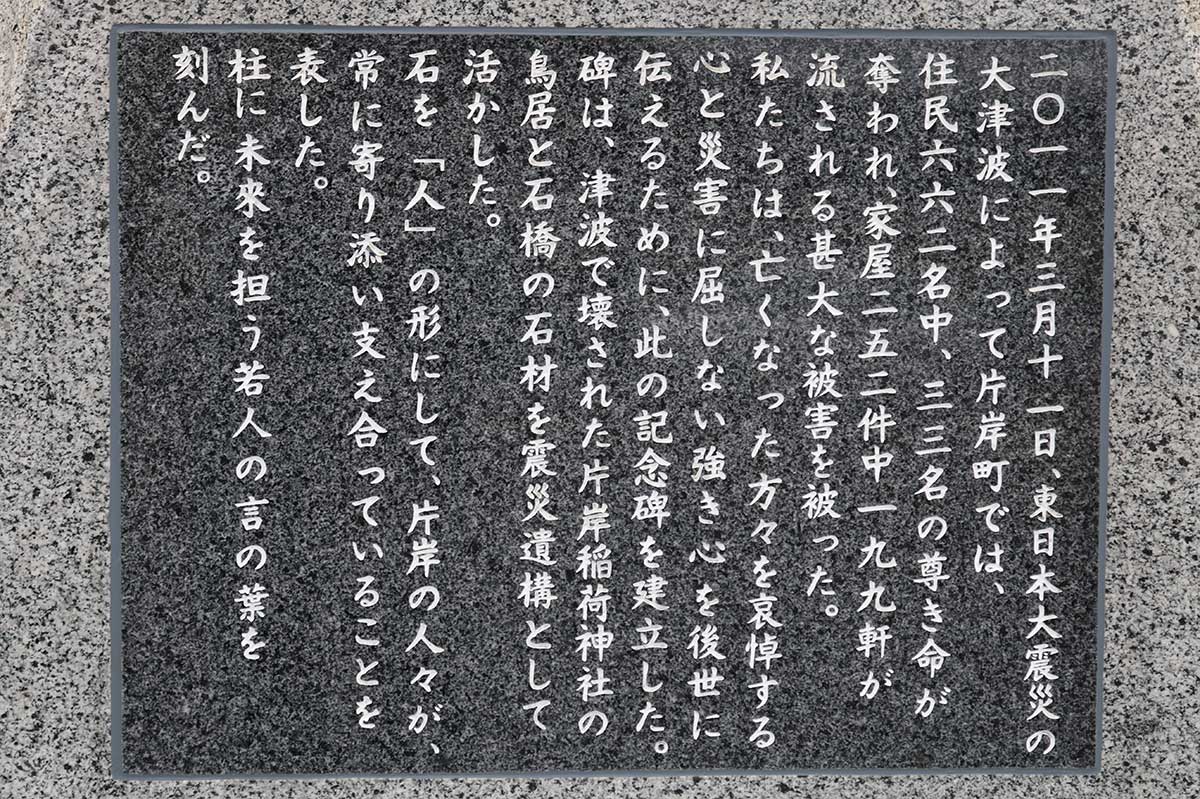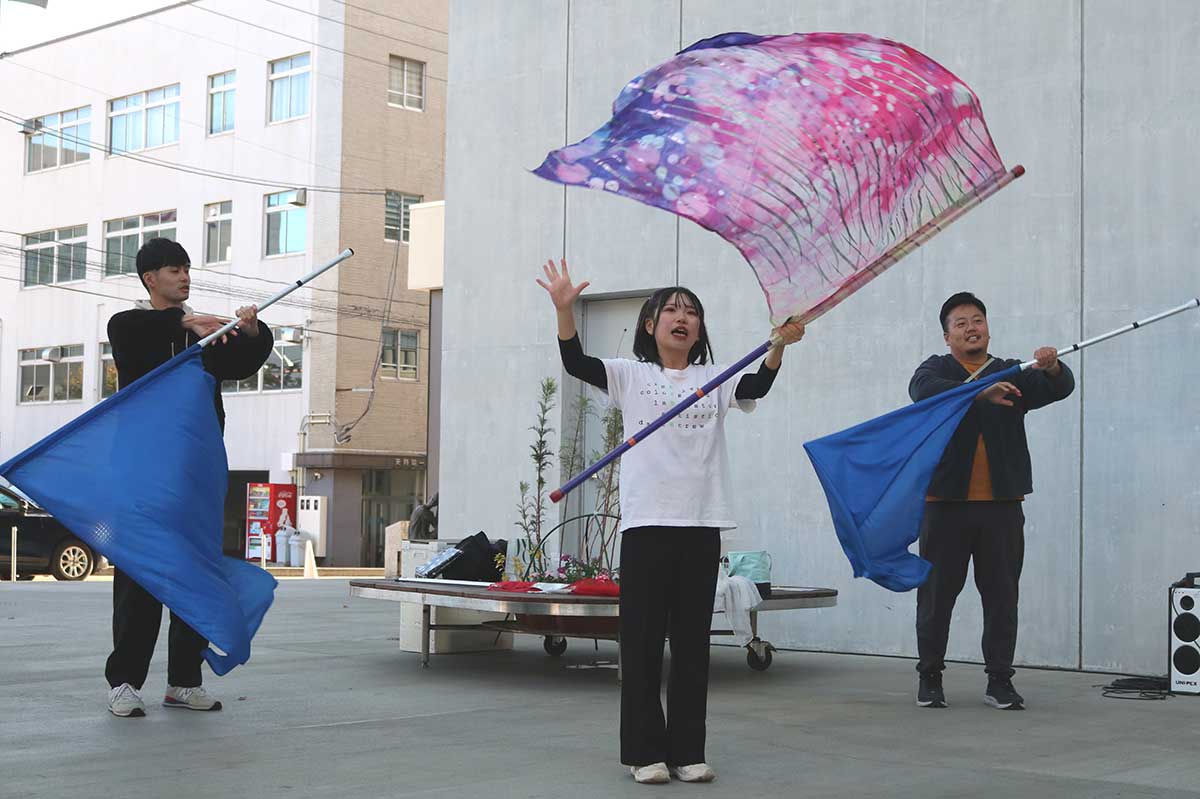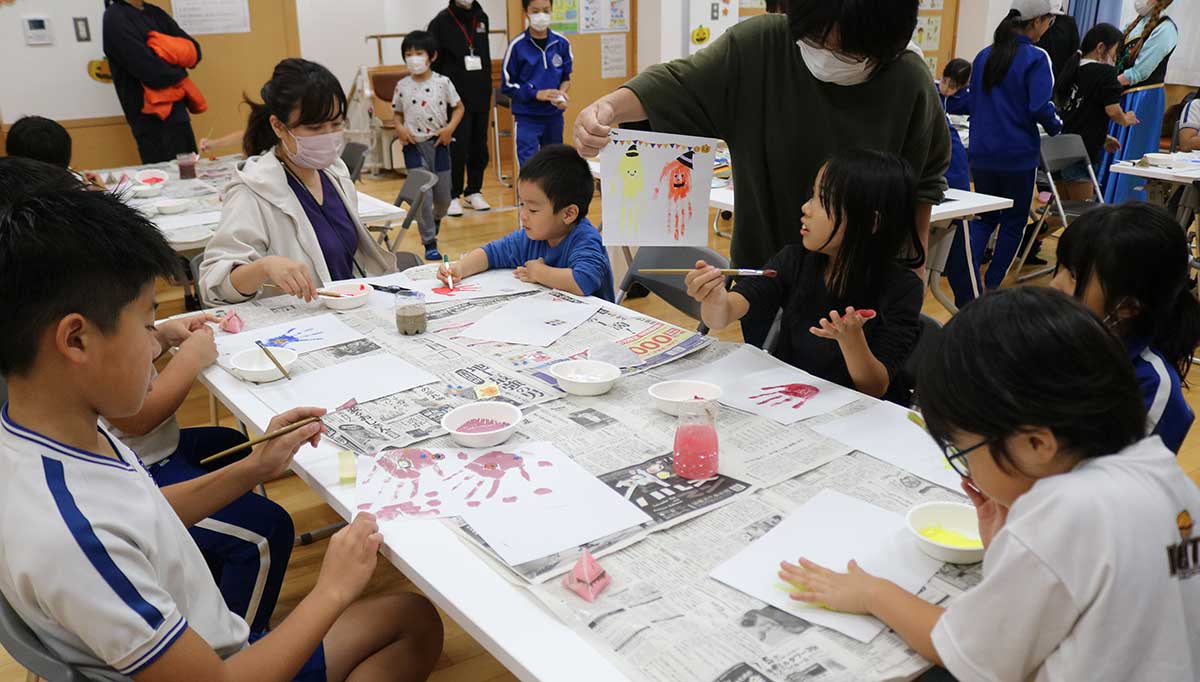4年ぶりに開かれた「かまいし仙人峠マラソン大会」=10月29日
第14回かまいし仙人峠マラソン大会(同実行委主催)は10月29日、釜石市甲子町大橋の旧釜石鉱山事務所を発着点に行われた。新型コロナウイルス感染症の影響で2020年から3年間中止されてきたが、今年待望の復活を遂げた。全国から集まった17~89歳の男女243人が出場。雨が降ったりやんだりのあいにくの空模様となったが、見ごろを迎えた美しい紅葉や沿道の声援に力をもらい、日本屈指の難コースを走り切った。
大会はこれまで、大松で折り返す10キロコース(標高差約160メートル)と仙人トンネルまでを往復する峠コース=17.2キロ(同約400メートル)の2コースで行われてきたが、今回は約10キロに短縮した峠コースに絞って実施。エントリーした281人のうち243人が出場した。
開会式で小泉嘉明実行委会長(市体育協会長)、野田武則市長が参加者を歓迎。ゲストランナーとして招かれたマラソン“川内3兄弟”の三男川内鴻輝さん(出場3回目)、山岳ランニングで国内トップの吉住友里さん(同2回目)が同コースの魅力を話し、「一緒に頑張ろう」と呼び掛けた。

参加者の憧れ、ゲストランナーの川内鴻輝さん(右)と吉住友里さん(左)
午前10時、小泉会長の号砲で一斉にスタート。陸中大橋駅方面へ約1キロ下った後、国道283号に出て約4キロの上り坂へ。遠野市との境、仙人トンネル手前の折り返し地点までひたすら続く坂道を駆け上がった。復路は一転、下り坂へ―。最後の難関はスタート直後に下った坂道。今度はゴールまで上る形となり、参加者は残る体力と精神力で完走を目指した。ゴール付近では、仲間や家族が声援を送り、完走後は共に喜びを分かち合った。

午前10時、旧釜石鉱山事務所前を一斉スタート

大橋トンネルを抜け、仙人峠頂上を目指す参加者

ゴールまであと少し。熱い声援を受け、最後の力を振り絞るランナー

釜石市でダンス教室を開く澤田稔さん、美世子さん夫妻は手を取り合ってゴール!
全参加者中、トップでゴールしたのは宮古市の宇部雄太さん(25)。タイムは39分57秒で、2位と約2分の差をつけた。レース後、男女年齢別6部門で1~6位を表彰した。

後続を引き離し、トップでゴールした宇部雄太さん(左)。復路の2位争いはデッドヒート(右)

6部門で1~6位を表彰。入賞者には賞状や記念品が贈られた
最年少参加者で今大会唯一の高校生、遠野高2年の佐々木寧音さん(17)は「思ったよりきつい。今まで走ったことがない難コース」と驚きの初体験。父譲さん(47)の影響で小学校から長距離走を始め、同大会も父の背中を見て応募した。初の親子参加に「感無量。よくゴールした。一緒に完走できてうれしい」と喜ぶ譲さん。自身は今回で3回目の参加だが、峠コースは初挑戦。「足がやられた。でも完走できたので自分を褒めたい」。一緒にトレーニングに励むこともある寧音さんを「心の友」と表し、「東京マラソンに出てみたい」と目標を掲げる愛娘に温かいまなざしを向けた。

最年少、唯一の高校生参加者の佐々木寧音さん(左)は選手宣誓も務めた。父譲さんと完走の喜びを分かち合う(右)
釜石移住の仲間と初挑戦したのは、同市に移住して1年の会社員三浦万侑さん(25)。写真で見た仙人峠の紅葉に魅せられ「楽しめそう」と申し込んだが、「坂、やばいです。折り返し前、中盤ぐらいが一番きつかった」と苦笑い。長距離走自体経験がなく、普段はたまにスポーツジムで汗を流す程度。大会2~3週間前から3~4キロ走るのを繰り返し、本番に臨んだ。「(成果は)出せたと信じたい。制限時間内にゴールできたので」。雨ながら肉眼で見る紅葉は格別で、「感動です。途中で写真も撮りました」と記憶と記録に残した。

釜石移住者仲間で参加したこちらのグループは全員完走。喜びの笑顔を輝かせた
職場の仲間での参加も同大会おなじみの光景。今回、釜石税務署の職員4人は11月11日から始まる「税を考える週間」をPRしようと、そろいのTシャツ姿で初参加した。背中にはQRコードを大きくプリントしてアピール。伊東亮将さん(26)は「想像以上のしんどさ。上り坂で何回も心が折れかけたが、何とか気合いで乗り切った」。大和田純さん(28)は「税の広報もでき、全員完走。かなりの達成感。明日からまたみんなで仕事を頑張れそう」。応援に駆け付けた石亀博文署長(58)は「若い職員が何かできないかと考え、自ら行動してくれた。Tシャツも大会のために準備したもの。税に目を向けるきっかけ作りに頑張ってくれたことに感謝したい」と奮闘をたたえた。

「税を考える週間」をPRするTシャツ姿で走る釜石税務署の職員ら

完走した釜石税務署の大和田純さん(左)、安保充さん(中左)、伊東亮将さん(右)と石亀博文署長(中右)
今大会参加者の最年長は花巻市の仙内直衛さん(89)。同大会には所属する花巻走友会の仲間とほぼ毎回参加している。自身のスタイルを「“ずぼら”走だ。自分を追い込まず、完走できればいいという感じ」と屈託なく笑う。マラソンは50歳から始め、72歳までフルマラソンにも出場。「完走すると気分がいい。若い人たちと一緒に走れるのは楽しい」と心を躍らせる。今回も無理なく走り切った。

「最高齢者賞」を贈られた花巻市の仙内直衛さん(左)と松岡マヨ子さん(右)。年齢を感じさせない健脚ぶりに拍手!
仙内さんは、女子の最年長松岡マヨ子さん(77、花巻市)とともに「最高齢者賞」を受賞。最も遠くからの参加者に贈られる「遠来賞」は鹿児島県南さつま市から参加の中村貴子さん(45)が受賞した。
同大会は2010年にスタート。翌11年に東日本大震災が発生したが、「復興への峠を駆け上がれ」の合言葉のもと、大会は途切れることなく続けられた。12年の第3回大会で参加者数1011人と最多を記録している。今大会は3年間のブランクを経ての開催ということで、運営体制などを考慮し規模を縮小した。参加者からは大松コースの復活を望む声もあり、実行委では来年以降の形態を再度、検討していく。

ハロウィーン仕様のカラフル衣装で選手を応援。力をもらったランナーが急勾配の坂を駆け上がる

仮装ランナーは今年も健在。沿道の人たちを楽しませた