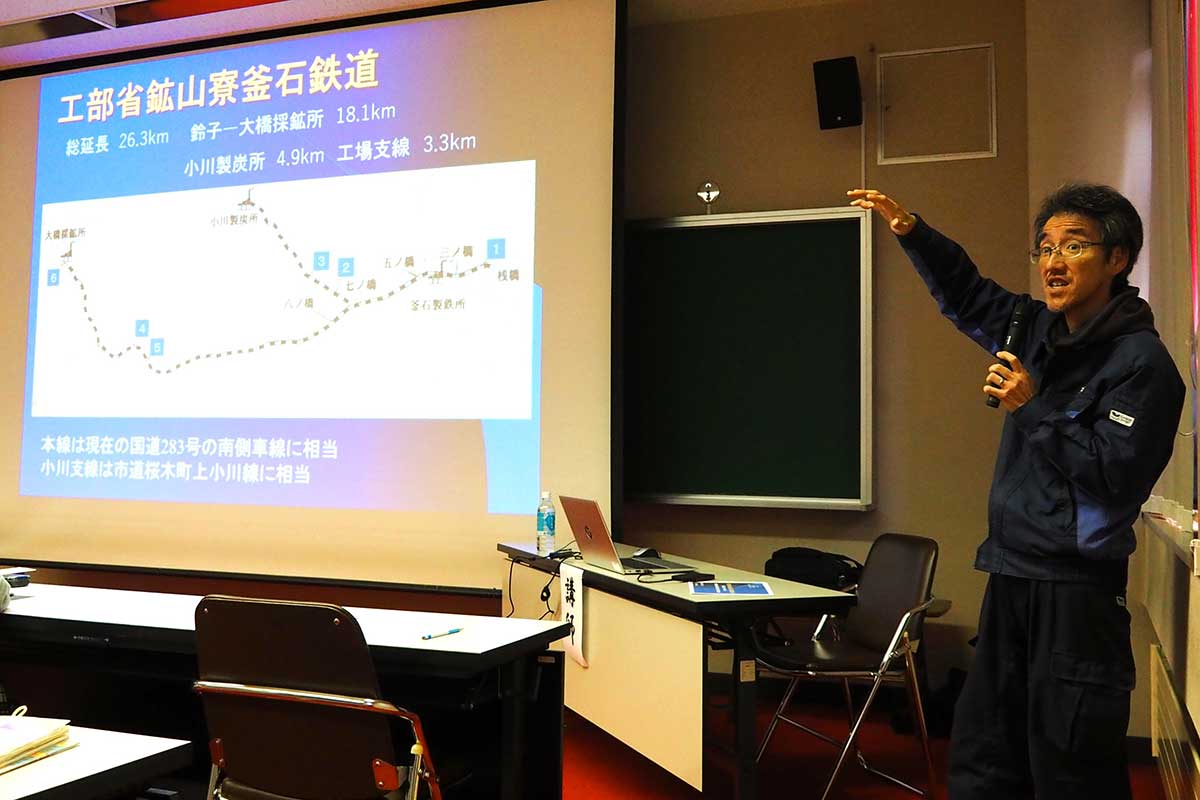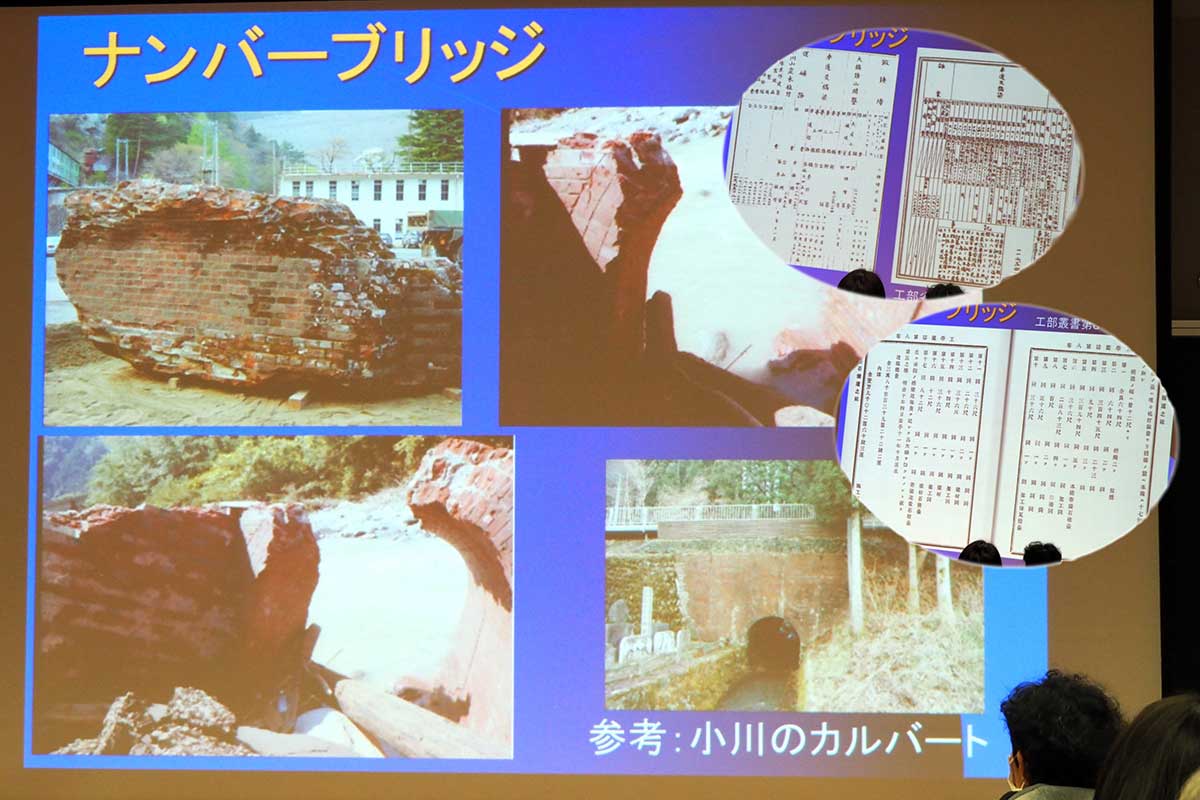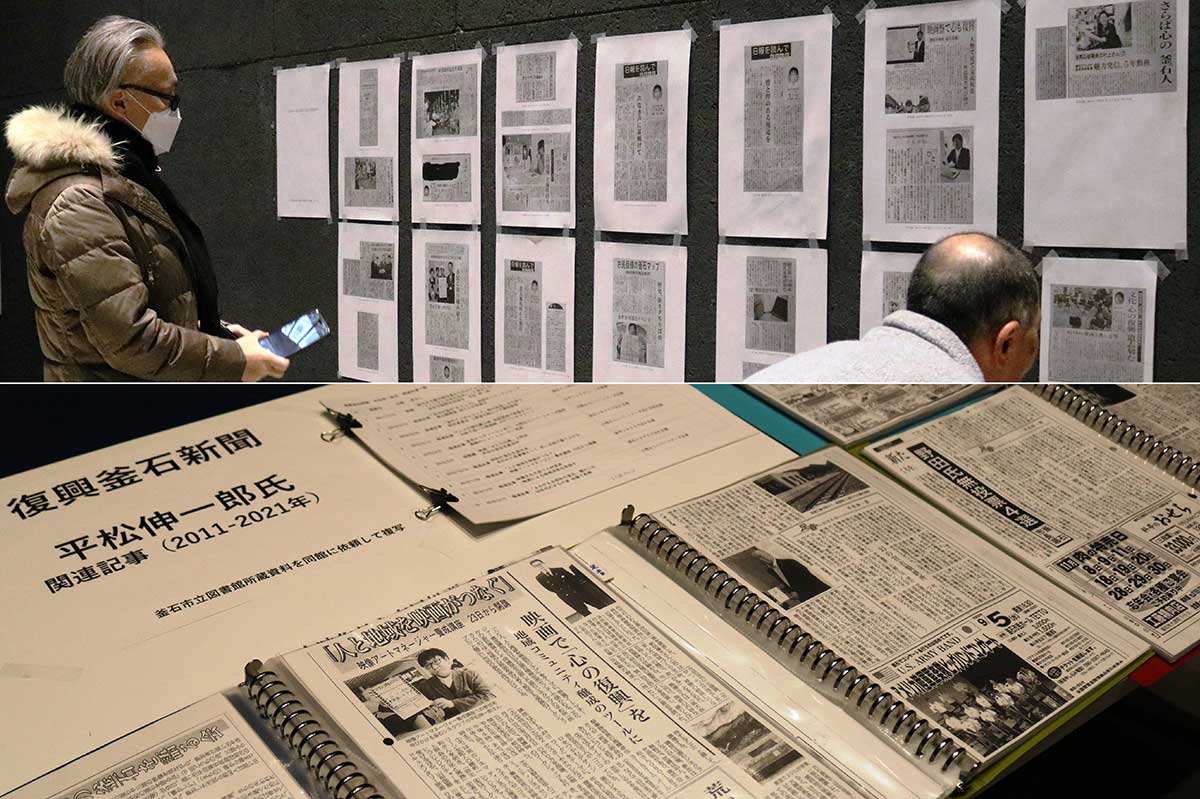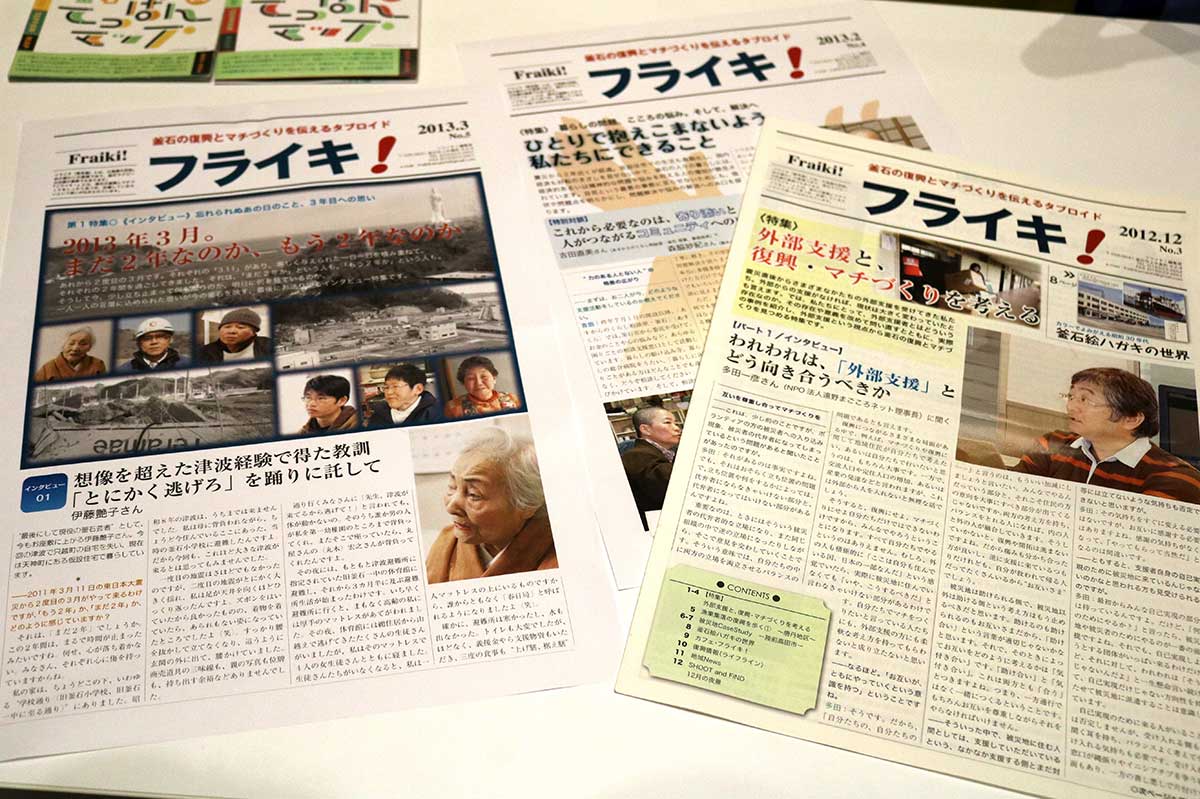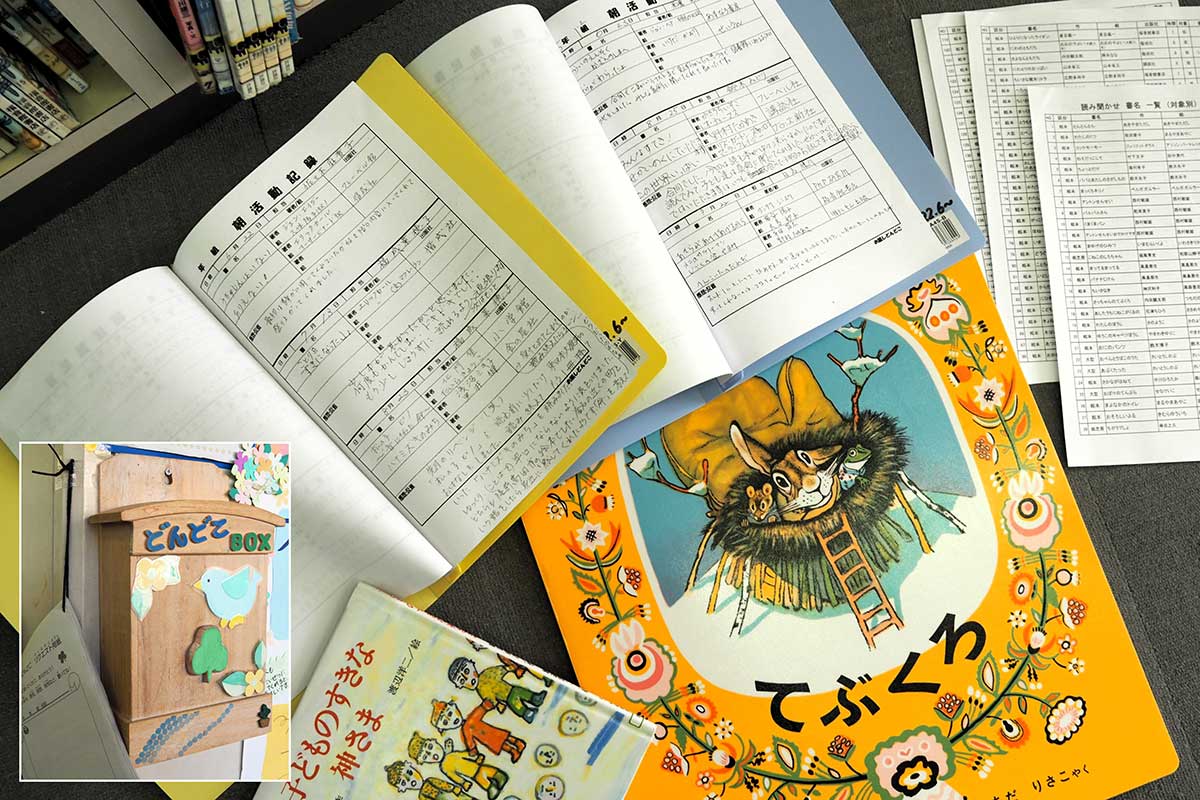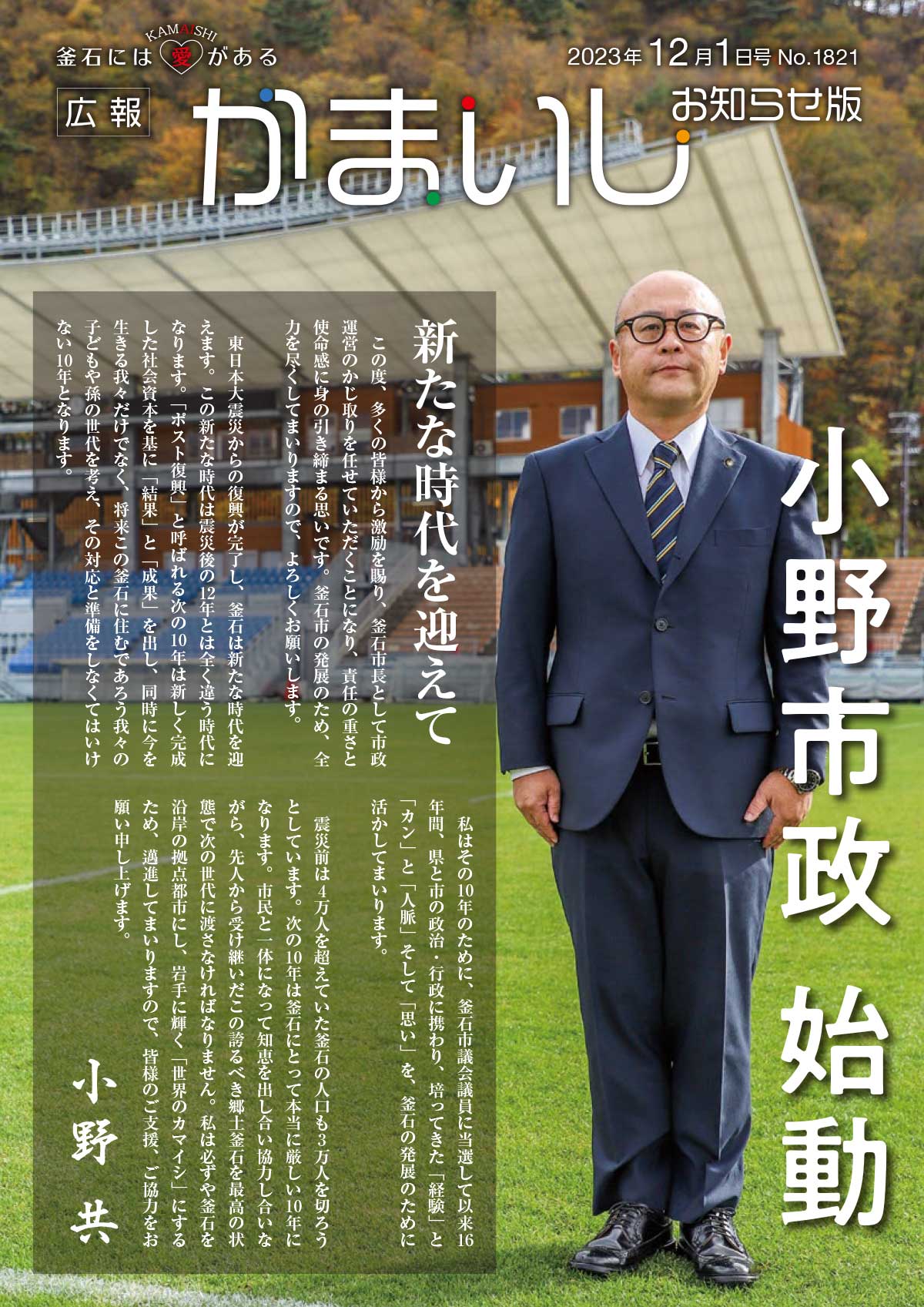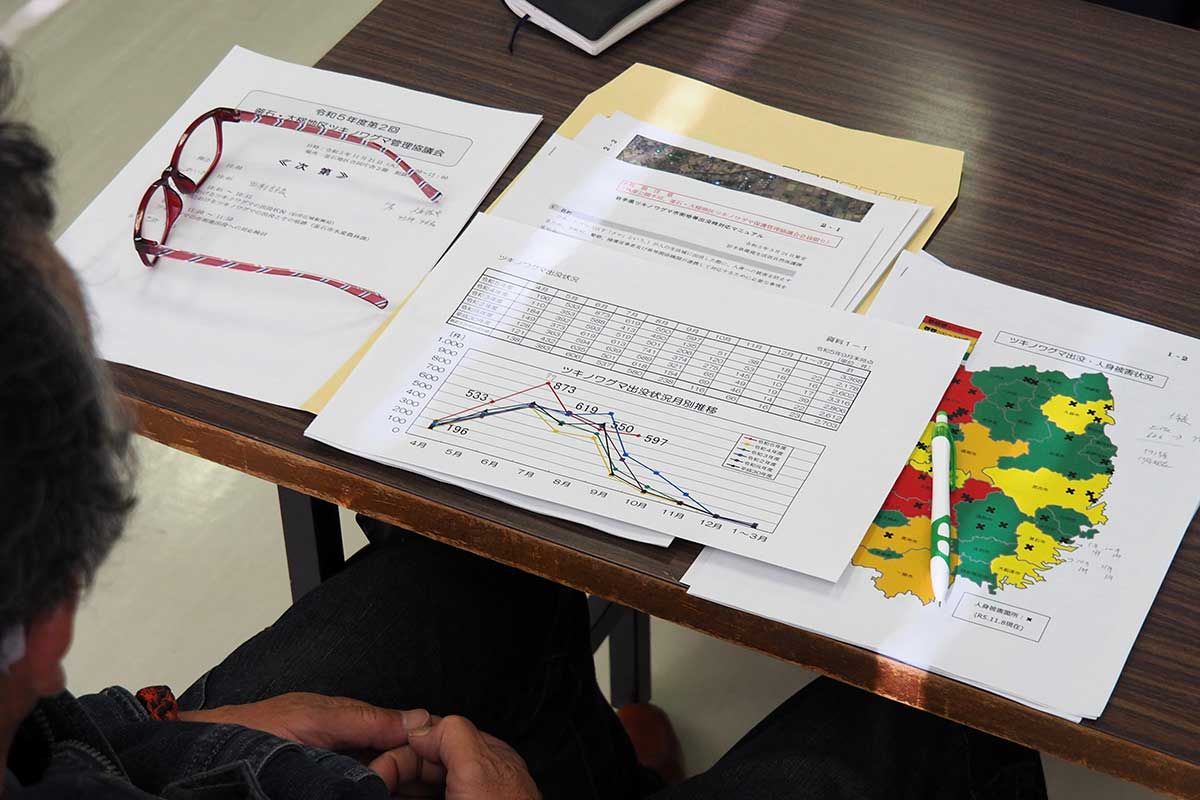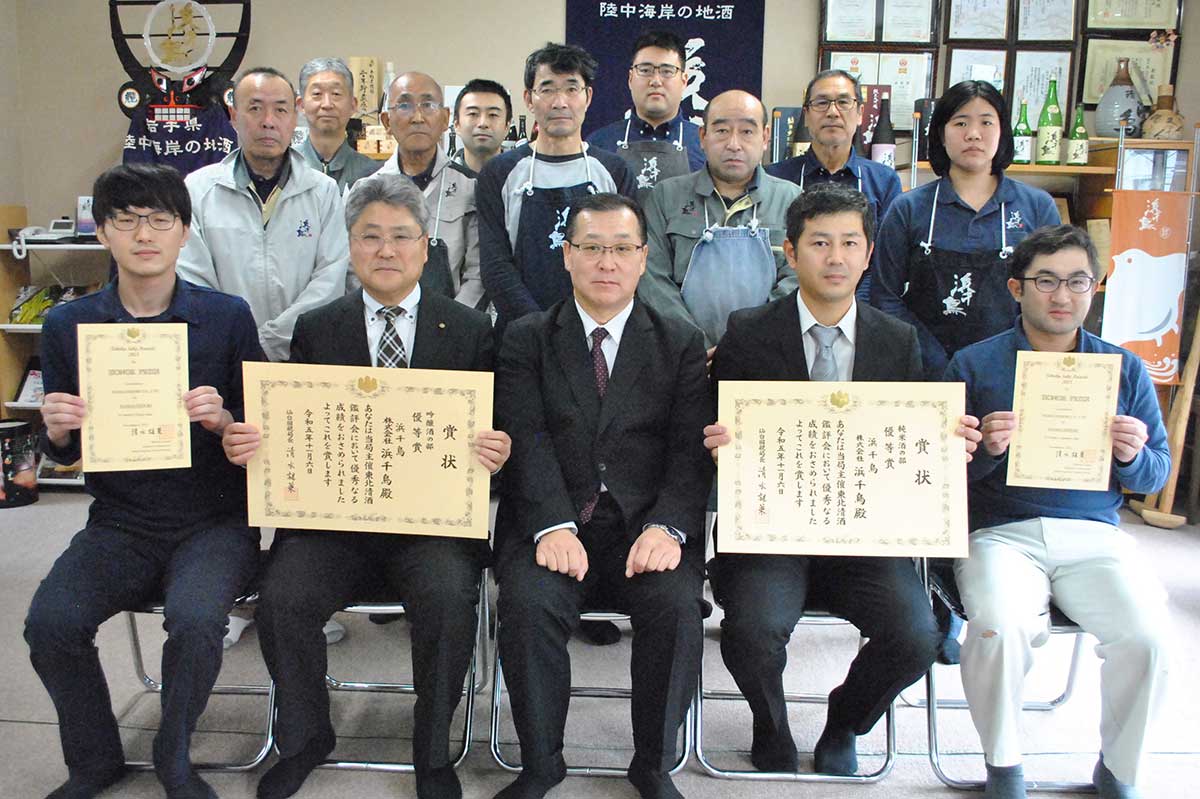/// 人の手助けができるサバイバルマスター®️に ///
全国の子どもたちにお願いです。
災害時は、大人たちだけでは対応できないことが次々に起こります。
そんな時のために一緒に学び続けよう。
8つのサバイバルプログラム
講習を受けると修了証、実技・筆記試験に合格するとワッペンがもらえます。
スキルが身についているか?学んだことを理解しているか?が合格の基準。
8つのプログラムすべてのワッペンがそろうと「サバイバルマスター®️」として認定されます。
サバイバルマスター®️1DAYチャレンジ!フード編チラシ(PDF/14.9MB)
スケジュール
10:00 受付開始
10:30 講習開始
このスキルを身に着けたら、どういった場面で役にたつか、学びながら練習しよう!
12:00 昼食
非常食を食べてみよう!
13:30 筆記試験
知識がしっかり身についているかテスト!
13:50 ふりかえり
14:00 解散
インストラクター
伊藤 聡
さんつな 代表
釜石高等学校 探求学習講師「防災ゼミ」
72時間サバイバル教育協会 認定ディレクター
釜石生まれ釜石育ち。
東日本大震災で自身も被災したものの、生まれ育ったまちを取り戻すため、ボランティアコーディネートを中心とした活動からスタート。
自然と災害という二つの要素を織り交ぜながら、子どもたちの生きる力を高めるために、様々な体験機会のコーディネートを行っています。
<<主な資格>>
防災士、防災検定2級、JVCAボランティアコーディネーション力検定2級、MFAメディック・ファーストエイド チャイルドケアプラス
お申し込み
予約フォームよりお申し込みお願いします!
https://reserva.be/santsuna
日程:2023年12月24日(日)
定員:15名(先着順)
※最小催行:3名
料金(税込):各回3,000円/一人あたり
※プログラム費、検定費、保険代など含みます
※助成金により、通常の参加費(5、500円)より割安になっています
対象:小学3年生以上
※子ども向けの内容ですが大人も参加大歓迎です
集合時間:10時受付開始
会場:根浜レストハウス キャンプ場
(釜石市鵜住居町第21地割23番地1外)
持ち物・注意事項:
●参加費は当日受付でお支払いお願いします(現金、PayPay、かまいしエール券)
●保護者や、対象年齢以外のご家族の付き添い(見学のみ)可能です
主催・お問い合わせ
さんつな(三陸ひとつなぎ自然学校)
LINE https://lin.ee/RvMUVBk
TEL 0193-55-4630 / 090-1065-9976
mail hitotsunagi.main@gmail.com
主催
さんつな
協力
72時間サバイバル教育協会
Tri4JAPAN