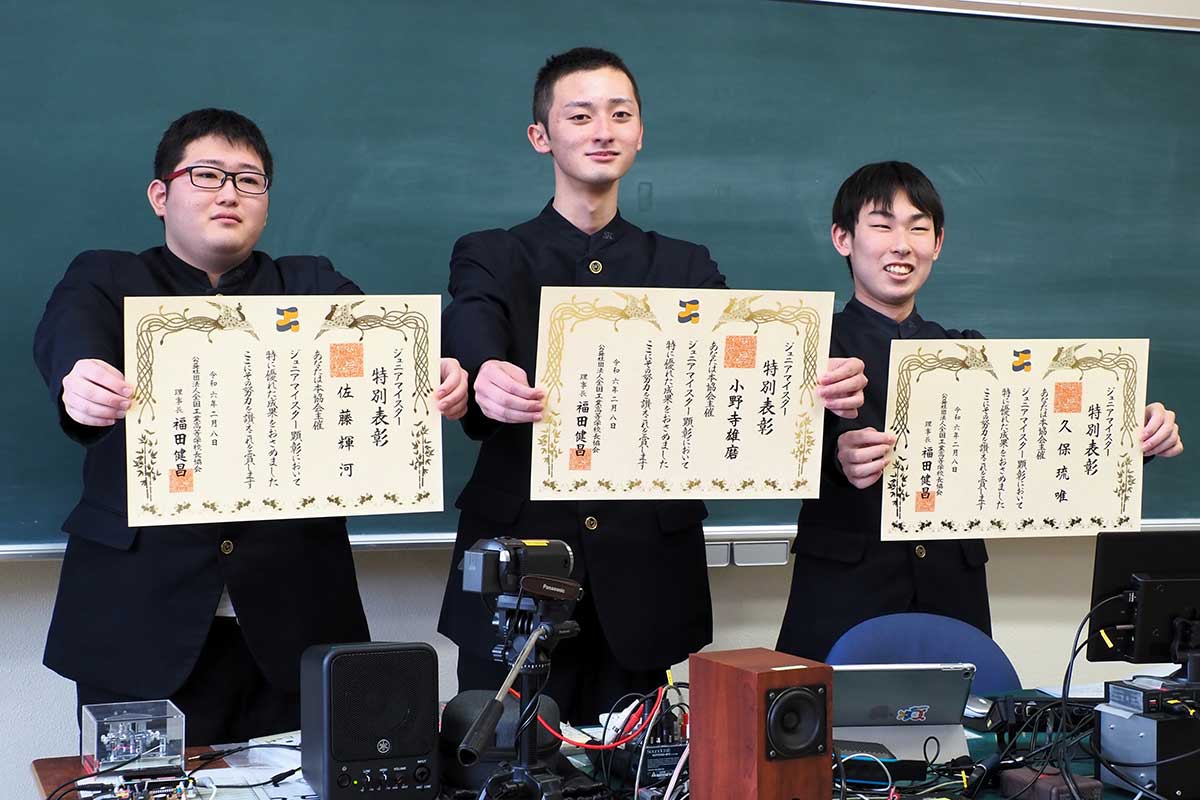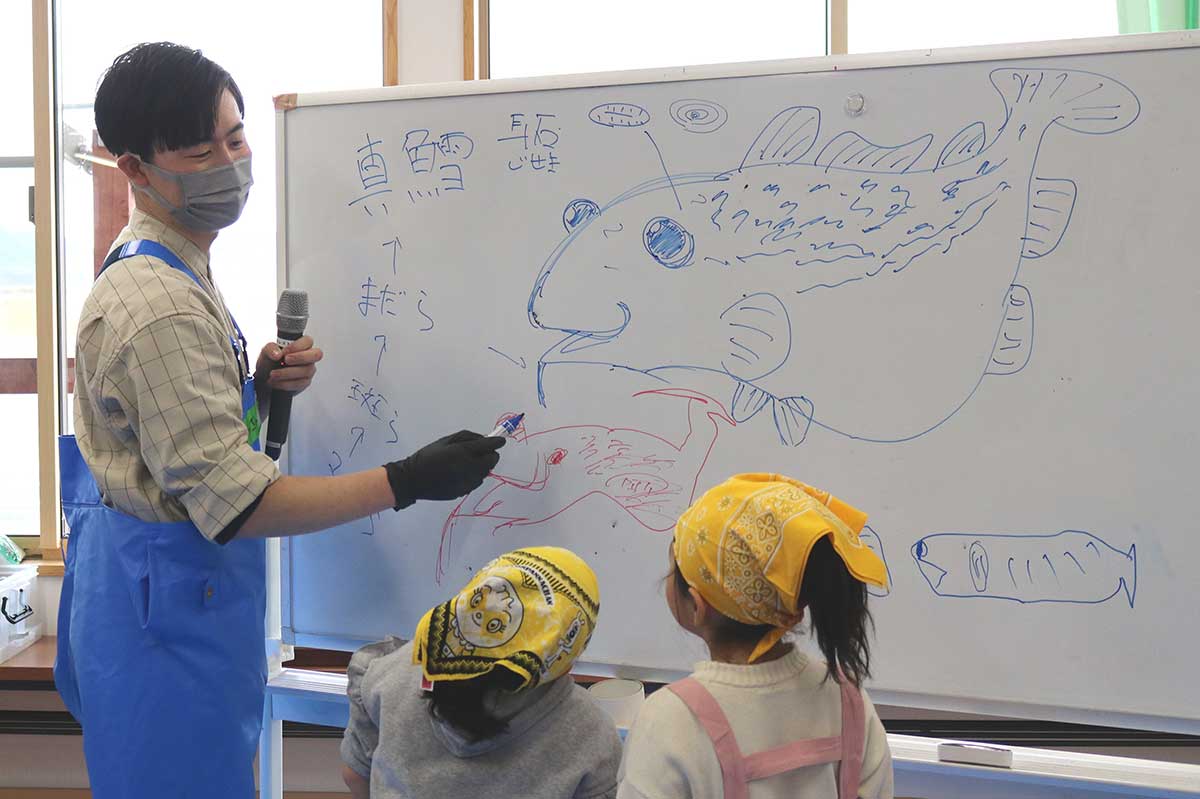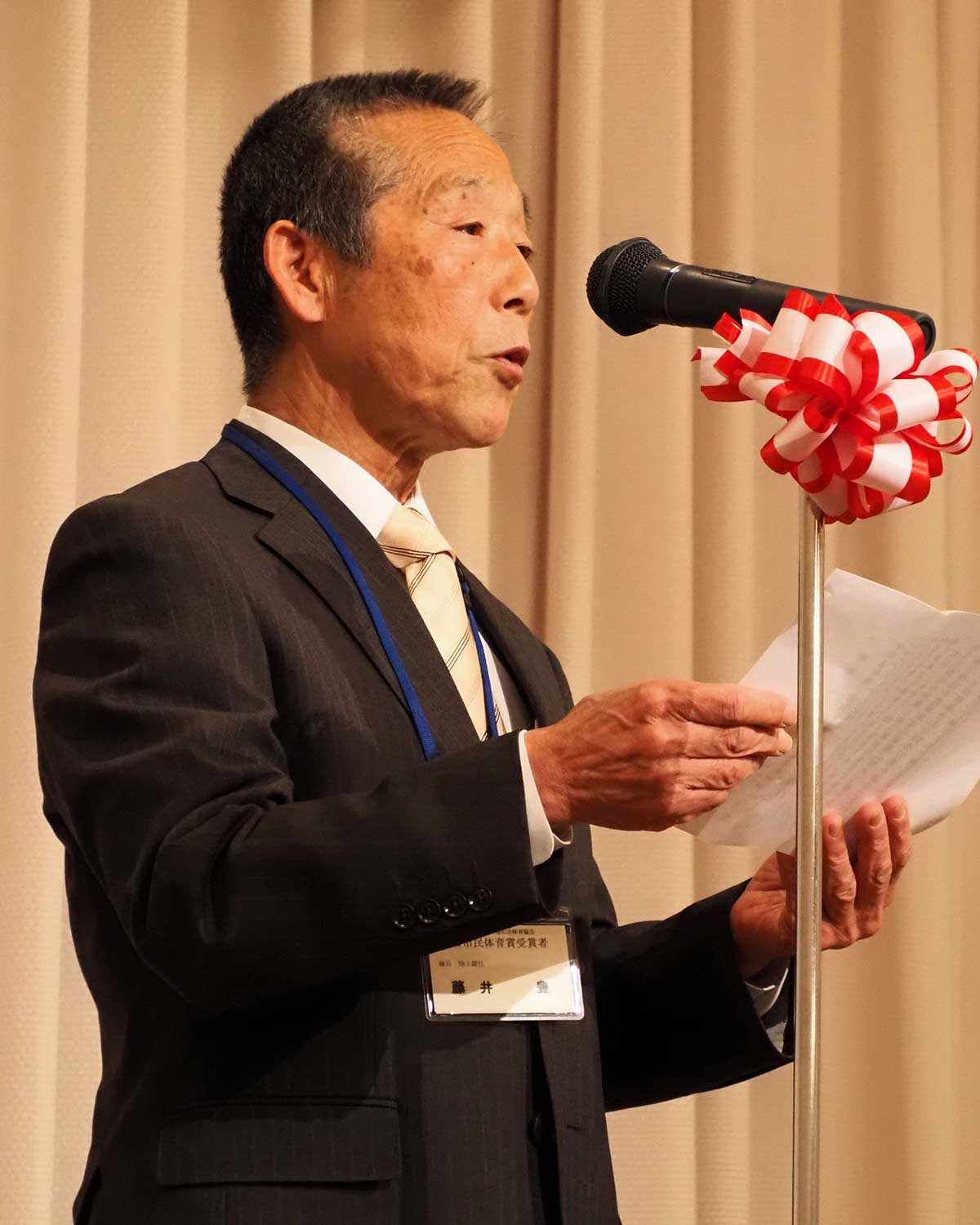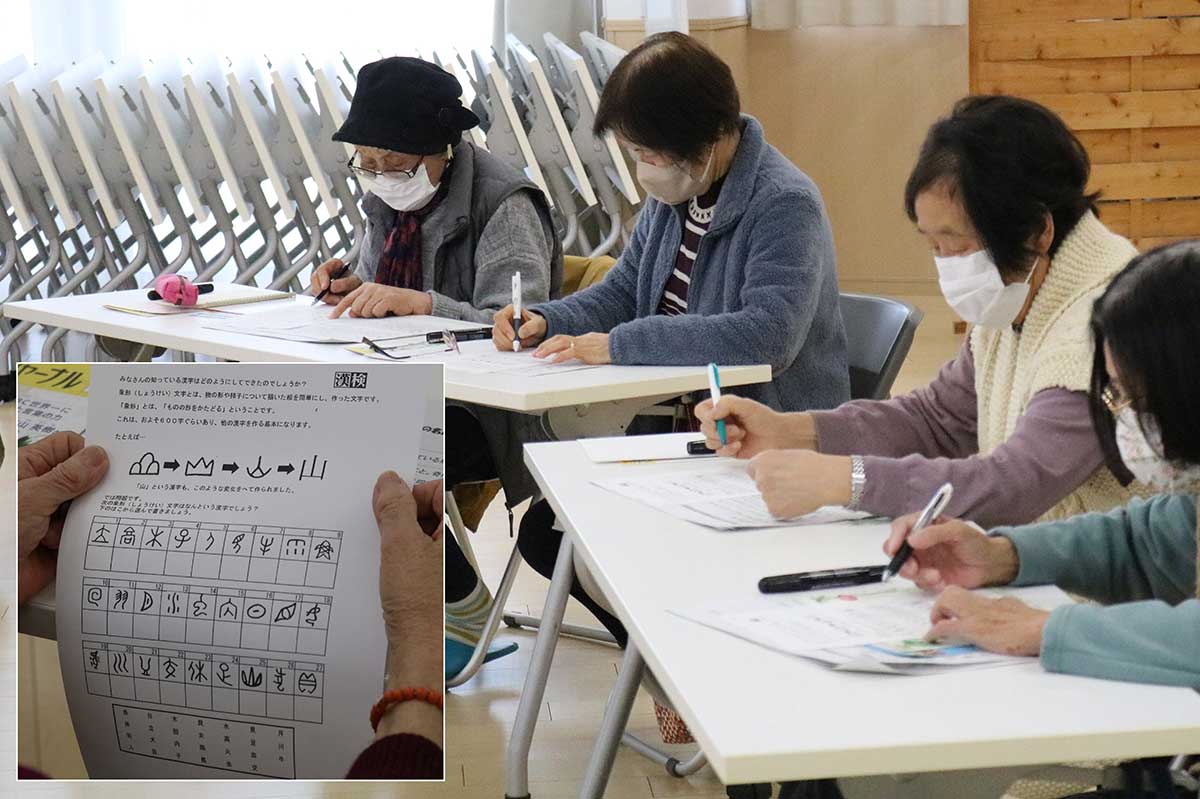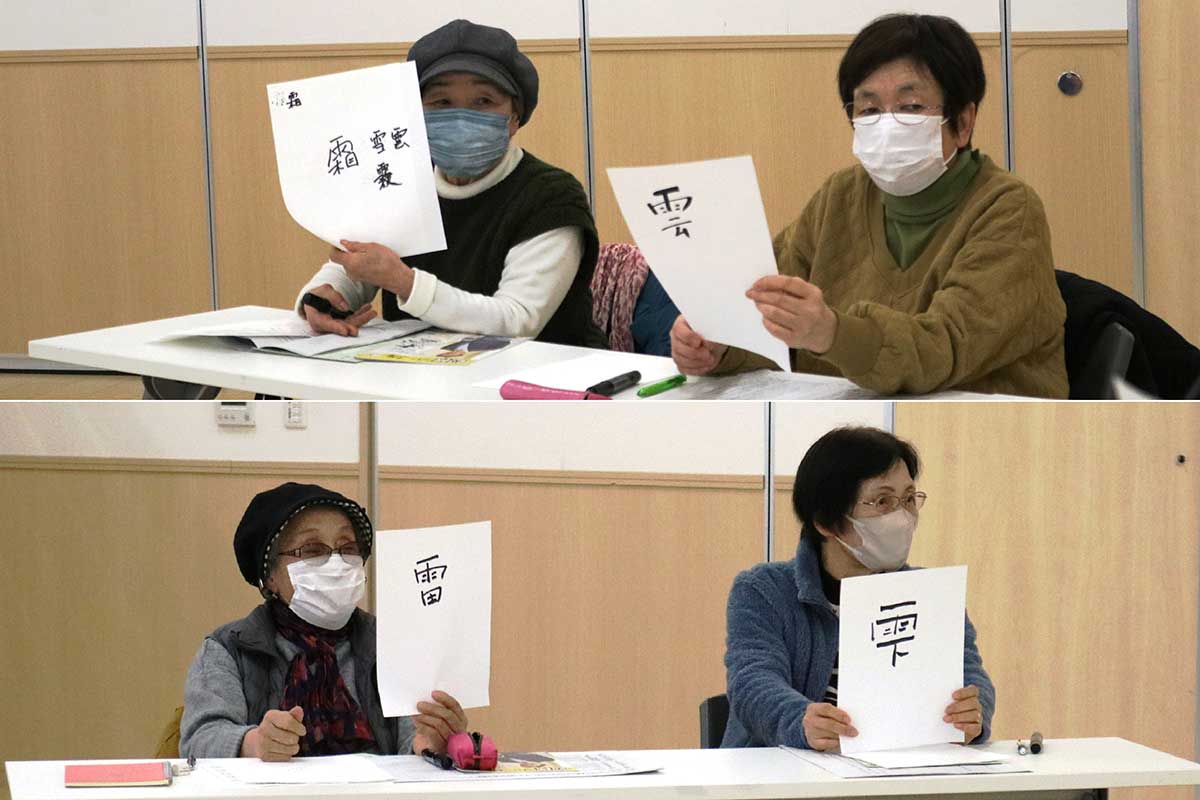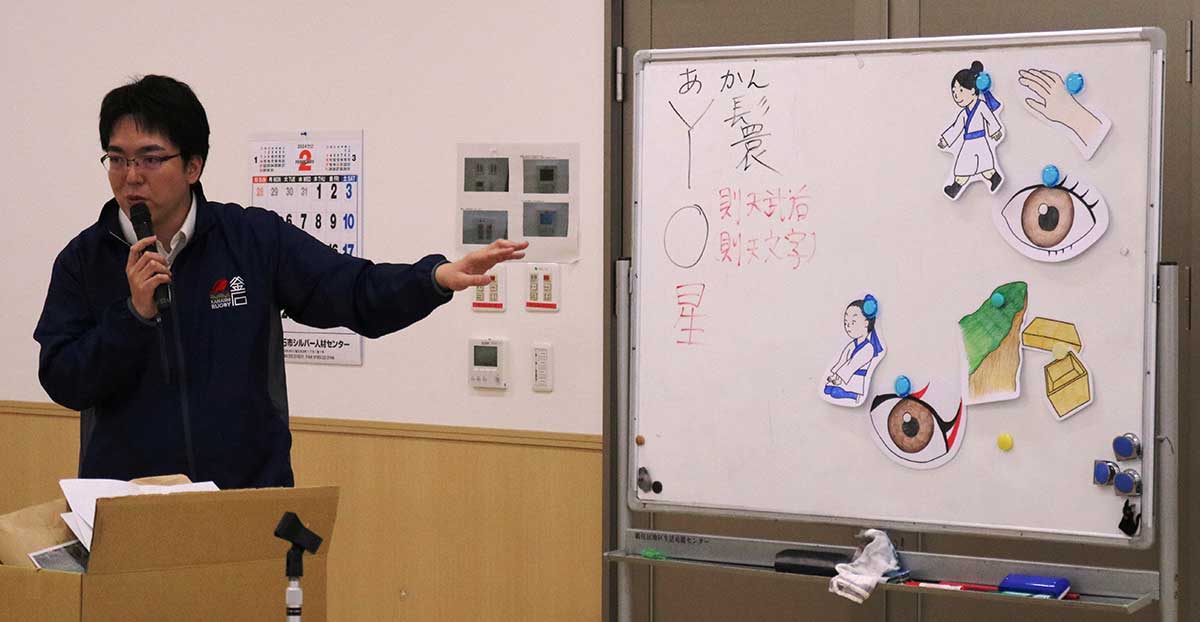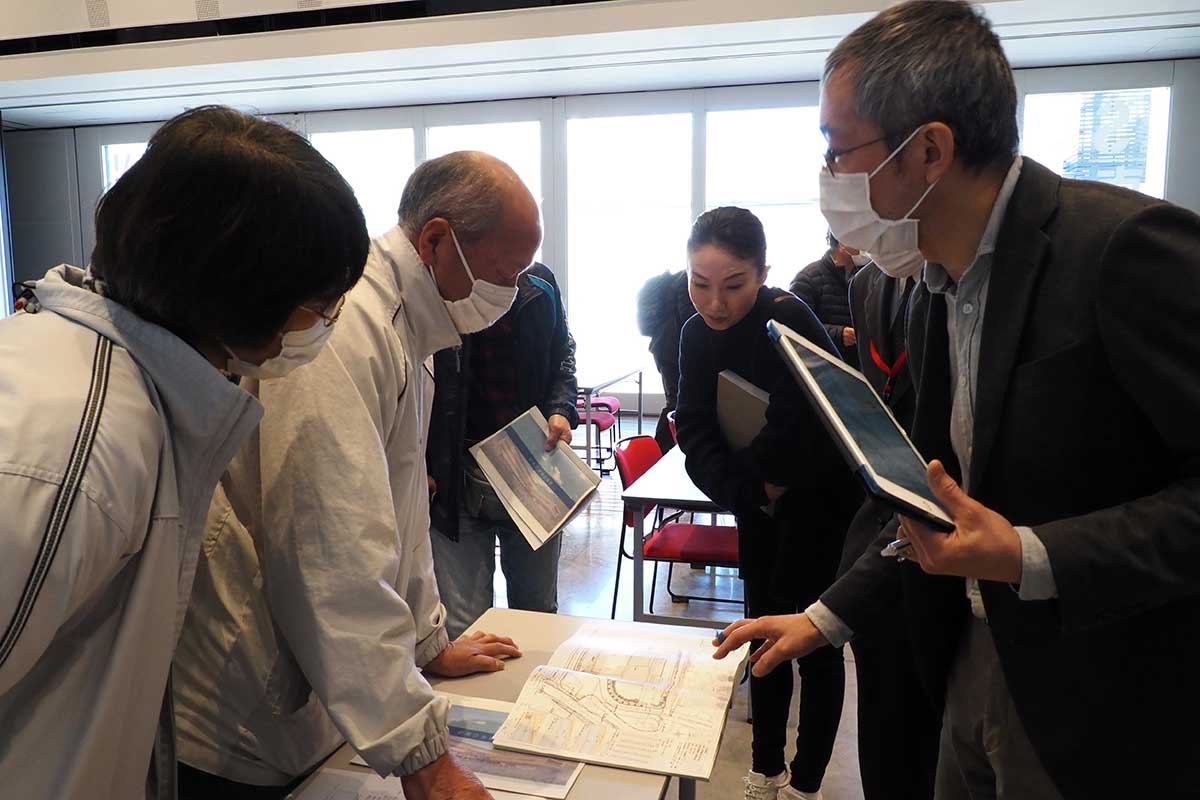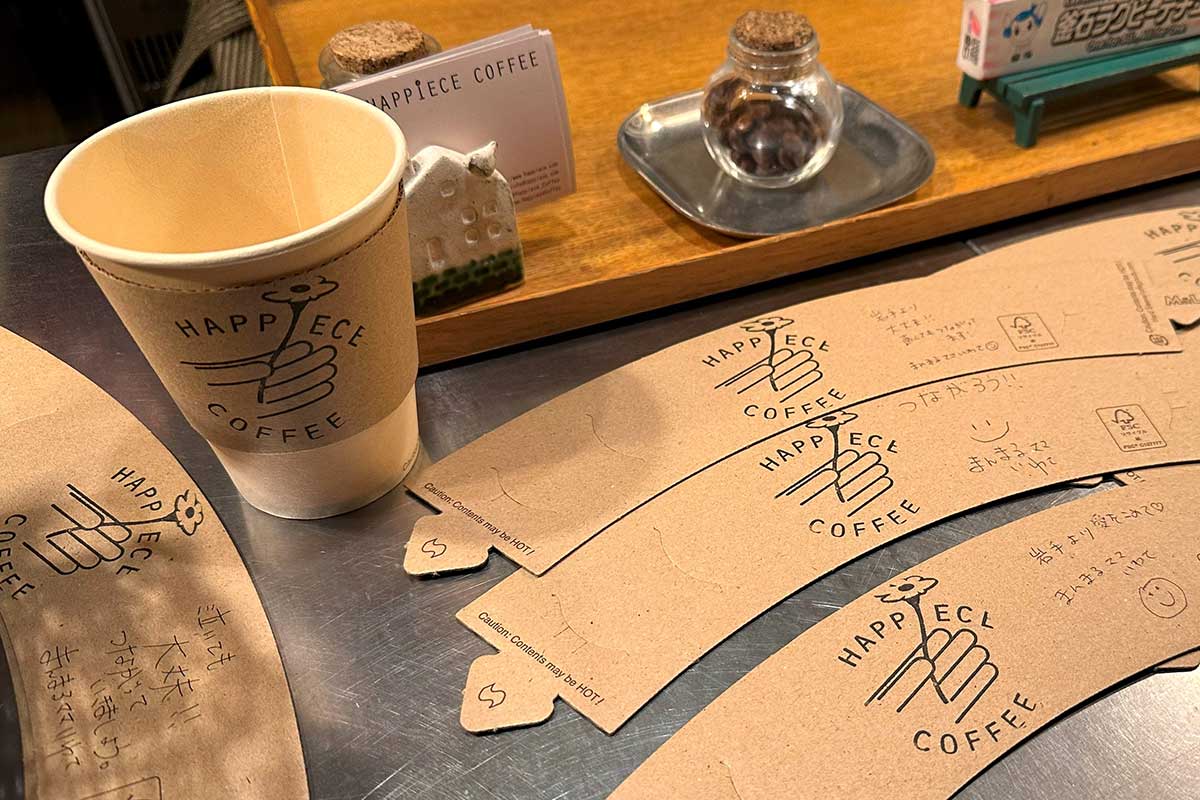大観衆の中、行われた釜石SW(赤)対九州KV(青)の試合=10日、釜石鵜住居復興スタジアム
NTTジャパンラグビーリーグワン2部の日本製鉄釜石シーウェイブス(SW)は10日、釜石市の釜石鵜住居復興スタジアムで九州電力キューデンヴォルテクスと対戦。28-11(前半13-8)で今季初の勝利をもぎとった。翌日は東日本大震災から13年となる日―。被災した小・中学校跡地に建てられたスタジアムで、チームは常に「自分たちがここで戦う意義」を意識し続けてきた。選手たちの思いが体現された特別な勝利に大勢の釜石ファンが沸いた。次の試合は17日。3日に雪の影響で中止された、第7節対NECグリーンロケッツ東葛戦が同スタジアムで行われる。
日本製鉄がマッチスポンサーとなったこの日の試合は全席無料招待。同スタジアムでの釜石戦最多の3947人が来場し、両チームに声援を送った。前半は九州が先制。釜石は22分、SO落和史がPGを決め波に乗ると、ゲームキャプテンのナンバー8サム・ヘンウッドが26、32分と立て続けにトライ。素早いパス、クイックスローなどの的確な判断で、しっかりと得点に結びつけた。13-8、釜石5点リードで前半を折り返した。

3947人が来場。大漁旗や来場者にプレゼントされた赤いミニフラッグが揺れる。試合前には震災犠牲者に黙とうがささげられた(写真右下)

前半26分、ナンバー8サム・ヘンウッドが右サイドを抜け初トライ。仲間の祝福を受ける

前半32分、ヘンウッドがこの日2本目のトライ。客席に大歓声が響く。クイックスローでパスを出したWTBヘンリージェイミーも喜びの笑顔(写真下段右)
後半も相手にプレッシャーを与えながら果敢に攻め込む釜石は開始3分、ゴール前でショートサイドへのパスを受けたFB中村良真が体を翻してトライ。18-8とリードを広げた。38分には敵陣10メートルライン付近から抜け出した中村が大外のWTBヘンリージェイミーにつなぎ、そのまま独走トライ。後半は相手にトライを許さず、28-11で勝ち切った。釜石のホームでの勝利は、前々季2022年5月の2部残留を決めた日野レッドドルフィンズ戦以来。

FW陣は押し負けないスクラムで相手にプレッシャーを与えた

うのスタ特有の風に悩まされながらも3本のゴールを決めたSO落和史(写真左)。体を張って前へ前へ進む釜石の選手ら(同右)

後半38分、FB中村良真(写真左下枠内)のロングパスを受けたヘンリージェイミー(右)が試合を決めるトライに持ち込んだ
試合後、釜石の須田康夫ヘッドコーチ(HC)は「やってきたことをパーフェクトに近い内容で遂行できた。自分たちの強みを一番出せる形、得意な分野を自信を持ってやるという仕組みが機能した」と勝因を説明。トレーニングでこだわってきたのはブレイクダウンでの圧力。「強いプレーを常に選択し、前に出続けて勝負サイドを攻略する」。仕切り直しとなる次のGR東葛戦も「自分たちの力が試されるゲームになる」と気を引き締めた。
ゲームキャプテンのサム・ヘンウッド選手は「今まで見た中で最高のパフォーマンスだった。チームをすごく誇りに思う」と胸を張った。釜石でプレーして4年目。毎年、同震災について学ぶ中で「聞けば聞くほど釜石という地域に親近感を持ち、(3月11日が)どれだけ大事な日かが分かる。受け取った思いがパフォーマンスにもつながっている」と話した。

今季初勝利に顔をほころばせる釜石の選手ら

勝利した選手をたたえるバックスタンド席の観客

試合後、客席に手を振り、応援への感謝の気持ちを表す選手ら
釜石SWは10日の試合を終え、1勝6敗勝ち点6で最下位。レギュラーシーズンは残り3試合。10日の震災復興祈念試合で見せた勝利への執念を次につなぎ、「最後まであきらめない釜石ラグビー」を見せてくれることを多くのファンが待ち望む。
10日のうのスタ 各種企画で大にぎわい 新日鉄釜石V7戦士らのトークイベントも

新日鉄釜石ラグビー部V7戦士トークイベント=10日
釜石SW対九州KV戦の会場となった釜石鵜住居復興スタジアムは、九州を含め全国各地から集まったラグビーファンでごった返した。キッチンカーなどで出店した市内外の業者によるフードコーナー、大型エア遊具やボール遊びを楽しめるキッズ広場がグラウンド周辺に開設された。1月1日に発生した能登半島地震の被災地応援コーナーも。越中の特産品などを釜石SWの選手らが販売した。

能登半島地震の被災地復興を応援するための物販ブース。釜石市の友好都市・富山県朝日町の協力で行われた
来場者が楽しみにしていたのは、約40年前に日本選手権で7連覇を果たした新日鉄釜石ラグビー部OBによるトークイベント。森重隆さん(72)=1974~82年・CTB、和田透さん(74)=68~82年・HO、石山次郎さん(66)=76~89年・PR、金野年明さん(66)=75~87年・CTB、千田美智仁さん(65)=77~92年・LO,FL,No8が招かれた(=在籍期間・ポジション)。

新日鉄釜石ラグビー部OBの(左から)森重隆さん、金野年明さん、千田美智仁さん、和田透さん、石山次郎さん
当時のスクラムの強さについて石山さんは洞口孝治さん(PR)、瀬川清さん(LO)らの名前も挙げ、「力関係や方向性がかみ合って形に表れた」と説明。和田さんはFW陣が強い当たりを身に付けるため、相撲部に練習に行っていたことを明かし、「スクラムで勝てないとラグビーは勝てないという精神でやっていた。練習はかなりハードだった」と振り返った。体幹の強さに定評があった千田さんはその要因を問われると、「家業の農業で足腰が鍛えられたのかも」と推測。部ではベンチプレスなどのトレーニング器具を自分たちで作っていたという。

和田さん(中央)ら当時のFW陣は釜石のスクラムの強さについて話した
正確無比のプレースキッカーとして注目された金野さんは「私の場合は間合いだけ。余計なことは一切考えず、無心で蹴るのが一番」と自身の経験を語った。森さんは当時の釜石の強さの秘密を「日本一になろうという気持ちが常にあった。『去年よりも練習しないと勝てない』と努力する姿勢。コミュニケーションがすごくとれていたのも大きい」と分析した。

ユーモアを交え、試合のキック秘話を語る金野さん(左から2人目)
2019年から日本ラグビー協会会長を務め、現在は名誉会長の森さんは「野球の大谷翔平選手のような、みんなが憧れる選手が出てくれるといい」と期待。19年のラグビーワールドカップ(W杯)釜石開催誘致に尽力した石山さんは「このスタジアムがもっとラグビーでにぎわってほしい。ラグビーを通じて人の輪(和)がつながっていけば」と思いを寄せた。
宮古市の山根正敬さん(66)は5人の紹介パネルに掲載された選手時代の顔写真に「当時の活躍が思い浮かぶ。今日は練習風景の裏話も聞けた。皆さんのメッセージも良かった」と大感激。釜石SWにも「1部進出を果たしてほしい」とエールを込めた。

往年の名選手に熱い視線を向けるトークイベントの観客