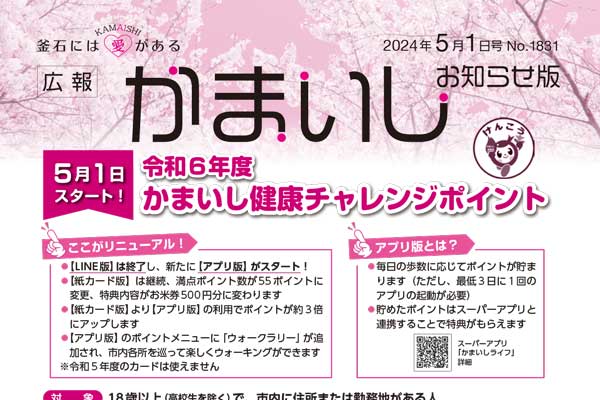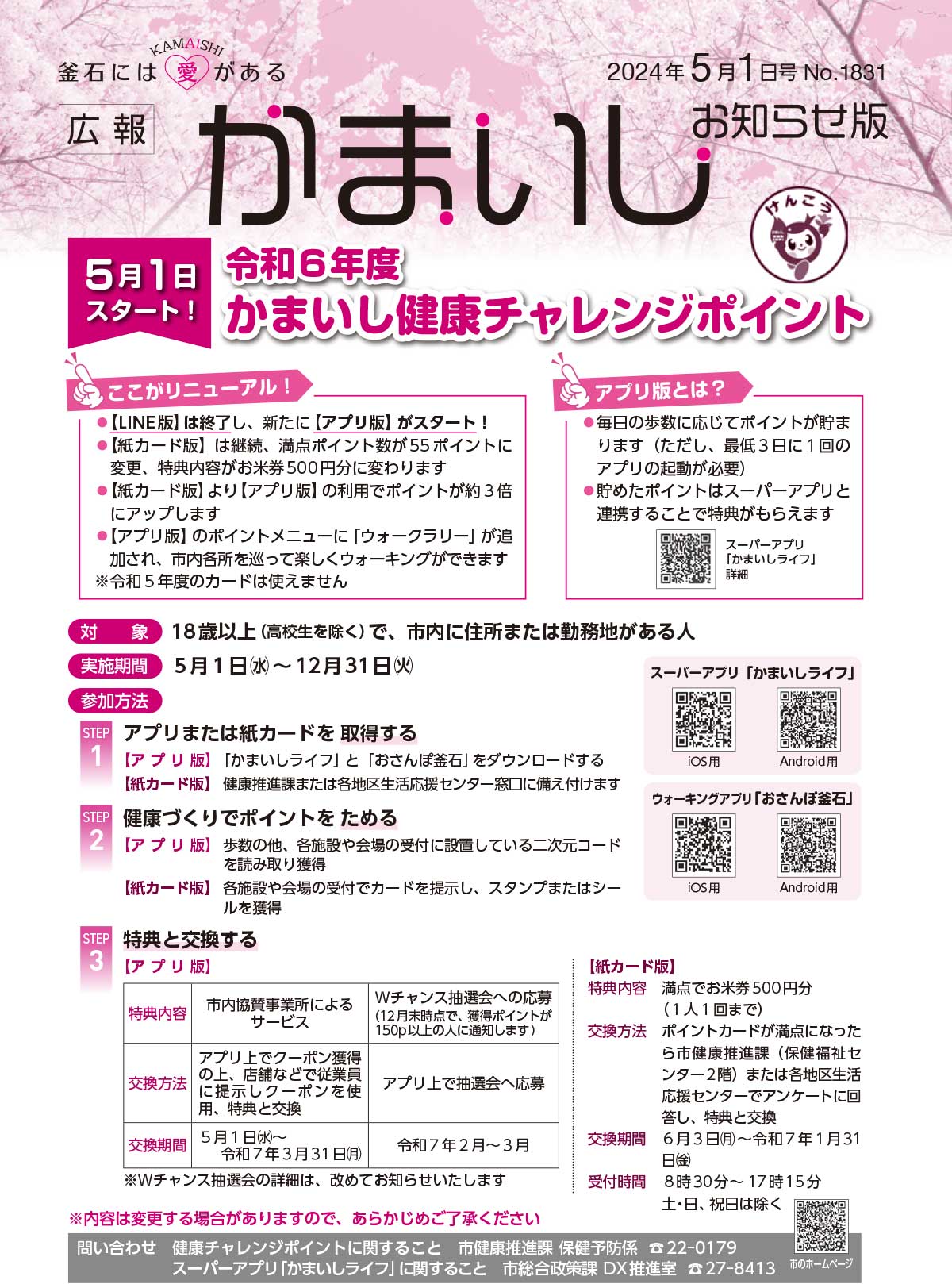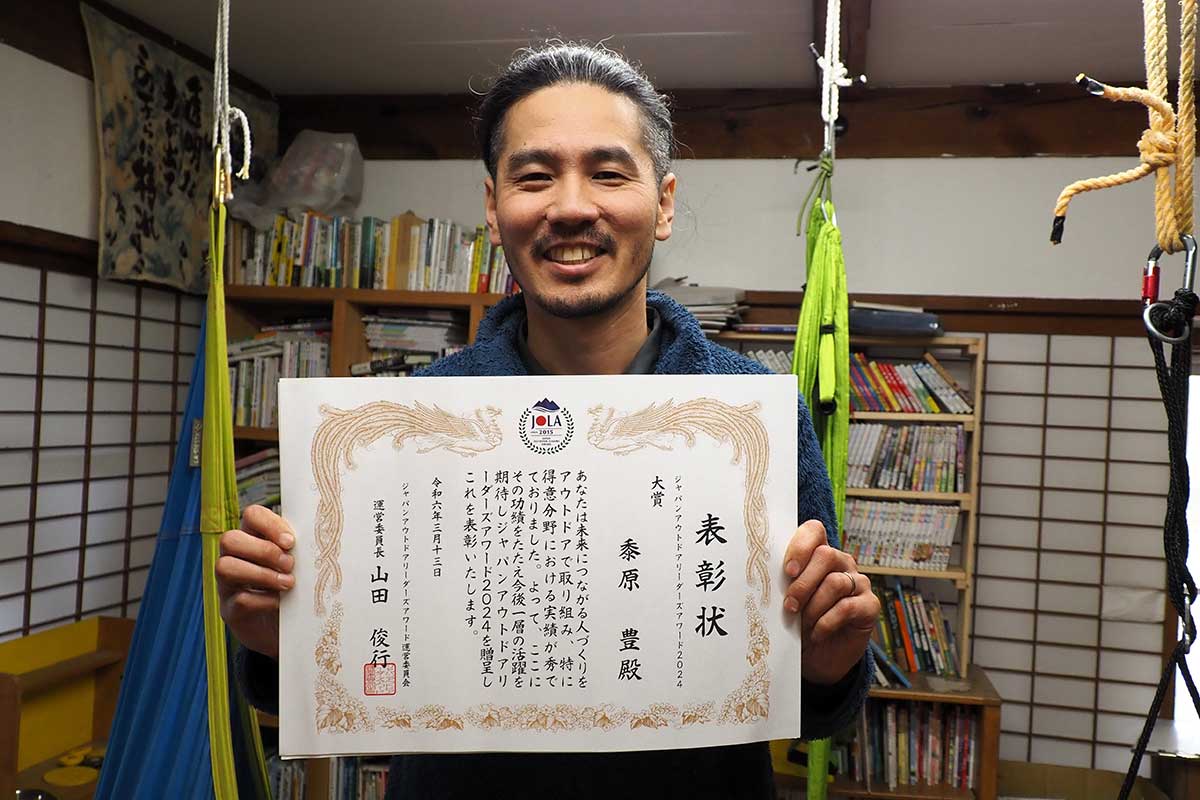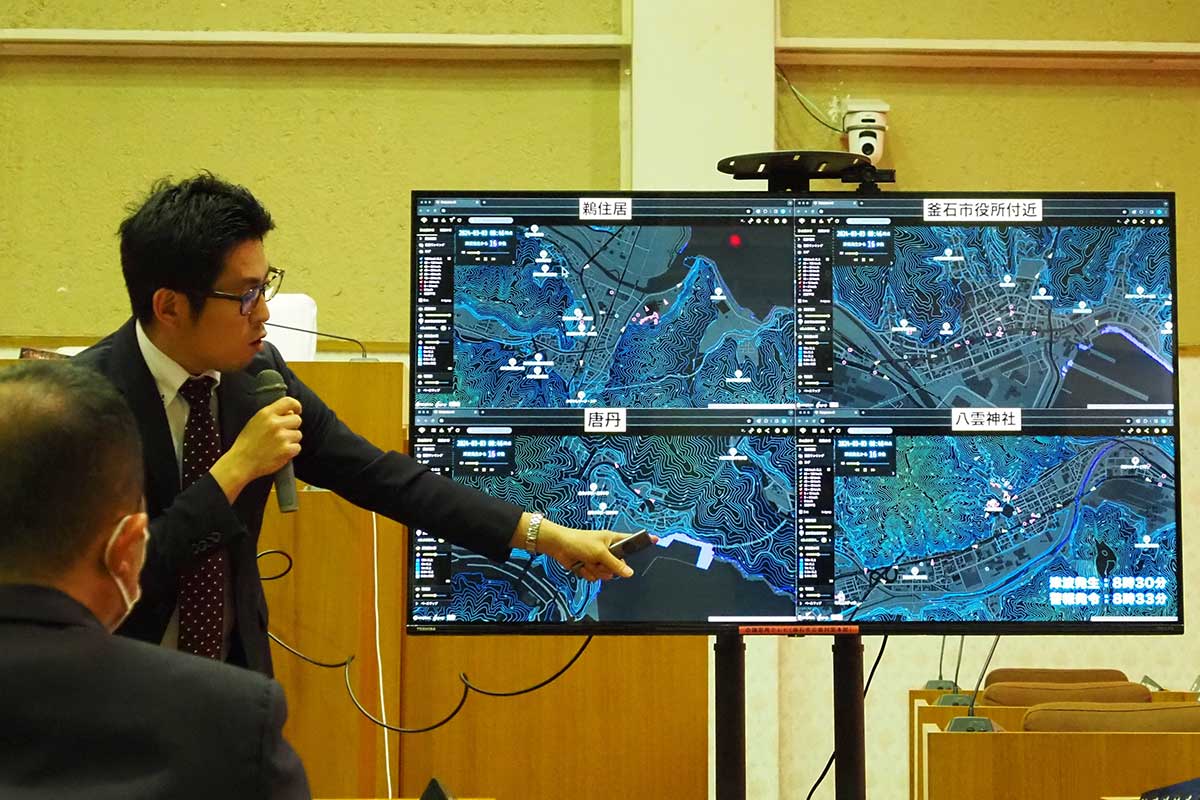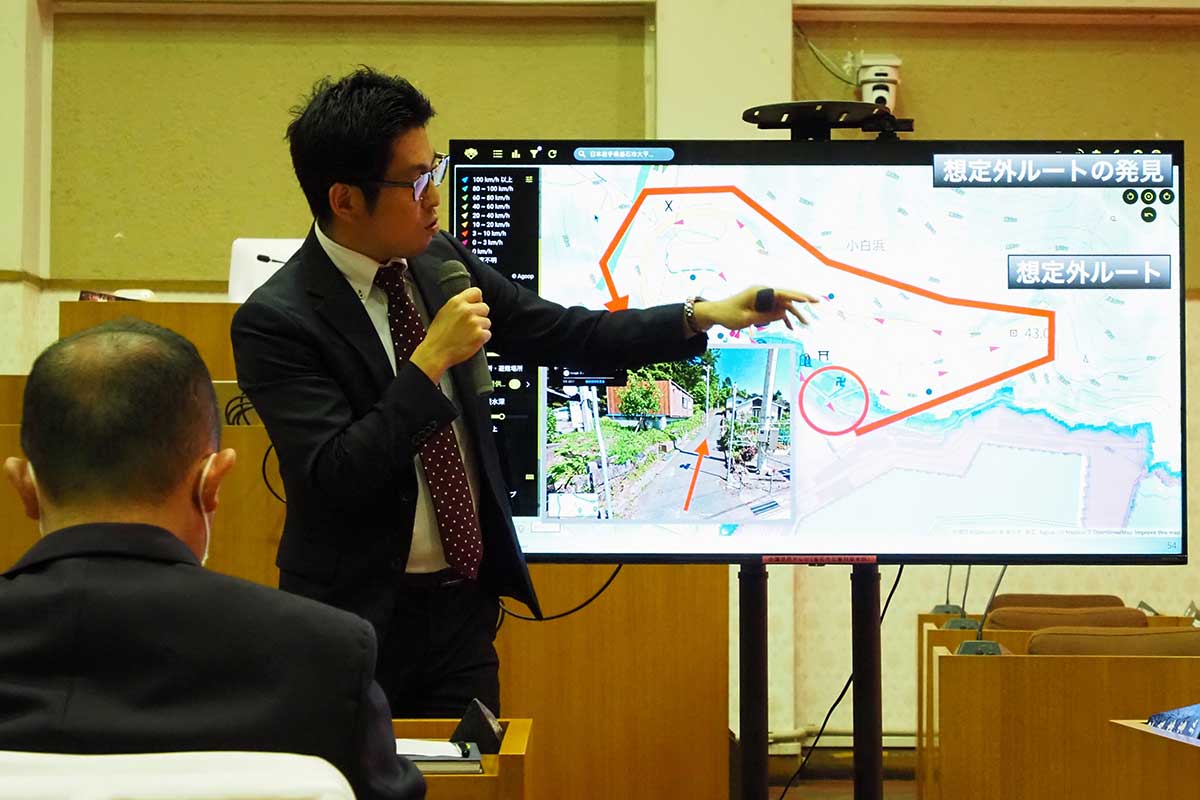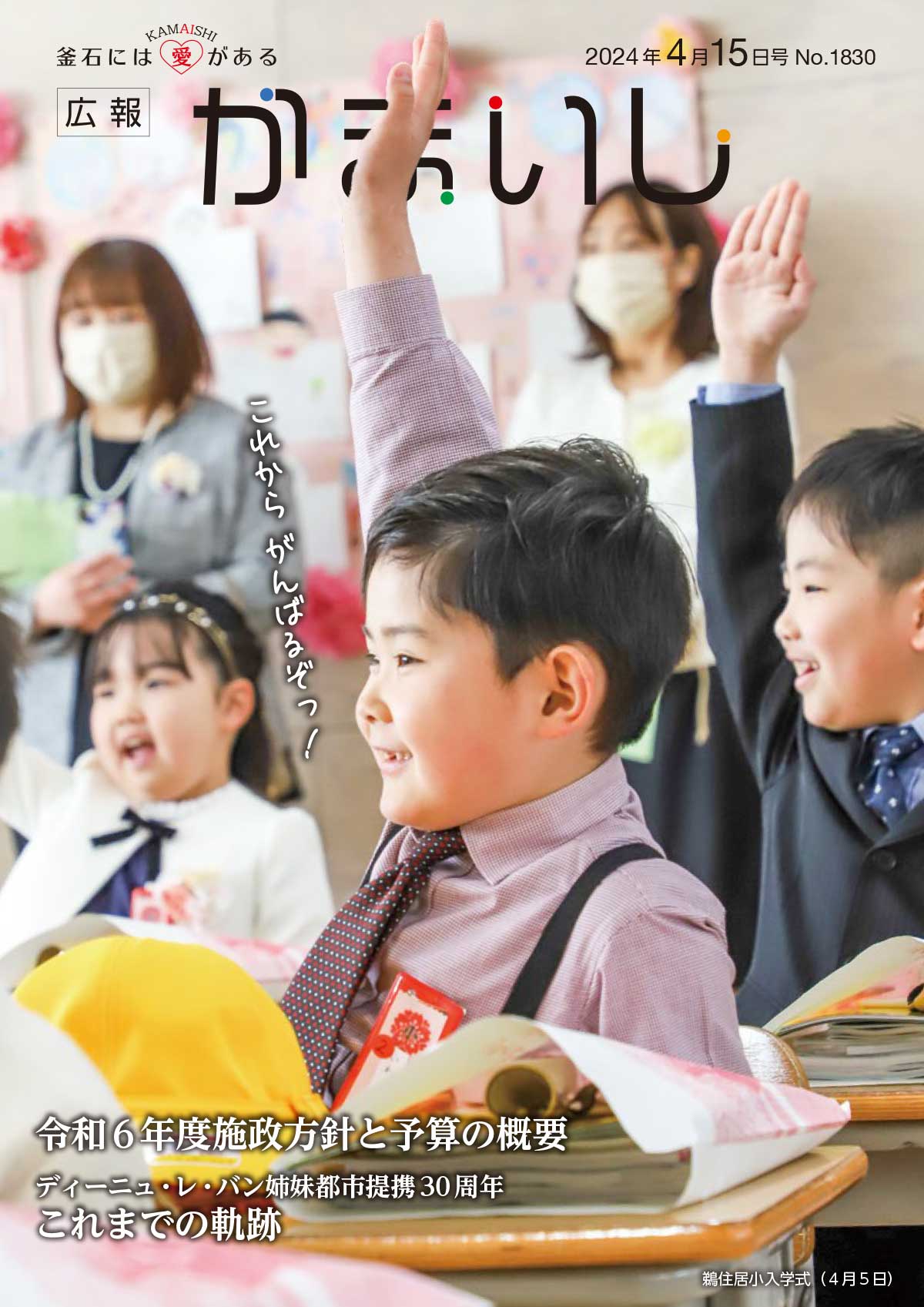ゴールデンウイークを彩った釜石の海の魅力を発信する催し
ウニむき体験に、漁船クルーズ-。海の魅力を体感してもらう催しがゴールデンウイーク(GW)期間中の3日間、釜石市魚河岸の魚河岸テラスを拠点に展開された。施設を管理運営する観光地域づくり法人かまいしDMC(河東英宜代表取締役)が企画。この時期ならではの食や景色を味わい、もてなす漁師らとの触れ合いを楽しんだ人たちは釜石が発信する“みりょく”に満足げだった。
ウニむき体験は3、4日に実施。畜養事業に取り組む唐丹町漁協の協力を得て、キタムラサキウニ約150キロを用意した。挑戦者たちはキッチンバサミやピンセットを使って「口開け」。殻を割って海藻などを丁寧に取り除き、スプーンで身をすくって味わった。「甘い」「濃厚」「うまい」「いつも食べているのと違う」と感想はさまざま。神奈川県大和市の小学生松村海里君(11)は「触ったのも、むきたてを食べるのも初めて。おいしいし、米が欲しくなる」と頬を緩めた。

魚河岸テラスで開かれたウニむき体験を楽しむ家族連れ=3日

黙々と。子どもも大人も真剣な表情で作業に集中した
提供された畜養ウニは、海藻が少なくなる「磯やけ」やエサの減少によるやせたウニの増加といった漁業が直面する厳しさを改善させる手段として漁業者が育てた。その取り組みを岩手大学釜石キャンパス特任専門職員の齋藤孝信さん(62)が解説。エサとして漁協の加工場で出る塩蔵ワカメの端材などを与えていて、「価値のないものや捨てるもの、そんなマイナスを組み合わせてプラスに持っていきたいという漁業者の思いが込もっている」と伝えた。

齋藤孝信さんの手ほどきを受け、ウニむき体験を楽しむ親子

「口、とった」「うまーい」。いい表情を見せる子どもたち
愛知県名古屋市の井上峰行さん(41)、由里恵さん(43)夫妻は、東日本大震災のことを考える“三陸めぐり旅”の途中で立ち寄った。「海と断絶された高い壁のような防潮堤」が印象的だったというが、海という資源に対する地域の思いやSDGsという視点に触れる機会にもなった。ウニむき作業は浜の人たちの手にかかると3分ほどというが、2人が要した時間は約20分。細やかで手間のかかる作業を日々繰り返している漁業者の仕事ぶりに思いを巡らせながら、そのひとすくいの「味力(みりょく)」をかみしめた。

絶好のクルーズ日和。水面や景色の近さを楽しむのは漁船ならでは=5日
釜石湾内の漁船クルーズは5日限定で「定期便」を運航した。魚河岸テラス前を発着に、波が比較的穏やかな湾口防波堤の内側を巡る約1時間の船旅。通常は事前予約(乗船希望日の2日前まで)が必要だが、この日は出港時間を決めて6便航行した。
乗客は涼しげな潮風を受けながら、釜石港周辺の産業中心地や尾崎半島にかけての大自然を堪能。海上から見上げるガントリークレーンの迫力、正面から望む釜石大観音など、普段見られない視点からの光景に「観力(みりょく)」を感じた様子だった。

産業中心地の風景を間近で眺め、普段とは違った角度に面白さを感じたり
このクルーズの魅力は、漁師の船長がガイドを務めていること。第1便は釜石湾漁協に所属する平田の佐々木剛さん(71)が乗客をもてなした。漁船内の魚槽や魚群を探知する機器などを見せながら、「今、この辺にはサバの群れがいるってことです」などと解説。カキやサクラマスなど湾内で行われている養殖、2011年の東日本大震災や2017年の林野火災の被害と再生の取り組みにも触れた。

ガイドとして乗客をもてなす漁師の佐々木剛さん(写真中央)

釜石湾内で行われているサーモン養殖のいけすに興味津々
福島県須賀川市から訪れた阿部仁一さん(47)、志帆さん(46)夫妻は「水面が近く、風も感じられてリフレッシュした。台本通りではないガイドが素朴で味があったし、いけすを見られたのもよかった」と笑顔を重ねた。鵜住居町の根浜海岸ではオートキャンプを満喫。宿泊サイトは満杯だったものの静かで快適な時間を過ごしたといい、釜石の海レジャーに好感触を残した。
GW後半は天候に恵まれ、釜石港の岸壁では釣り客も多かった。水中に糸をたらし、寄ってきた小魚を網ですくい取る子ども、サバなどをバケツいっぱいに釣り上げた人もいた。「釣りをやってみたい」という子どもらの希望を受けてやってきた盛岡市の40代男性は「道路がつながって三陸が近くなった。年に数回、平田で釣りをしていて、釜石の海にいいイメージを持っている。子どもたちも楽しんでいる」と目を細めた。

魚市場近くの岸壁では釣りを楽しむ人の姿も多く見られた=5日

「とったー」。魚を釣り上げてピースサインをつくる子ども
ウニむき体験は、畜養しても活用方法や販路の確保を模索していた漁協を後押ししようと、昨年のGWに続いて2回目の実施。漁船クルーズは海を生かした持続可能な観光振興を目指し取り組む。どちらも反響は上々で、イベントを担当するかまいしDMCの佐々木和江さん(46)は「魚食、遊び、人との関わりなど多様な要素を取り入れた企画で、臨海部ならではの魅力を発信していきたい」と先を見据えた。