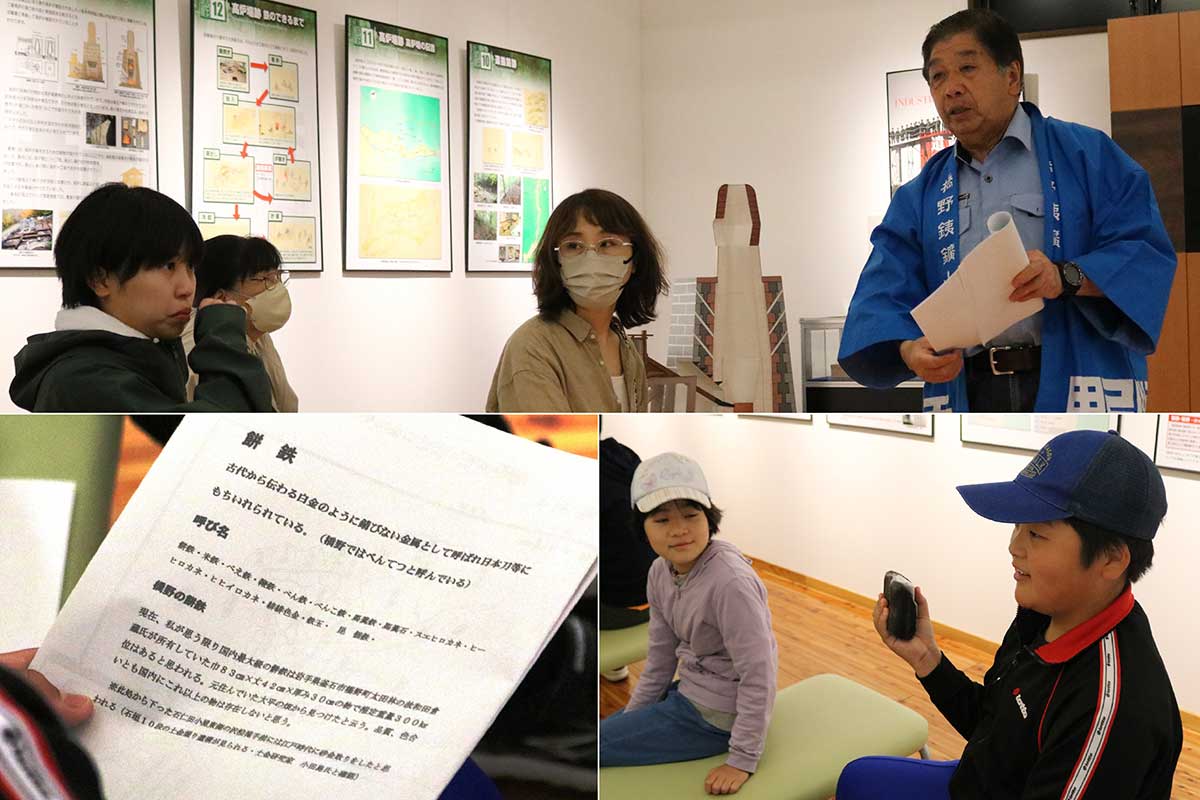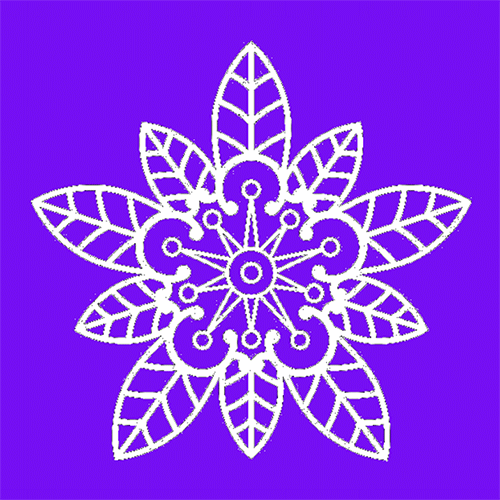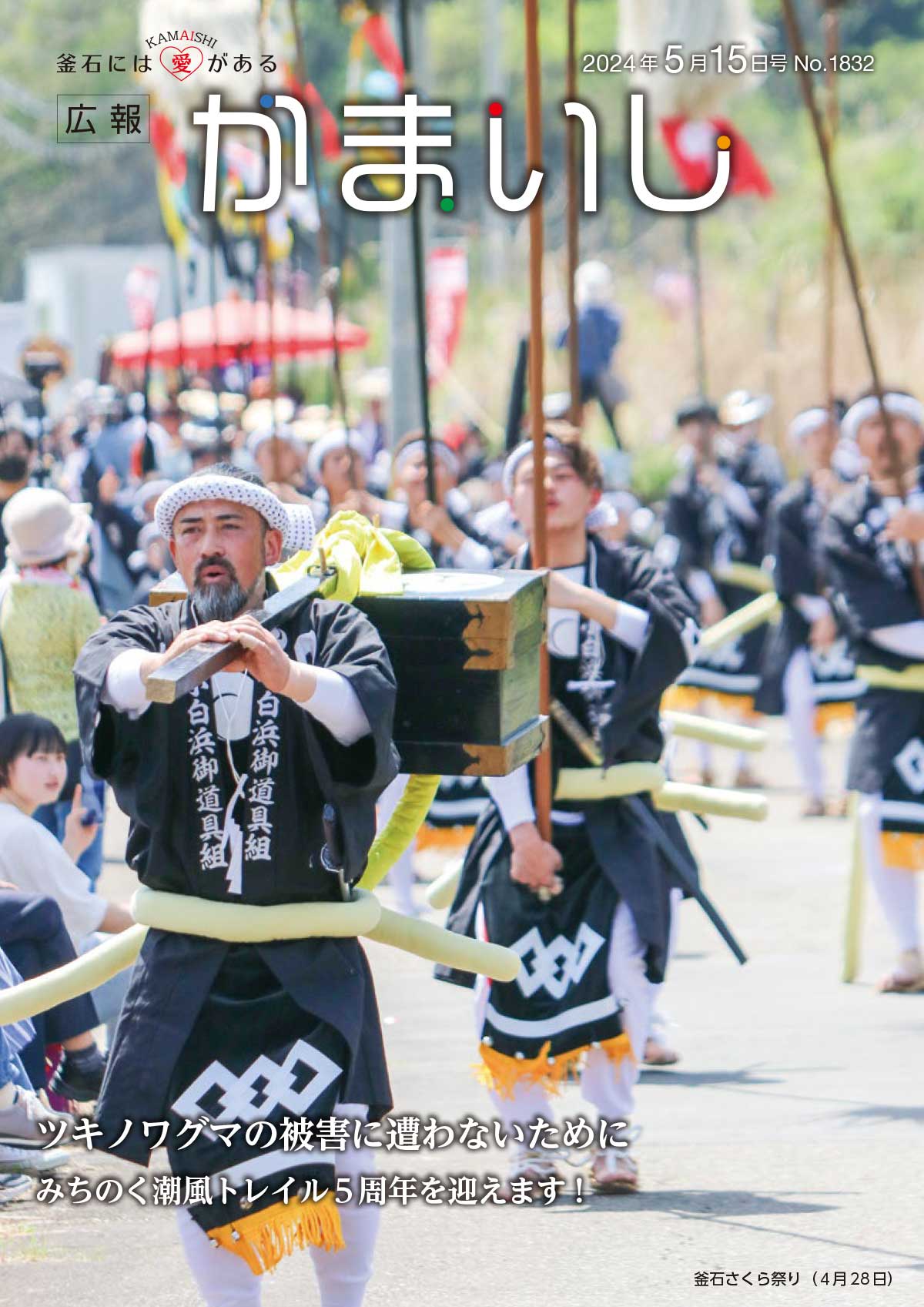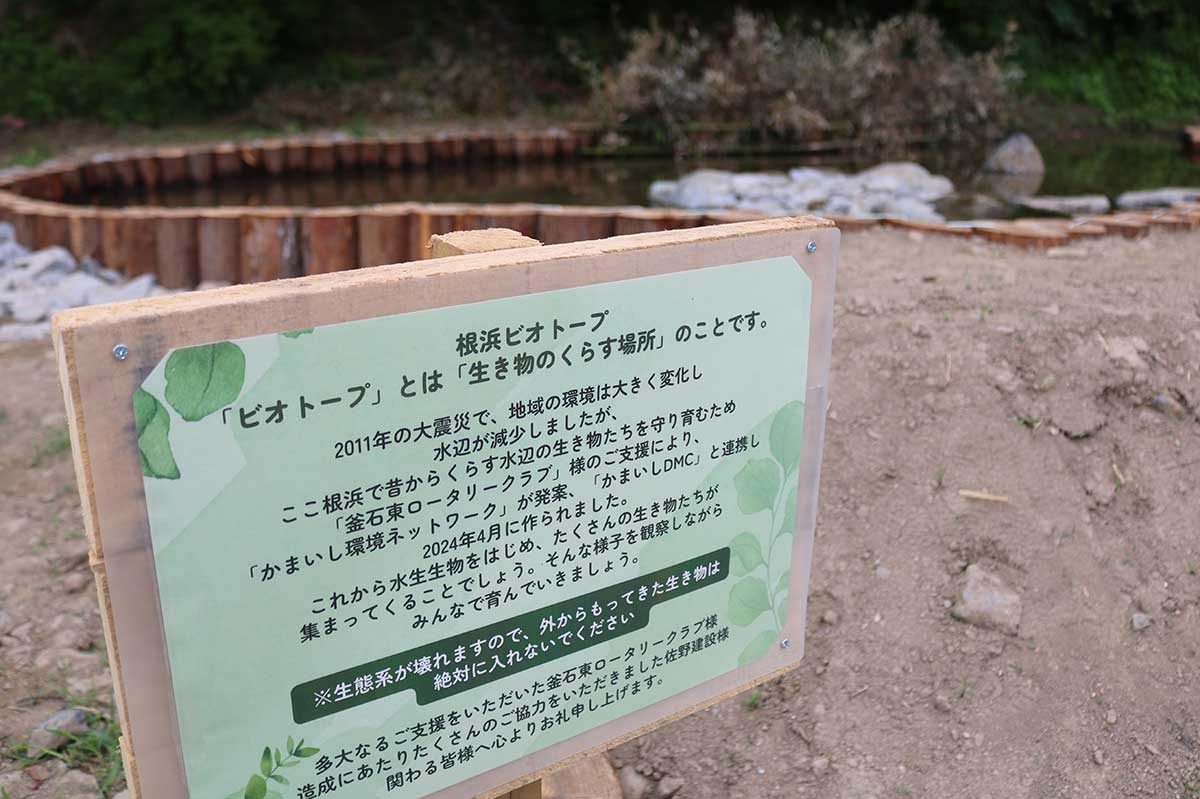絵本作家サトシンさんのライブを楽しんだかまいしこども園児と保護者
釜石市天神町のかまいしこども園(藤原けいと園長、園児80人)は本年度、開設から10年目を迎える。5月29日、記念イベントとして、人気絵本作家のサトシン(本名:佐藤伸)さん(61)を招いての読み聞かせライブが園内で行われた。作品を歌で伝えたり、物語を作る面白さを園児に体験させたりと、絵本のさまざまな楽しみ方を提案。この日は保育参観日で、園児と保護者がかけがえのない時間を過ごした。
サトシンさんは新潟市出身、在住。広告制作プロダクション勤務、専業主夫、フリーのコピーライターを経て40代前半から絵本作家に。これまでに50作品以上を手掛ける。2010年に出版した「うんこ!」は数々の賞を受賞。大きな反響を呼んだ。テレビやラジオ番組、全国を回ってのライブなどで、絵本の楽しさや大切さを伝えている。
今回は釜石では初のライブ。自身の代表作をさまざまな手法で聞かせた。あいさつの大事さを表現した作品「こんにちは、ばいばい」は同園の教諭と掛け合い。登場する動物の鳴き声で楽しませた。いろいろな曲調で物語を歌で伝える活動もしているサトシンさんは、「とこやにいったライオン」などを歌って聞かせた。虫好きが高じて作った「はやくおおきくなりたいな」、子どもたちへのメッセージが込められた「おとなからきみへ」も披露した。

トレードマークの王冠帽子とマント姿で、園の先生と絵本を読み聞かせるサトシンさん(写真右)

日本昔ばなしや自身の作品を歌で披露。「ソング絵本」としてCDも発売している

スクリーンにページを写しながら読み聞かせ(写真上)。物語の世界に引き込まれる親子(同下)
サトシンさんを一躍有名にした「うんこ!」は楽しい絵本の代表格。近寄ってきたネズミやヘビ、ウサギに「くっさーい」と敬遠されながらも、仲間を探す旅に出るうんこが主人公。最後は農家さんに出会い、肥やしになっておいしい野菜を育てるのに役立つ。悔しがる時に発する「くっそー」、考える時の「うん、こーしよう」など駄じゃれを交えたセリフもあり、会場の親子は一緒に声を出して楽しんだ。

発売から10年で50万部売れた人気作品「うんこ!」。掛け声で楽しめるのはライブならでは

サトシンさんのエネルギッシュなライブに拍手と笑顔
サトシンさんが考案した「おてて絵本」という遊びも紹介。手のひらを絵本に見立てて即興で物語をつくるもので、園児も体験した。この日は好きな動物から話を展開。サトシンさんが園児に質問しながら会話するうちに、自然と1つの“お話”が出来上がった。「子どもは大人に話を聞いてもらいたい生き物。親がその気持ちを受け取り、やり取りする中でコミュニケーションが生まれ、子どもは満足する。作っている話の中で日常では見えなかった子どもの気持ちが見えてくることもある」とサトシンさん。絵本を読んだり物語を考えたりすることで「想像力が育まれる」とも。

「おてて絵本」で“物語作り”体験。希望した園児と藤原園長が挑戦した

言葉遊びの面白さ、何げないやり取りの中に込められた自分らしく生きるためのヒント…。子どもだけでなく大人にも響く作品を存分に楽しんだ親子は、たくさんの笑顔を広げた。サトシンさんの作品に初めて触れた久保梓ちゃん(4)は「楽しかった!絵本大好き」とにっこり。母静樺さん(27)は「子ども向けの絵本だけど、深いメッセージが込められている。サトシンさんご自身の言葉で聞けて良かった」と大満足。夜、寝る前の読み聞かせを習慣にしていて、「絵本は子どもとの貴重なコミュニケーション。忙しい中でもその時間は大事にしている。今日聞いたことも今後に生かしたい」と話した。
ライブ後は本の販売やサイン会、記念撮影も行われた。サトシンさんは「自分の人生を自分のカラーで切り開いていって」などと声を掛けながら、親子と親しく会話。思い出に残るひとときを提供した。この日は、同園が開設する子育て支援センターバンビルームの記念イベントとしても同ライブが行われ、大町の市民ホールTETTOで市内の親子連れや大槌町のこども園の園児らが楽しんだ。

会場では絵本の販売も。サトシンさんからサインももらった

一緒に写真も撮って思い出づくり。かけがえのない時間となった
両ライブでサトシンさんは「絵本を読む時間はほんの3~4分。忙しい中でもできる。子どもにとって一番うれしいのは、大好きなお父さん、お母さんが寄り添って言葉や愛情をかけてくれること。家庭でもぜひ、親子で絵本を楽しんでほしい」と呼び掛けた。
かまいしこども園は2015年に開園した。前身の釜石保育園(大渡町)が11年の東日本大震災津波で被災。甲子町の旧釜石南幼稚園舎を借りて保育を続けた後、幼保連携型認定こども園に衣替えし、現在地で新たな歴史を刻む。藤原園長は「多くの人の助けがあってここまでこられた。応援してくれる方、頑張ってやってきてくれた職員がいるからこその10年。本当に感謝」と目を潤ませる。7月には10年の歩みを振り返るイベントも開催予定。19日は同園の施設見学、20日は市民ホールTETTOで夏まつりを企画する。