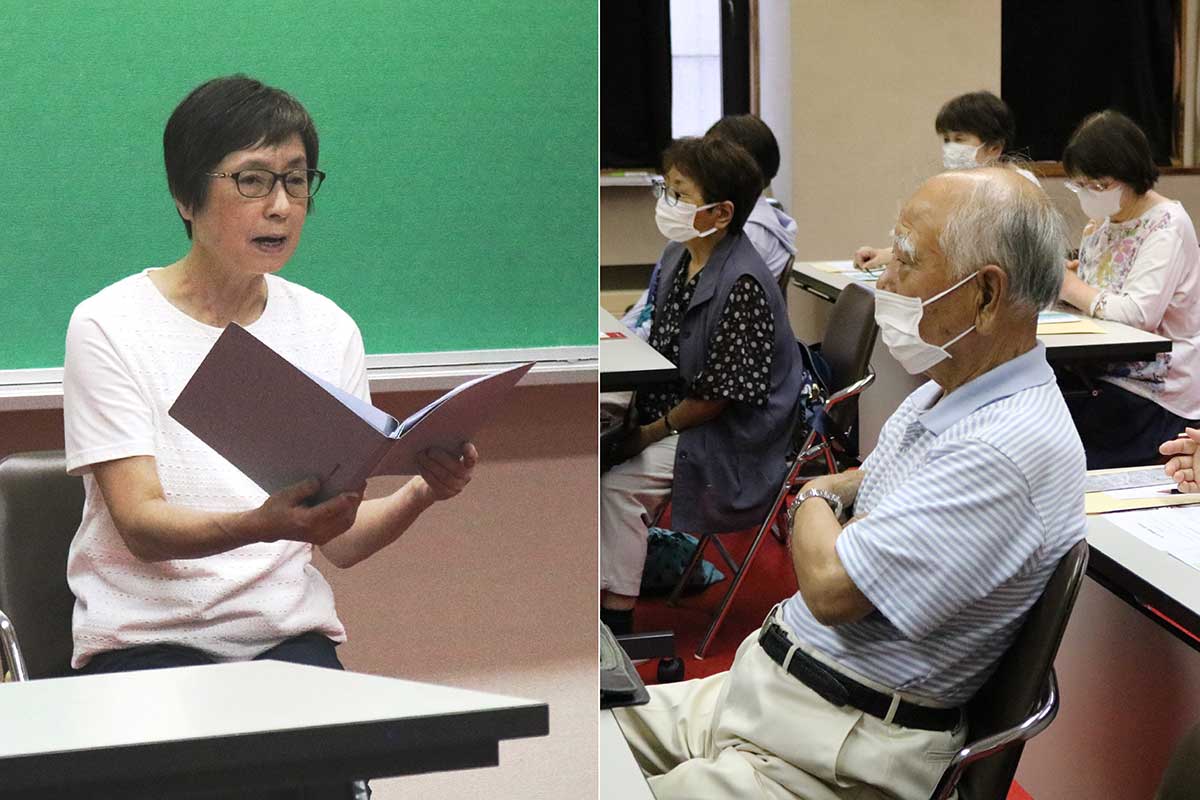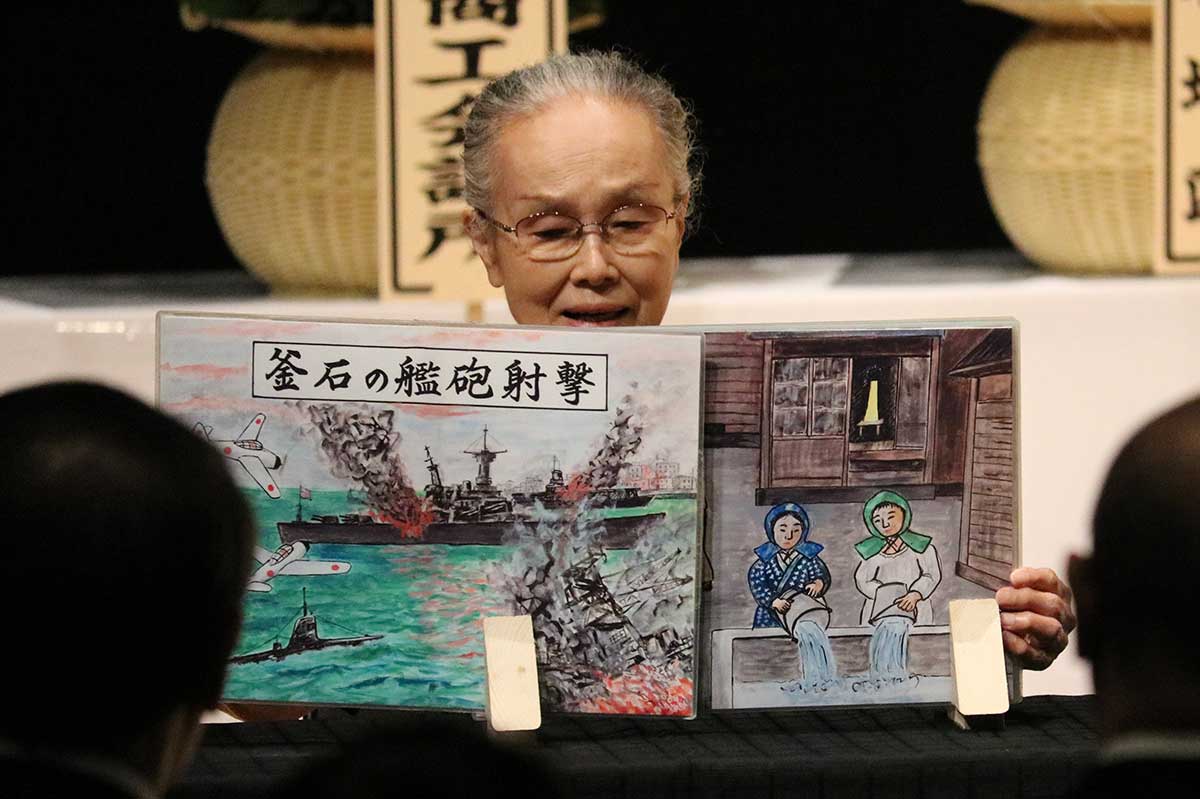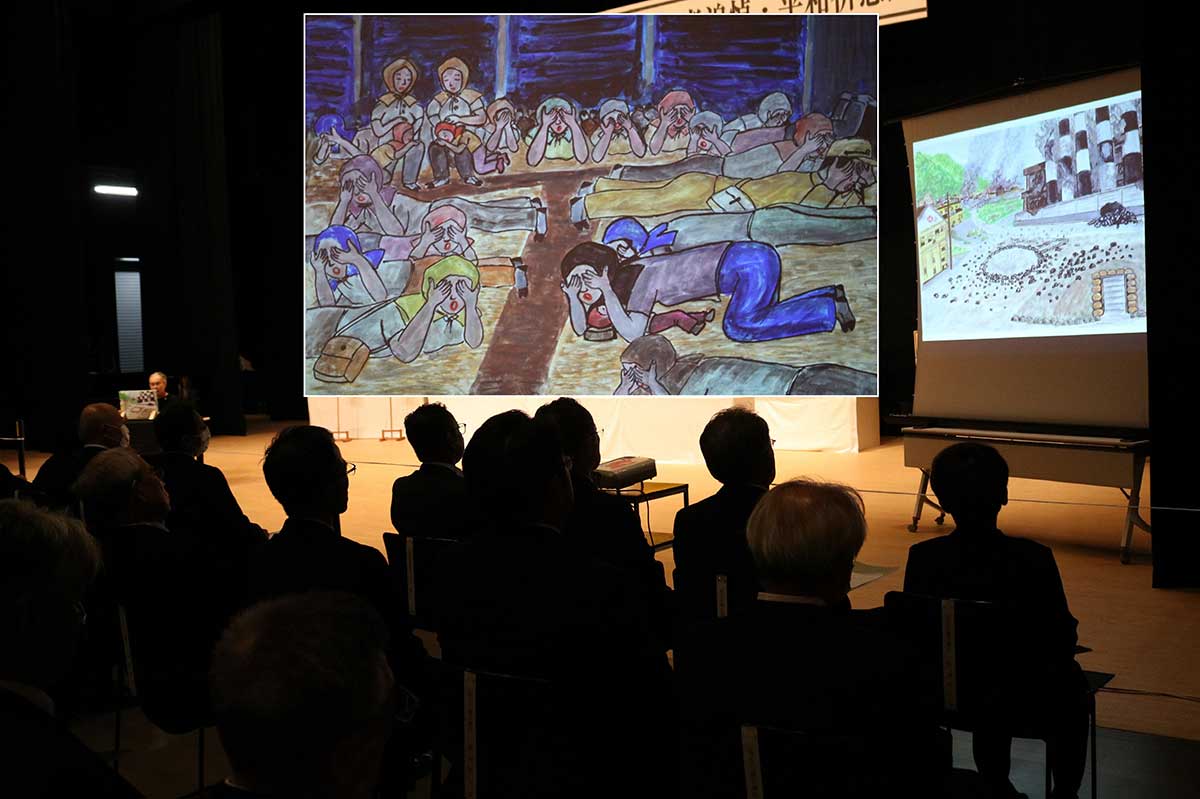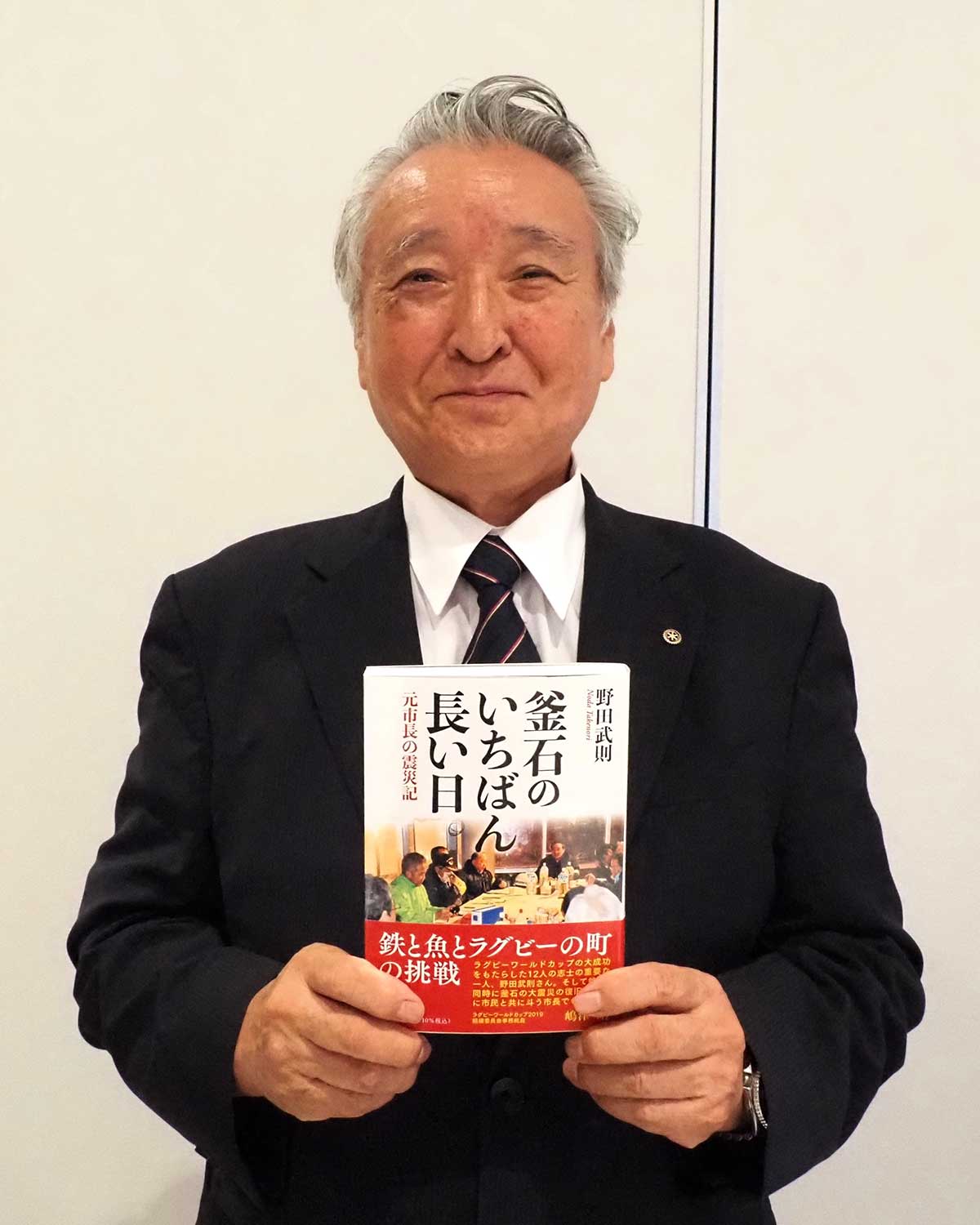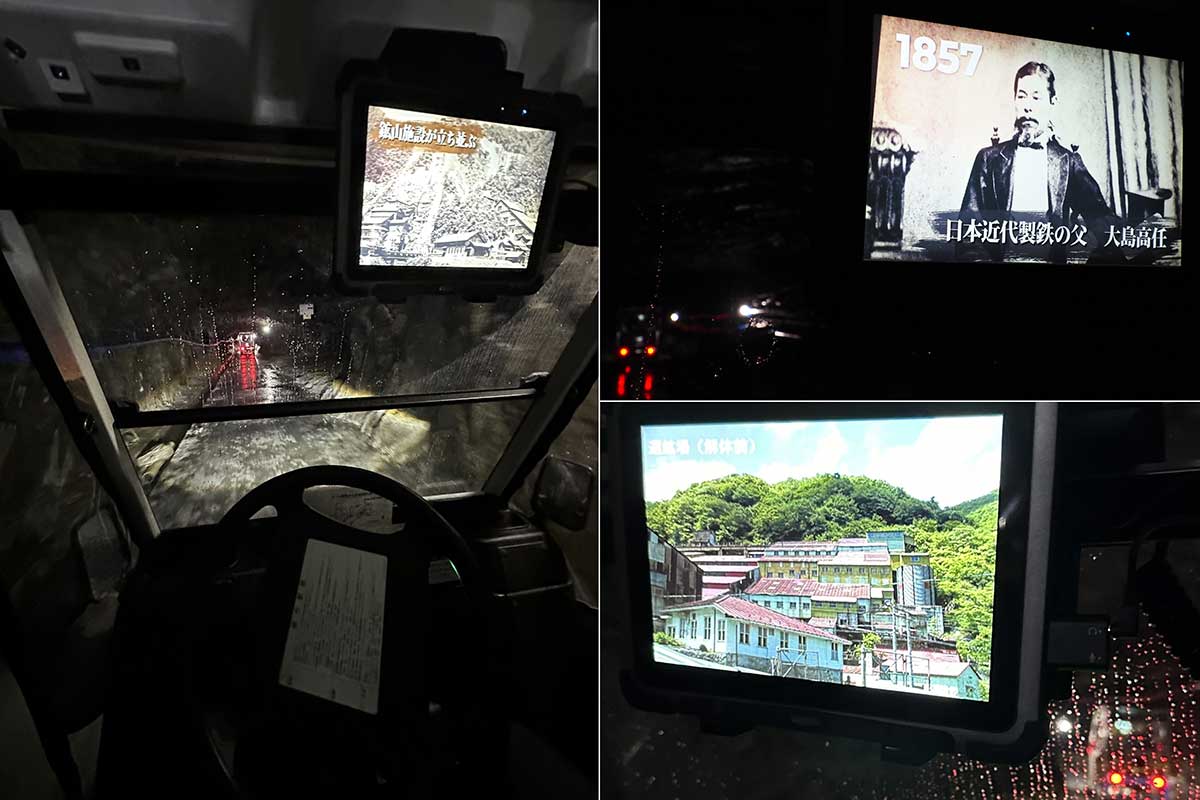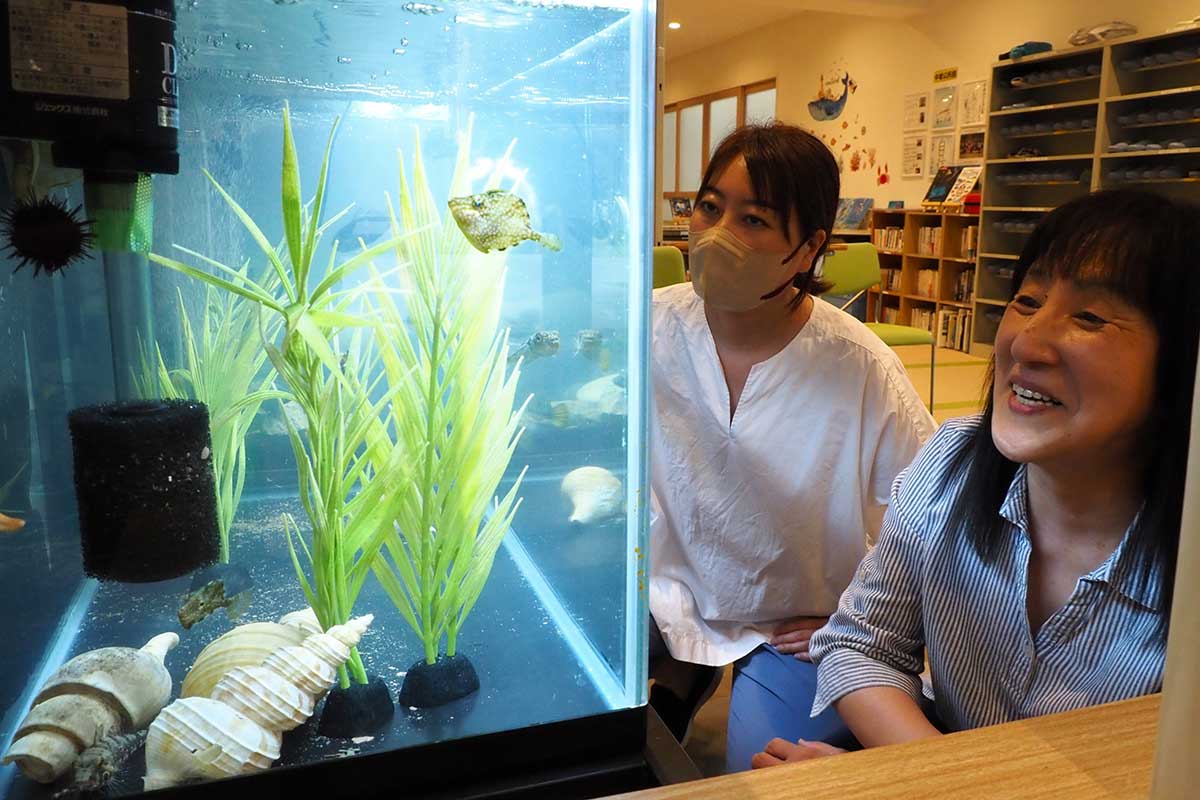釜石産鶏肉を使った給食を味わう鵜住居小の児童ら
釜石で鶏肉を作っていることを知ってほしい―。釜石市栗林町に養鶏場がある鶏肉生産加工販売業オヤマ(本社・一関市、小山征男代表取締役)は、学校給食用食材として釜石産のいわいどりを市に提供した。さっそく22日に給食のメニューに登場。これに合わせて、同社の小山達也常務取締役(48)らが鵜住居小(佐藤一成校長、児童143人)を訪れ、「おいしいー」と頬張る子どもたちの様子をうれしそうに見つめた。
栗林の養鶏場は4月から本格的に生産、出荷を始めた。今回提供したのは鶏もも肉で、小学校用が1205個(1個40グラム)、中学校用は720個(同60グラム)。特別支援学校を含む市内13校で振る舞われた。

お楽しみの給食の時間。トレーを持つワクワク顔の列が続く

料理を盛りつけたり配膳したり役割分担しながら食事の準備
この日の献立は「いわいどりのマーマレード焼き」で、市学校給食センター(山根美保子所長)が調理。同校1年生(23人)の教室では、小山常務が「鶏肉は良質な筋肉、体をつくるもの。すてきな味付けがされた鶏肉をたくさん食べて大きくなってほしい」と自慢の食材をアピールした。
児童は大きく口を開いて鶏肉を頬張ると、「うまい」とひと言。中には、パンに挟んで味わったりする子もいて、思い思いの食べ方で地元産食材のよさをかみしめた。菊池咲希さんは「優しい味がする」とにっこり。鈴木綾誠さんは「食感が柔らかい。めっちゃ、おいしい。もっと食べたい」と喜んだ。

いわいどりのマーマレード焼きにかぶりつく児童

パクっと頬張ったり、パンで挟んだり、食べ方はいろいろ
小山常務は「みんなの笑顔を持ち帰り、生産している大人たちに伝える。その循環関係を大切にしながら、いい鶏を提供し続けるパワーにしたい。地元で良質な鶏肉を作っていることを知ってもらい、いわいどりをソウルフードしてもらえたら。将来、一緒に生産してもらえたら幸せ」と期待を込めた。

小山達也常務らが「おいしい鶏肉をもりもり食べて」とPR

「おいしー。ありがとう」。児童は笑顔を添えて感謝も伝えた
この日のメニューは他にも釜石産がお目見え。三陸産ワカメを使ったサラダに加わったキュウリ、スープには特産品化を目指すトマト「すずこま」やタマネギが使われた。