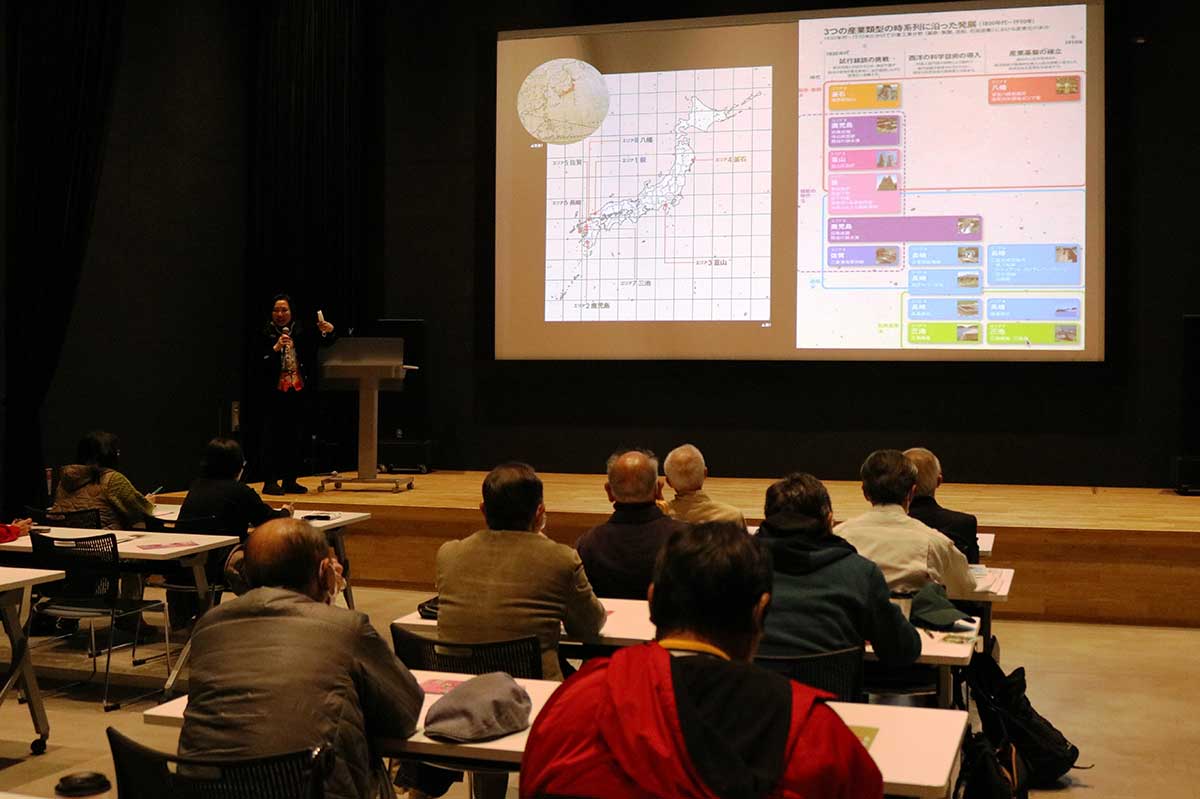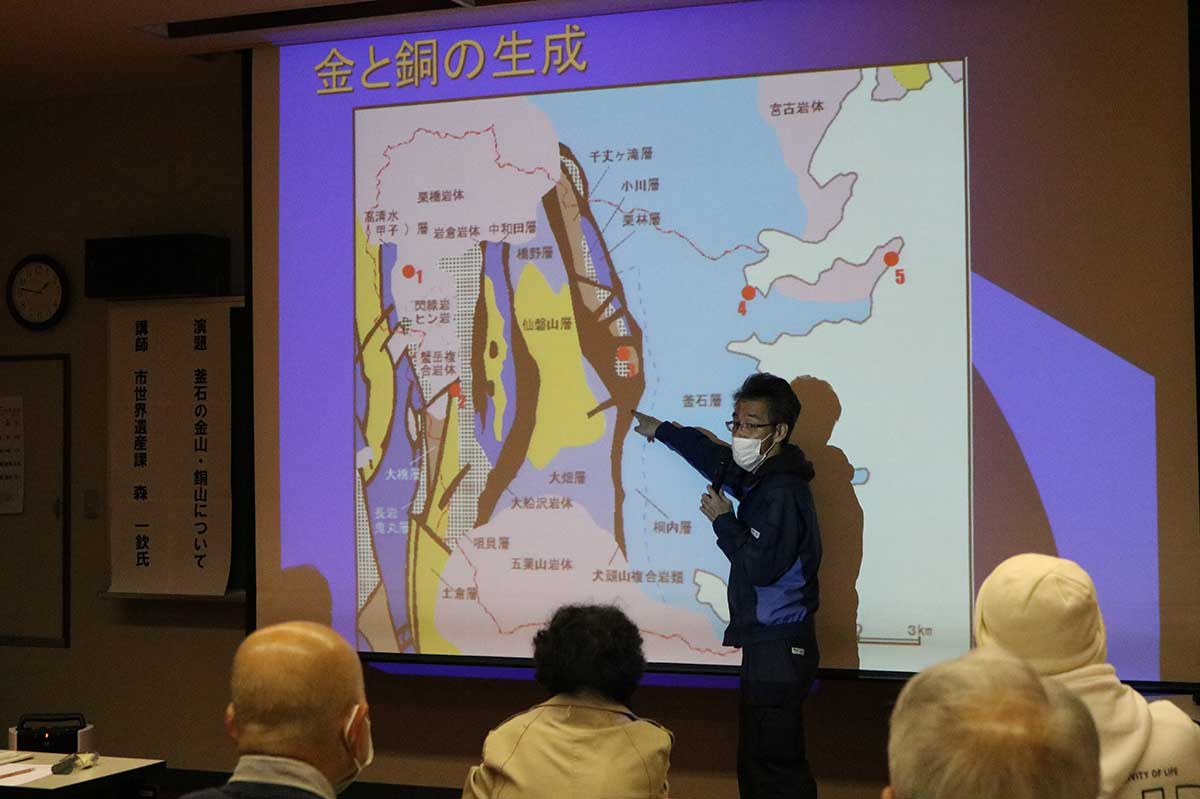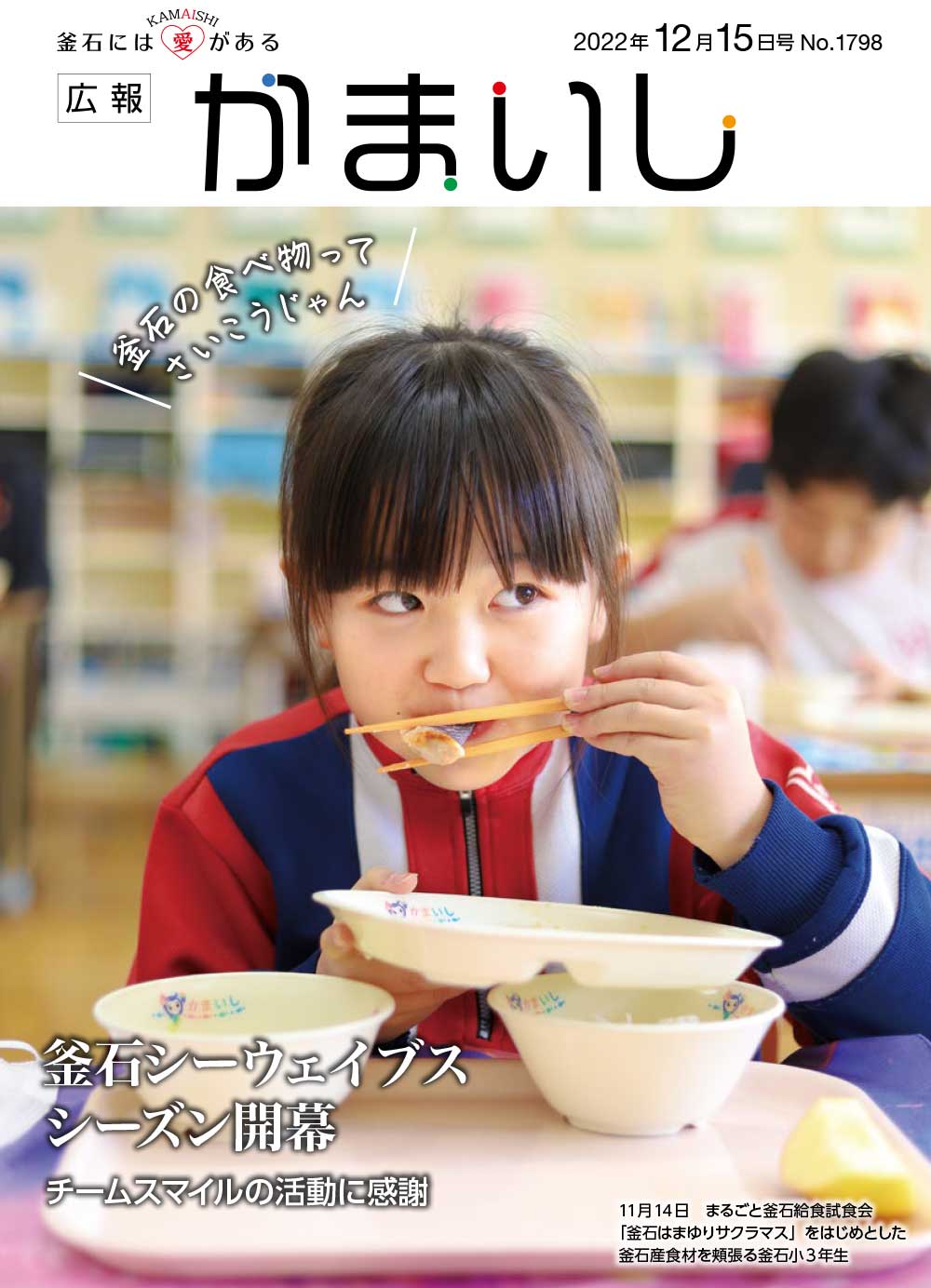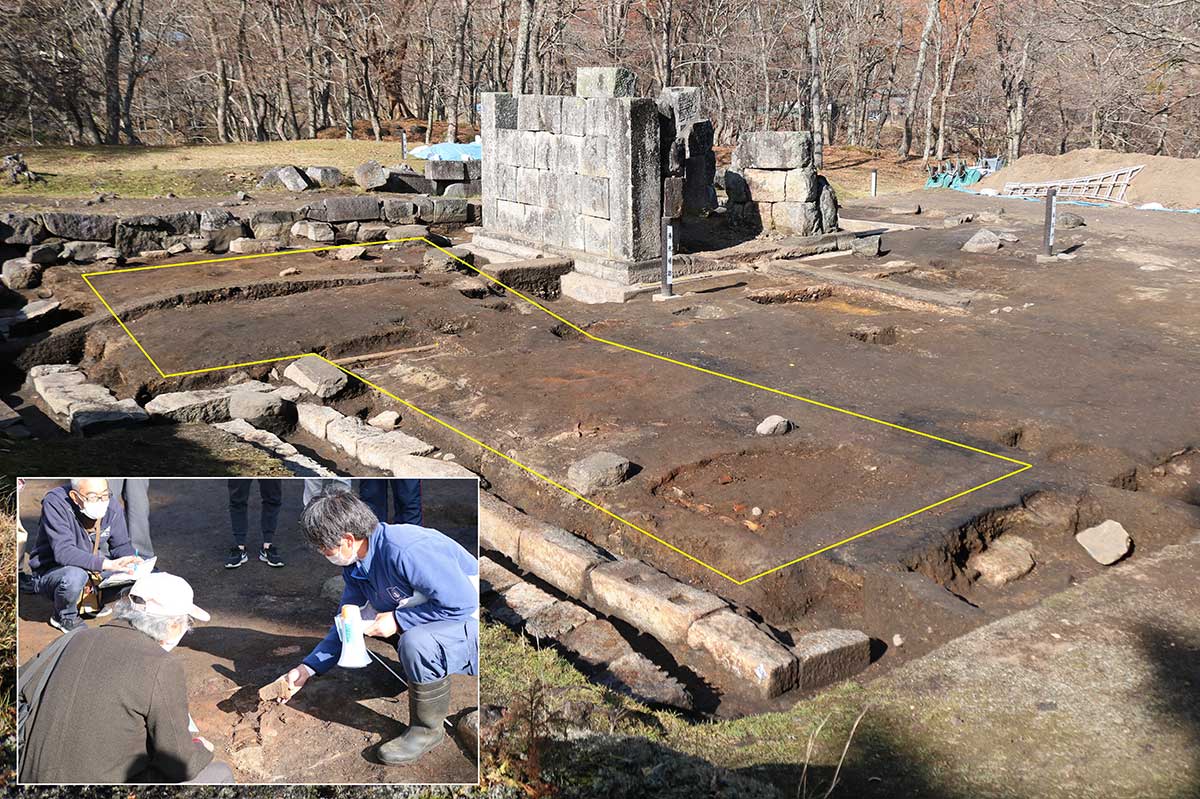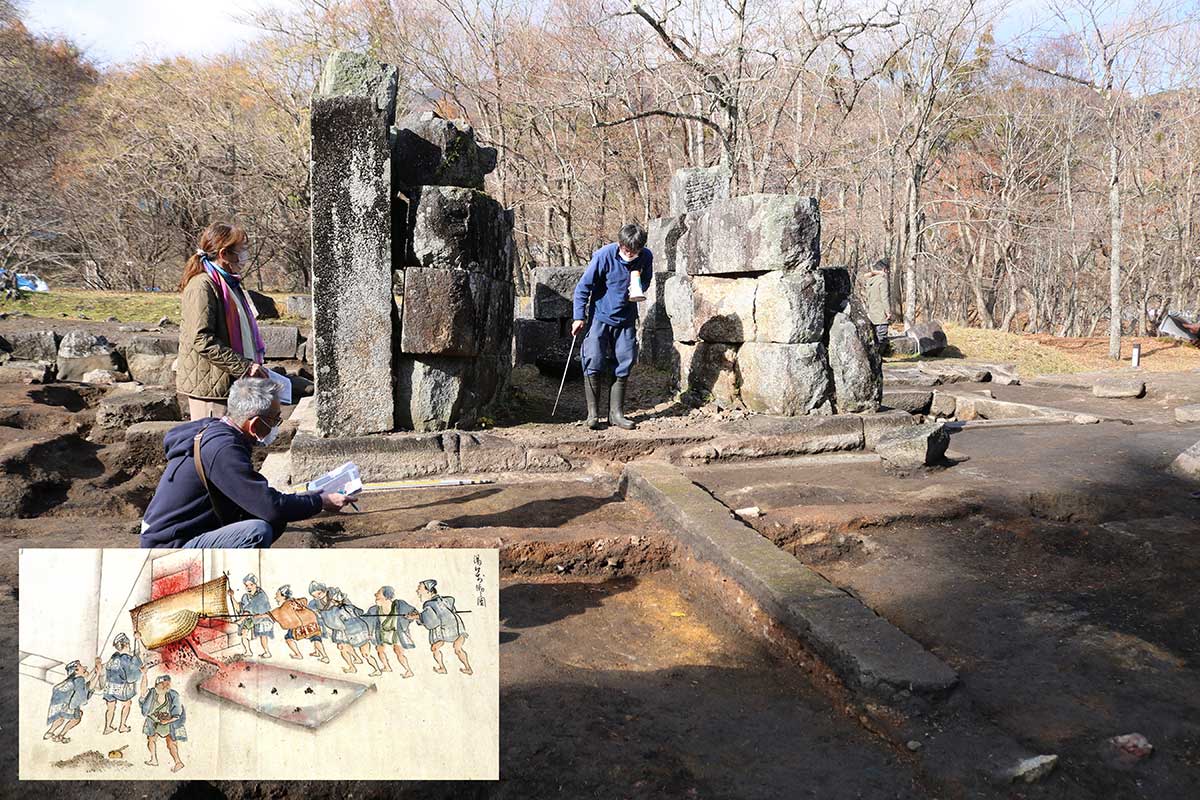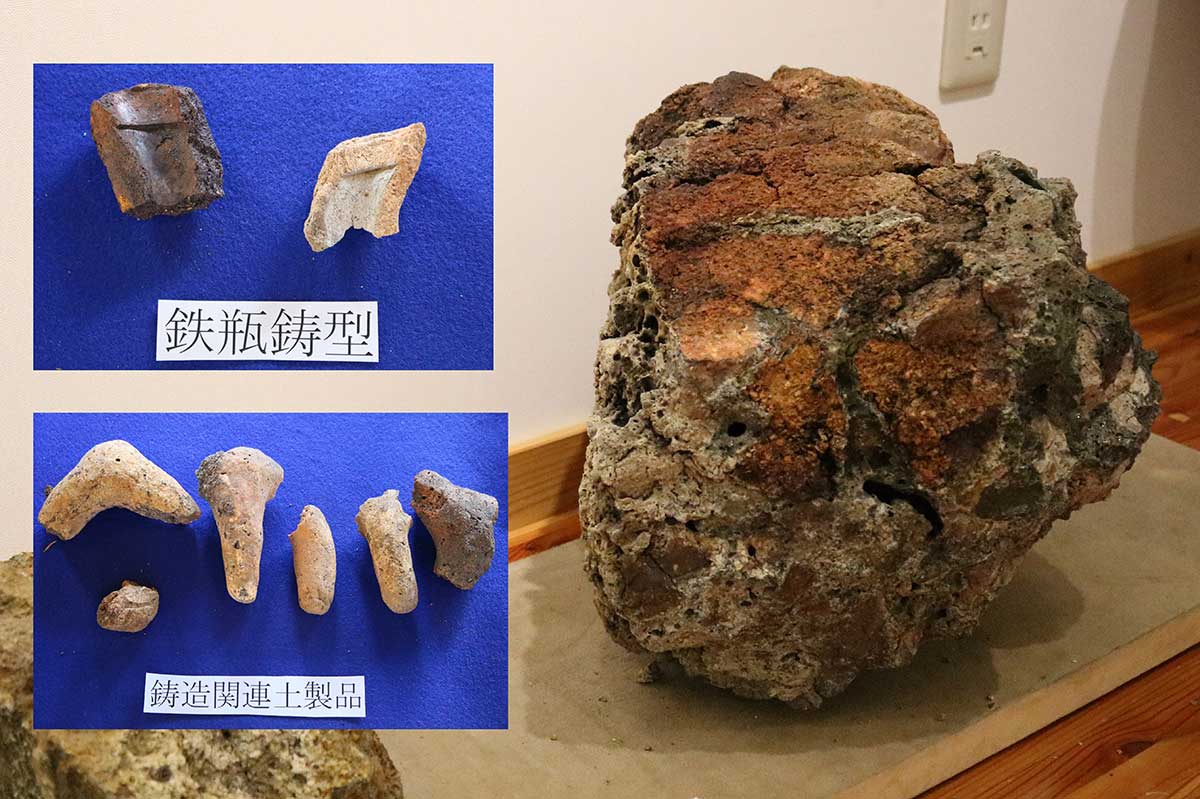譲渡会で保護猫の様子を見つめる親子
釜石保健所で保護した猫たちの譲渡会が17日、釜石市大町の市民ホールTETTOで開かれた。生後3カ月の子猫から成猫まで12匹を集め、参加者が自由に見学。会場では譲渡前講習会も行われ、受講した1組が「試し飼い」を決めた。
譲渡会は保護猫の譲渡促進、動物愛護思想や適切な飼育方法の普及啓発を図るのが狙い。県沿岸広域振興局保健福祉環境部が主催し、2022年度地域経営推進費を活用した「人と動物のふれあい活動事業」として実施。動物愛護団体「人と動物の絆momo太郎」が共催した。

保護猫と新たな飼い主の出会いの場となる譲渡会
保健所管理の保護猫は約20匹。同団体が運営する譲渡型保護猫ハウス「保護猫アンドゥ」(大渡町)が一時預かりしている。譲渡会では人慣れはしているが、「ちょっぴり臆病」「よく食べ、よく寝る」「元気いっぱい」「怖がり屋さん」といった個性派ぞろいの猫たちを紹介。保護猫に興味がある人らが足を運び、猫の様子を見て回った。
保護猫は病気の検査やワクチン接種、成猫は避妊・去勢手術を受けさせている。試し飼いも可能で、1週間ほど一緒に暮らし、問題がなければ正式に譲渡されるという。

ゲージの中でくつろぐ猫に触れ、様子を見る来場者
今回試し飼いをする人は、すでに猫を飼っていて「猫同士の相性を確認してから決める」という。甲子町の40代男性は「猫と暮らしたい」と一軒家に移ったばかり。初めて猫を飼うため講習を受けて適正な飼育に理解を深めた様子で、「家族と相談する。どの猫もかわいいから迷う。時期にこだわらず、相性、出会いを大事にしたい」と真剣な表情だった。

動物を飼う前の心構えや準備などを伝える講習
同保健所上席獣医師の奥村亮子さんによると、民間団体との連携は「常に誰かいて世話をしてもらうことで猫の人慣れが進み、譲渡がスムーズになる」のに加え、飼育の仕方など助言を受けることができ、譲渡後の支援が可能にもなる。新型コロナウイルス禍で譲渡会の実施を見送る時期もあったが、動物との暮らしに関心のある人らがアンドゥを訪ねていて、譲渡の機会は減ってはいない。

ゲージに入り、引き取り手を待つ保護猫たち
今年、市内で約50匹の猫の多頭飼育について情報提供があり、飼い主が高齢で健全に飼育することが難しいことから同保健所で子猫を保護。一時保護できる頭数には限界があり、ミニ譲渡会を開くなどの対応が必要となった。野良猫への餌やりといった苦情も寄せられており、奥村さんは「軽い気持ちで動物を飼い始めたり、餌をやったりする人もいて、身近に起こりうる」と指摘。県・沿岸振興局のホームページなどで普及啓発を行っているが、譲渡会は直接伝える機会になり、「飼い続けてもらうため、地道に種をまいておくことが大事。じかに見て触れ、試し飼いで性格を把握し、慎重に決めてほしい」と望む。