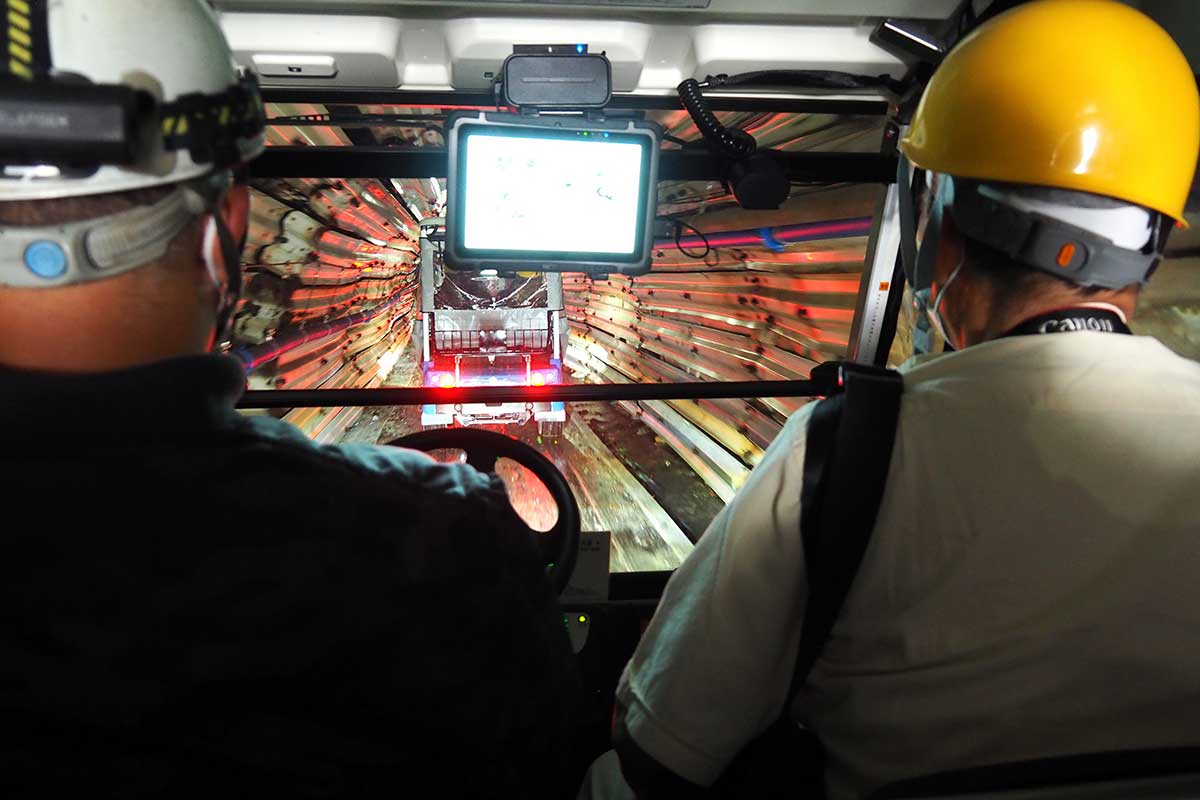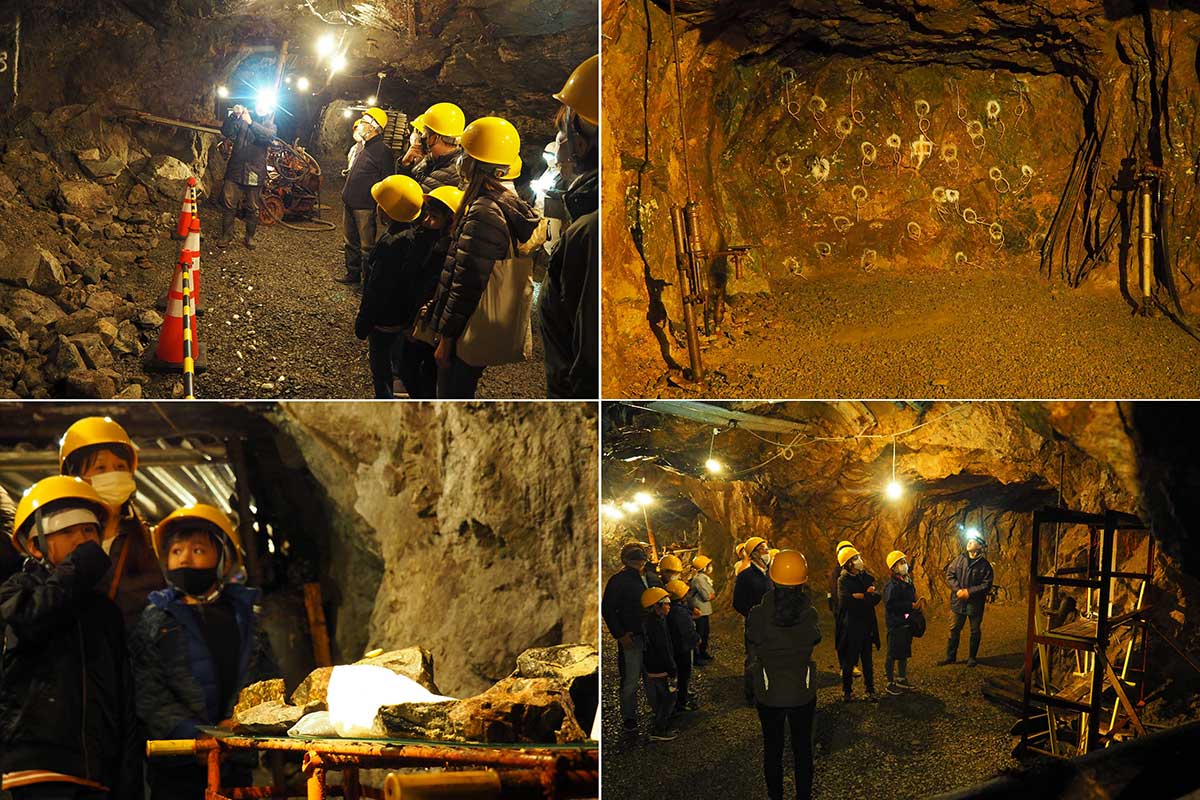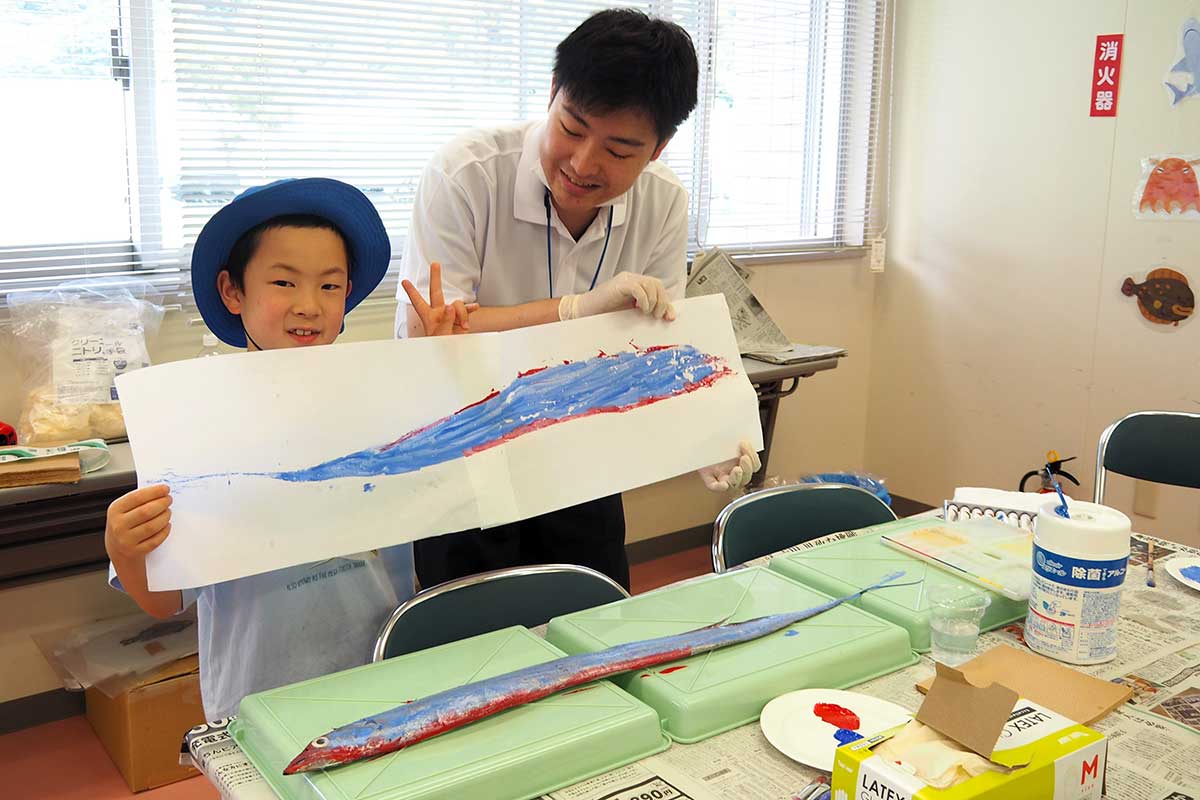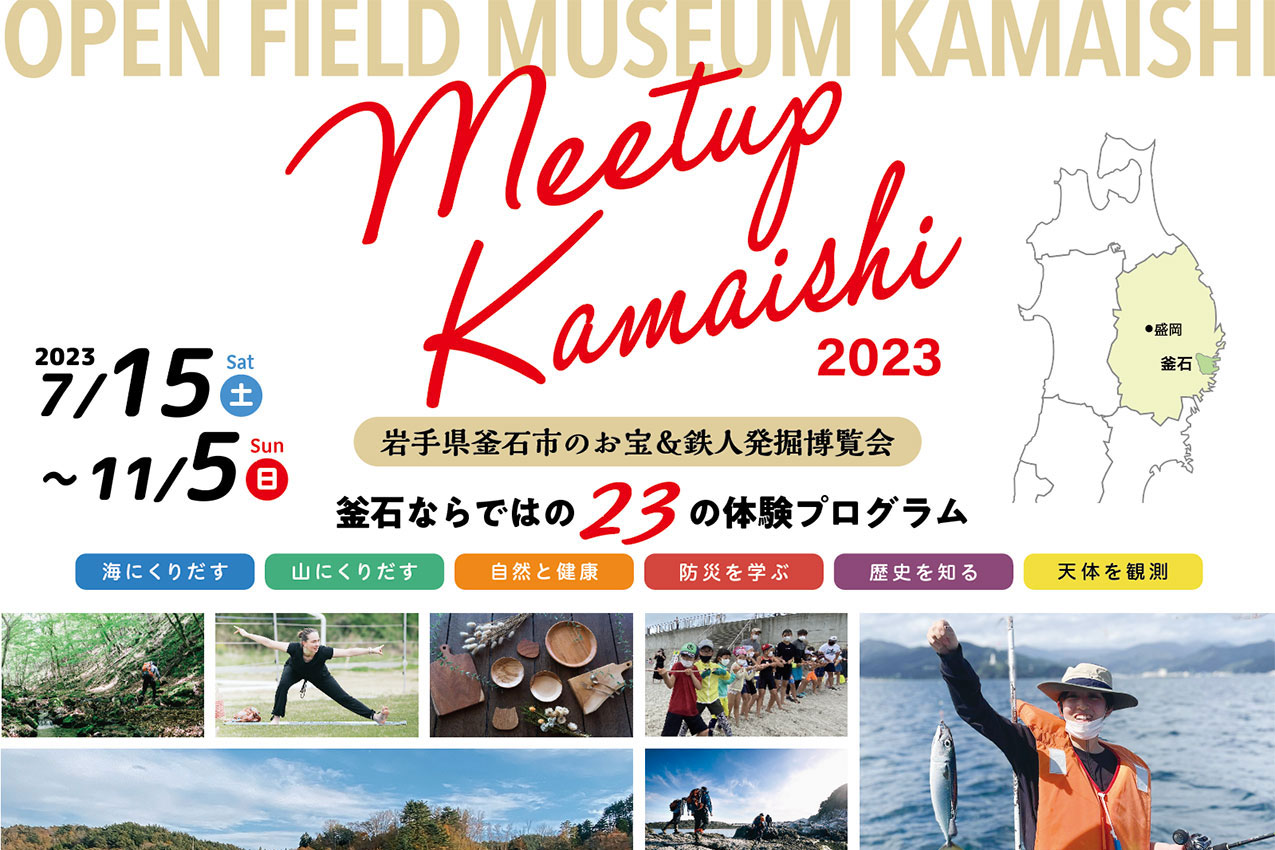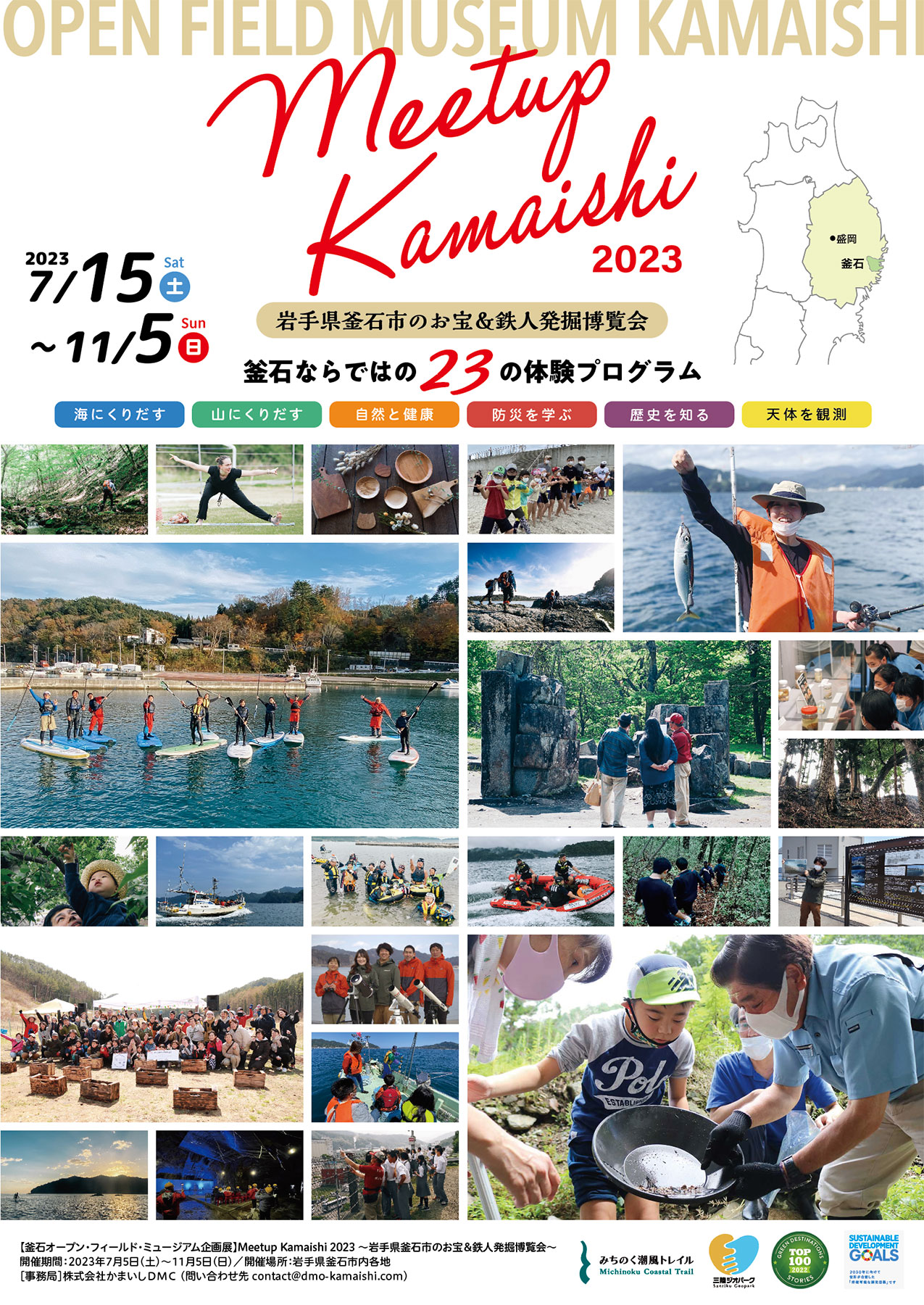「いただきまーす」。こさのこども食堂で昼食を楽しむ参加者
釜石市の小佐野地区民生委員・児童委員協議会(伊東恵子会長)は7月30日、小佐野コミュニティ会館を主会場に子ども食堂を開いた。夏休み中の子どもたちに楽しんでもらおうと初企画。小佐野小児童約50人が集い、食事だけでなく、ニュースポーツを体験したり、ボランティアとして参加した釜石高生に勉強を教えてもらったりした。市内で子ども食堂の開設は初の試みでもあり、居場所や世代間交流の機会を提供することで、地域で子どもを見守る環境づくりにつなげていく。
「こさのこども食堂、オープン!」献立はカレーライス。給食センターで腕を振るっていた元職員も加わった住民スタッフが手作りした。「夏バテをしないように」と少し多めに入れたショウガやニンニクが隠し味。夏休みで学校給食がなくなり消費が減少する牛乳、デザートにバナナも添えて、「いつもの給食」を再現。大人たちの思いを感じ取った子どもたちから「給食みたいでおいしい」と声が飛んだ。

献立はカレーライス。地域の大人との会話も食事のスパイスに

おかわりにも対応。忙しく動く地域のお母さんたちはうれしそう
交流活動は遊びと勉強の時間が用意され、高校生ボランティア約20人がサポート。同会館内の和室では宿題を持ち込んだ児童が学習を進め、分からない部分があると高校生に助言をもらったりした。隣接する小佐野小体育館ではニュースポーツ体験があり、パラスポーツのボッチャやスカットボール、輪投げで汗を流した。

宿題に取り組む小佐野小児童。釜石高生(左)らに手伝ってもらったり

体を動かした後はしっかり水分補給。高校生らが見守った
食事と遊びを目当てに参加した及川紗良さん(6年)は、期待通りでうれしそう。特に友達や高校生、地域の人たちとの交流が夏休みの思い出になったといい、「楽しかったので続けてほしい。ボランティアにも興味を持った」と刺激を受けた。
子どもたちを見守った釜高の生徒も学びを深める機会になった様子。人見知りをやわらげようと参加した芳賀結月さん(1年)は「子ども食堂は食事だけでなく、子どもたちの居場所にもなると感じた。年代別に固まっていて交流が少ない気がしたので、次回はもっと広く触れ合えるようにするといいかな。その中で、自分もコミュニケーション力を磨けたら」と期待した。

世代間交流を楽しみながら地域で子どもを見守る環境をつくる
市内陸部の小佐野地区は東日本大震災後、被災地域から人口が流入した。家族形態や生活スタイルが変わる中、地域の見守りなど子どもを取り巻く環境も変化。さらに、新型コロナウイルス禍で子ども会や地域活動が見送られたことで、子育て世帯を中心に住民同士の交流機会が減少し、関係性が希薄化していた。市によると、児童扶養手当の受給世帯数が比較的多いとのデータもあり、学校や家庭だけではない子どもの居場所づくりが必要とされていた。

「おいしい」。子どもたちの声に肩の力を緩めた伊東会長(中)
伊東会長(74)は初めての試みに不安がいっぱいだったというが、子どもたちの笑顔にホッと一息。「この触れ合いが声をかけ合える、顔見知りの関係づくりにつながると思う。これからの見守り活動に生かせる」と手応えを得る。
今回は地域住民や地元企業などが米や菓子を提供し、予算面では県や市の赤い羽根共同募金の補助金を活用できたが、継続にはより多くの協力が必要と実感。開催曜日など検討した方がよさそうな点も見えてきたが、「みんなが楽しく過ごせる場にしたい」と気持ちを新たにする。来年1月にも開催を予定し、「また来てね。みんなで交流しましょう」と子どもたちに呼びかけていた。