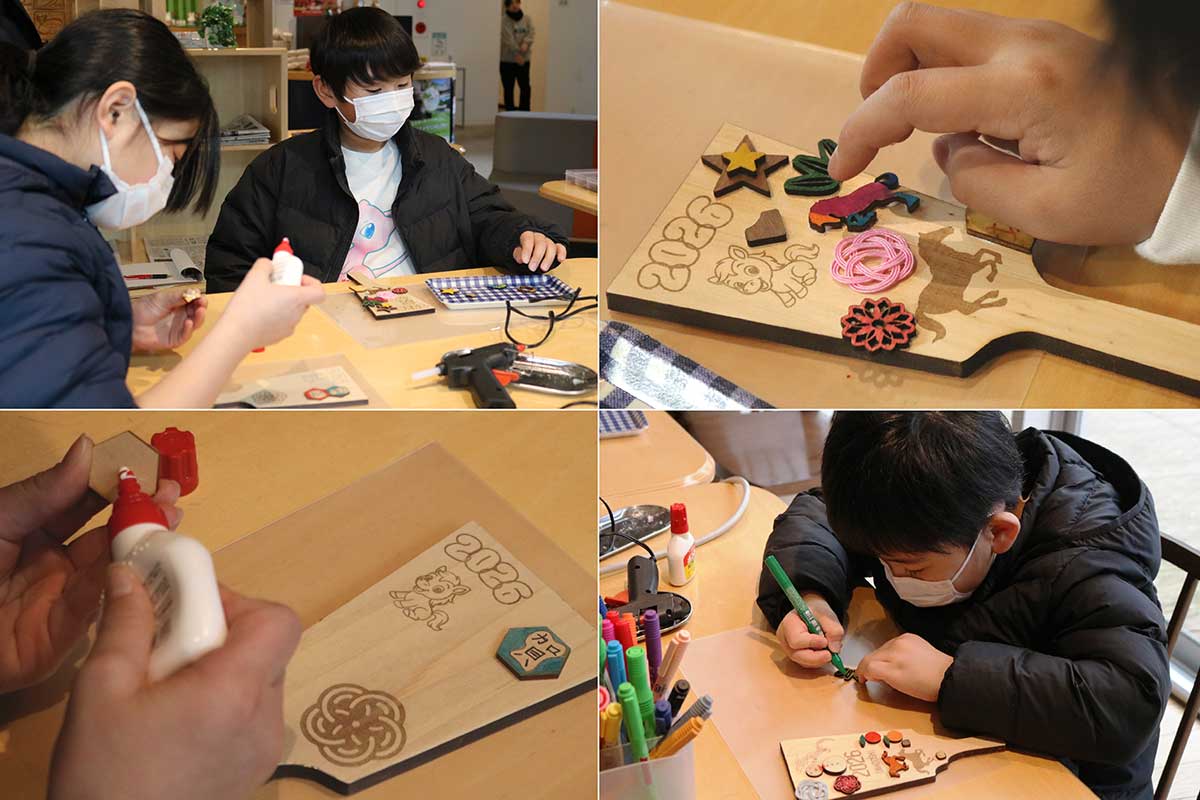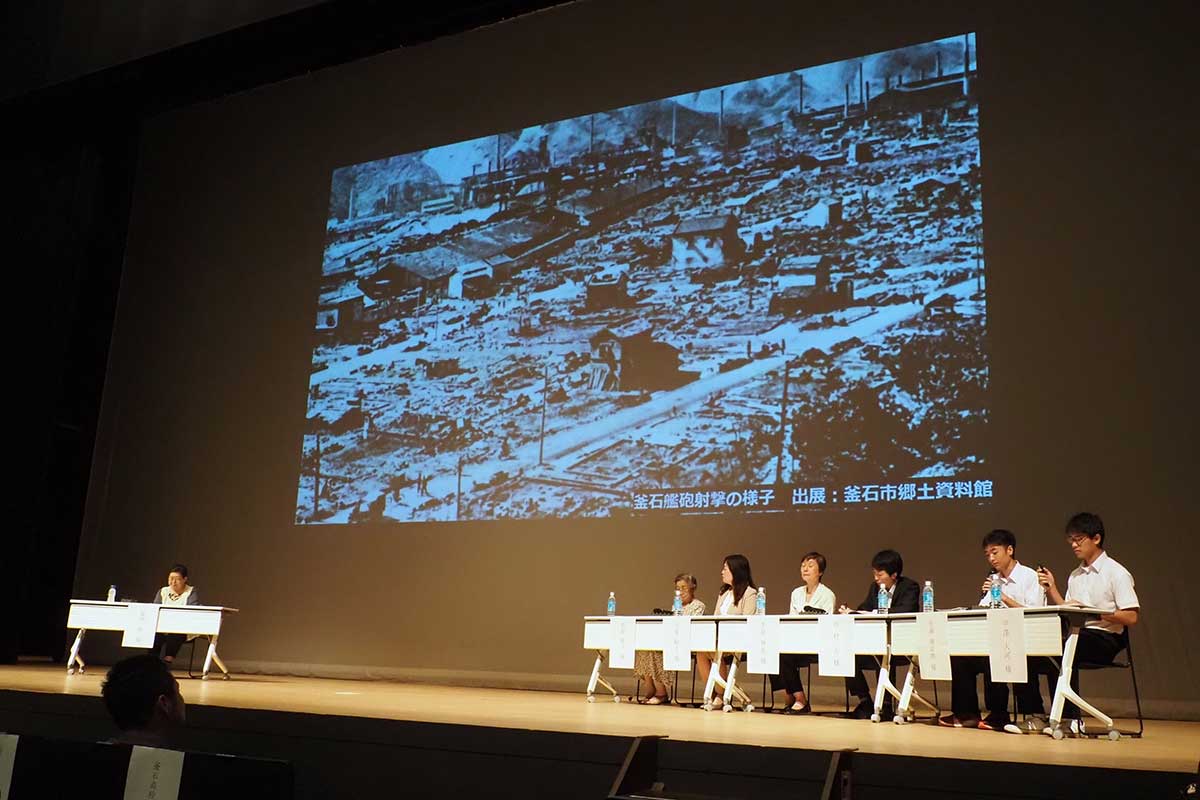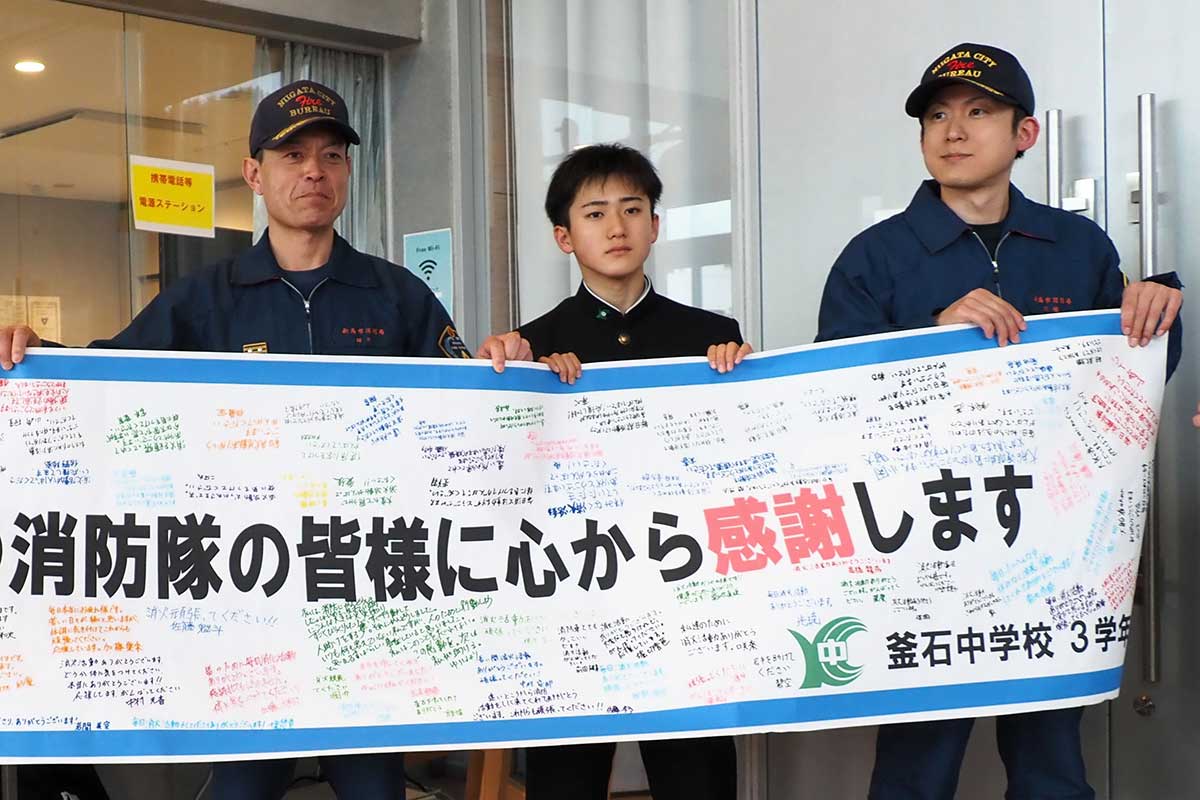2026年、「午(うま)年」の令和8年が始まった。釜石市内は元日早朝から雪が降り出し、冬本番の気候の中、新たな年を迎えた。正月三が日も気温が低い状態が続いたが、晴れの天気に恵まれ、各地の神社や寺は多くの初詣客でにぎわった。充実の1年へ希望を抱く一方で、昨年相次いだ津波警報やクマによる人的被害など、平穏な日常を脅かす事態への不安は尽きない。東日本大震災から15年となる本年―。改めて災害への備えの強化、継続的な危機意識が必要となりそうだ。
年越しは冷え込み緩む中で 釜石総鎮守・八雲神社 地元の家族連れらが続々と参拝

年越しの時間帯を前にした、おおみそか午後11時27分ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、盛岡市で最大震度4、釜石市では震度3を観測。一時、緊張が走ったが、津波の心配はないとのことで、釜石市内の神社や寺には例年通り、新年初のお参りをしようという人たちが足を運んだ。
八雲町の高台に位置する八雲神社(成瀬幸司宮司)には、日付が変わる午前0時を前に参拝客が集まり始め、境内に列を作った。新年を告げる太鼓が打ち鳴らされると、順にさい銭をあげて参拝。昨年の加護に感謝し、新しい年の無事、多幸を願って手を合わせた。本殿では成瀬宮司が「歳旦祭」の祭儀を行い、今年1年の地域の平穏、繁栄を祈願。地元の家族連れらの家内安全、商売繁盛などの祈祷も行った。境内では同神社氏子神和会のメンバーが甘酒を振る舞った。

新しい年への願いを込め、神前に手を合わせる参拝客=八雲神社、元日午前0時すぎ

境内では氏子神和会のメンバーが参拝客に甘酒をお振る舞い
中妻町の友人宅でおおみそかを過ごし、友人家族と連れ立って参拝に訪れた平田の藤原光輝さん(26)は昨年を振り返り、「子どもたちは自我が芽生えて、自分で行動に起こすことが多くなった」と、愛息(4歳、3歳)の著しい成長を実感。今年は「まだやったことがないこととか、いろいろな経験をさせてあげたい」と親心をのぞかせた。自身は社会人野球の選手でもあり、「子どもたちも野球に興味を持ってくれれば」と期待した。
同神社のお膝元、中妻町に暮らす榊原修さん(66)は帰省した娘らと家族4人で初詣。「昨年は病気をしたので、今年は健康第一で」と無病息災を祈願した。毎年、年越しの時間帯に同神社を訪れるが、「参拝客もだいぶ少なくなったね」としみじみ。同地域は人口減や高齢化が顕著だといい、「空き家も多い。若者も高校を卒業して市外に出るとなかなか戻ってこないしね」と寂しさをにじませた。

ちょうちんがともされた神社の参道(右)。複数の石段を上った先に社殿がある

新しい年を迎え、1年の無事を祈るご祈祷(きとう)を受ける家族連れら
八雲神社は鎌倉時代の1193(建久4)年の創建。釜石総鎮守として800年以上の歴史を誇り、江戸時代に盛岡藩主となった南部家から与えられた御紋(向かい鶴)が今に受け継がれる。春の例祭(例祭日:4月17、18日)では、みこし渡御が行われてきたが、コロナ禍以降、祭典関係者の高齢化などもあり、行列は見送られている。
新年の恒例行事としては、氏子神和会による元旦のみそぎ(水ごり)や大寒の裸参りもあったが、こちらも担い手不足などで休止中。同会の釜道浩さん(67)は「人材や資金不足などで神社関連の行事は以前のような形が難しい状況が続いている。新たに移り住んだ住民を含めたコミュニティーの再構築が課題。いつかまた“春”が訪れるよう期待したい」と話した。
雪降る中、初日の出に願い込め 湾内にのびる“光の道”に見物客から感嘆の声

雪模様となった元日早朝。両石港で初日の出を待つ人たち=午前7時前
深夜から早朝にかけて急激に冷え込んだ釜石市内。日の出前は雪が降り続き、路面を白く染めるほどだったが、夜が明けるにつれ、水平線上では雲の隙間から赤みを帯びた空色が見え始めた。釜石市の日の出時刻は午前6時52分。市内でも数少ない海面から昇る朝日を拝める両石港では、国道沿いの空き地などに車を止め、日の出を待つ人の姿が多く見られた。
今年も水平線上には雲がかかり、海面から直接顔を出す姿は拝めなかったが、時間の経過とともに雲の上からまばゆい光が湾内に差し込んだ。漁港の堤防、震災後かさ上げされた国道の路肩、さらに高い住宅地の一角と、思い思いの場所で御来光を拝み、その美しい光景を映像や写真に収めた。

雲の切れ間から太陽が顔を出し、まばゆい光が湾内に差し込む

美しい光景に笑顔を広げる見物客(左)。雲のかかり具合でさまざまな表情を見せる日の出風景(右)
埼玉県から鵜住居町の実家に帰省した古川隆功さん(39)、慶雲さん(11)親子は、防潮堤の階段の踊り場で「きれいだねー。見られて良かったね」と笑顔を広げた。正月の帰省は3年ぶり。慶雲さんは小学校生活最後となる今年、「パソコンのタイピングを頑張りたい。勉強と空手を両立させ、空手の一段を取りたい」と目標を掲げた。実家は東日本大震災の津波で被災。現在は前の場所より内陸部に再建した自宅で両親が暮らす。隆功さんは「最近また地震が多いので心配。自分たち家族も2年前から、飲料水や非常食などの防災グッズを備えている。大きな災害のない1年になれば」と願い、「これから初詣して親戚とかにあいさつに行きたい」と久しぶりの再会を楽しみにした。
沿岸有数の初詣スポット 釜石大観音 市内外からの初詣客で三が日にぎわう

観音像の入り口で新年初のお参りをする人たち=元日午前、釜石大観音
大平町の釜石大観音は例年通り、おおみそか午後10時に開館。年越しの午前0時前後、初日の出時刻の午前7時前後、元日日中は午前10時から午後2時ごろにかけて参拝客がピークを迎えた。朝方の雪の影響はほとんどなく、日の出の時間帯は午前6時ごろから客が一気に増え始め、市営プール前の臨時駐車場まで車両で埋まった。正月三が日の参拝者数は計約7800人。
県内各地のほか、県外から帰省した人たちが地元の家族と一緒に参拝に訪れる姿が多く、中には市内で働く外国人のグループも。幅広い年代が足を運び、それぞれの願いを胸に観音様に手を合わせた。参拝を終えると、おみくじを引いたり、縁起物の熊手や破魔矢、各種お守り、お札を買い求める人たちで境内はにぎわいを見せた。各所で記念写真を撮る人たちも多く、新しい年への期待感を高めた。

高さ48.5メートルの大観音。胸元には釜石湾を一望できる展望台がある(右)。浄土橋から観音像を見上げる家族連れ(左)

「良き年に…」。拝礼し祈りをささげる参拝客

釜石大観音は2016年に「恋人の聖地」に選ばれた。ハート型のモニュメントは人気の記念撮影スポット
大船渡市の嶋鈴子さん(71)は娘や孫ら6人で参拝。昨年は同市で大規模山林火災が発生。クマの出没も多く、心落ち着かない日々が続いた。「(火災で)浜関係の人たちは水揚げが減るなど大変な思いをしている。今年は被災した人たちの暮らしが少しでも良くなればいい」と心を寄せる。自身は今年「年女」。えとの“うま”にかけ、「あちこち飛び回って元気に過ごせれば。旅行にも行きたい」と笑った。孫の金野幸歩さん(21)は仙台市から帰省した。「ばあばのおいしいご飯が食べられるのと、なかなか会えない親戚と話をするのが楽しい」と正月休みを満喫。昨年、保育士となり、今年は社会人2年目に入る。「まずは病気にかからないように…。仕事では自分のやりたいことに挑戦できれば。子ども心を忘れず、寄り添える保育士になりたい」と理想を描いた。
東京都から宮古市の実家に帰省した会社員の男性(19)は、家族と大観音に初詣。おみくじで「大吉」を引き当て、幸先の良い新年のスタートを切った。社会人1年目の昨年は、施工管理技士などの資格を取得し、公私ともに充実。「今年も右肩上がりで生活できれば」と順風満帆な1年に期待する。20歳を迎える年でもあることから、「今までお世話になった人たちに恩返しができれば。感謝を伝えたい」と思いを込めた。

おみくじ、お守りなどの販売コーナー、キッチンカーの出店で境内は終日、にぎわいを見せた
境内にはキッチンカーなど飲食の5店が出店した。厳しい寒さの中、温かいコーヒー販売で人気を集めたのは、釜石ではおなじみの移動販売車「HAPPIECE COFFEE(ハピスコーヒー)」。店主の岩鼻伸介さん(48)は今年3月、釜石大観音仲見世通りの空き物件を利用し固定店舗を開く予定で、現在、店内の改装など開店準備を進めている。新店舗は、2024年に発生した能登半島地震の被災地に通い続ける岩鼻さんが継続支援のために構想。能登と釜石をオンラインでつなぎ、コーヒーの入れ方をレクチャーしたり、両地域の住民が交流できるような場として整備する。

釜石大観音仲見世通りに新店舗を構える予定のハピスコーヒー店主、岩鼻伸介さん(右)
「能登と釜石の架け橋になる…」。発災から2年となった元日、新たな挑戦に意欲をみなぎらせた岩鼻さん。「コーヒー好きの方に楽しんでもらえるような“とがった”店にしたい。ワクワクしながら待っていてください!」。釜石発のフェアトレードコーヒー専門店に期待が高まる。