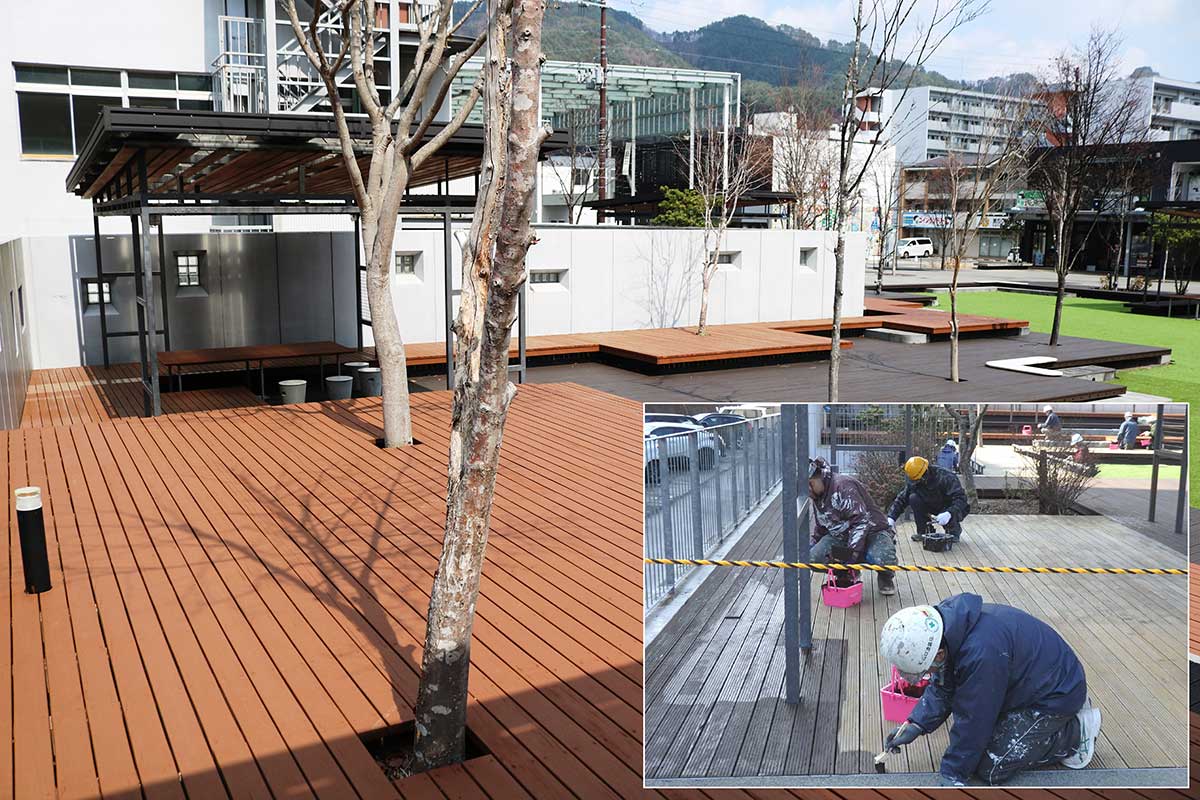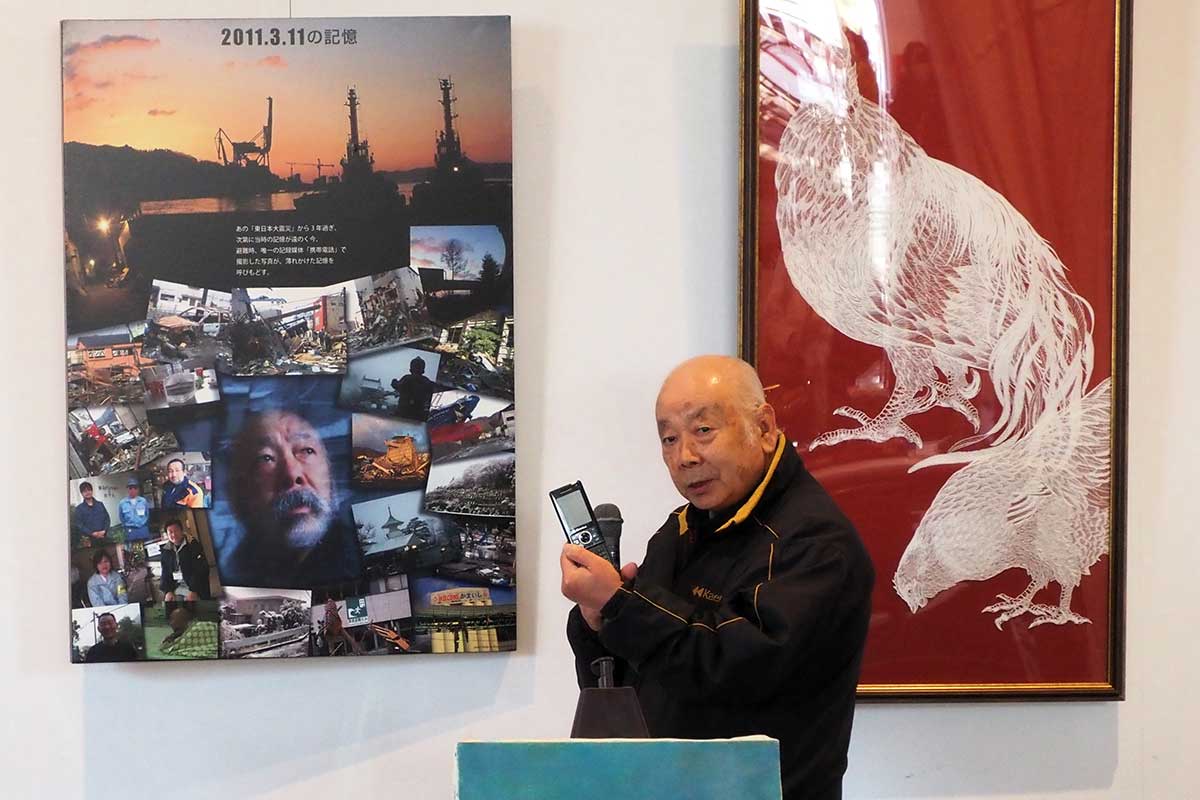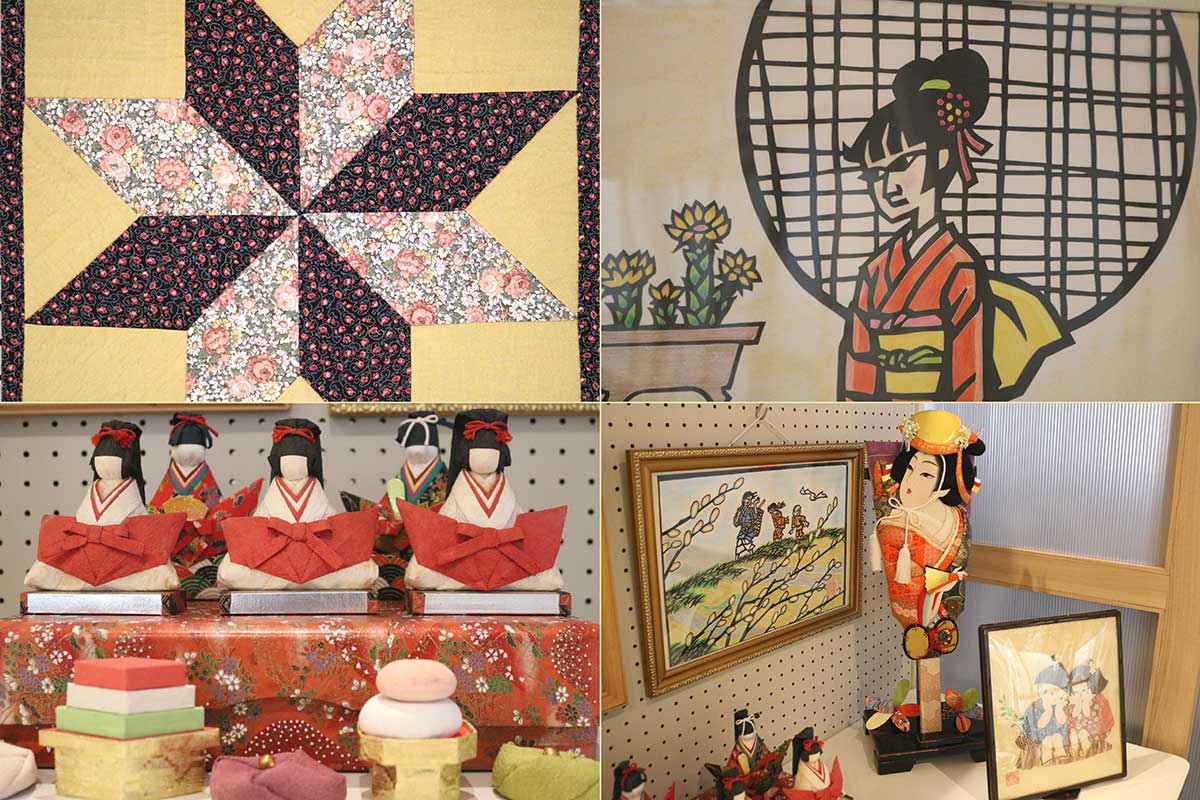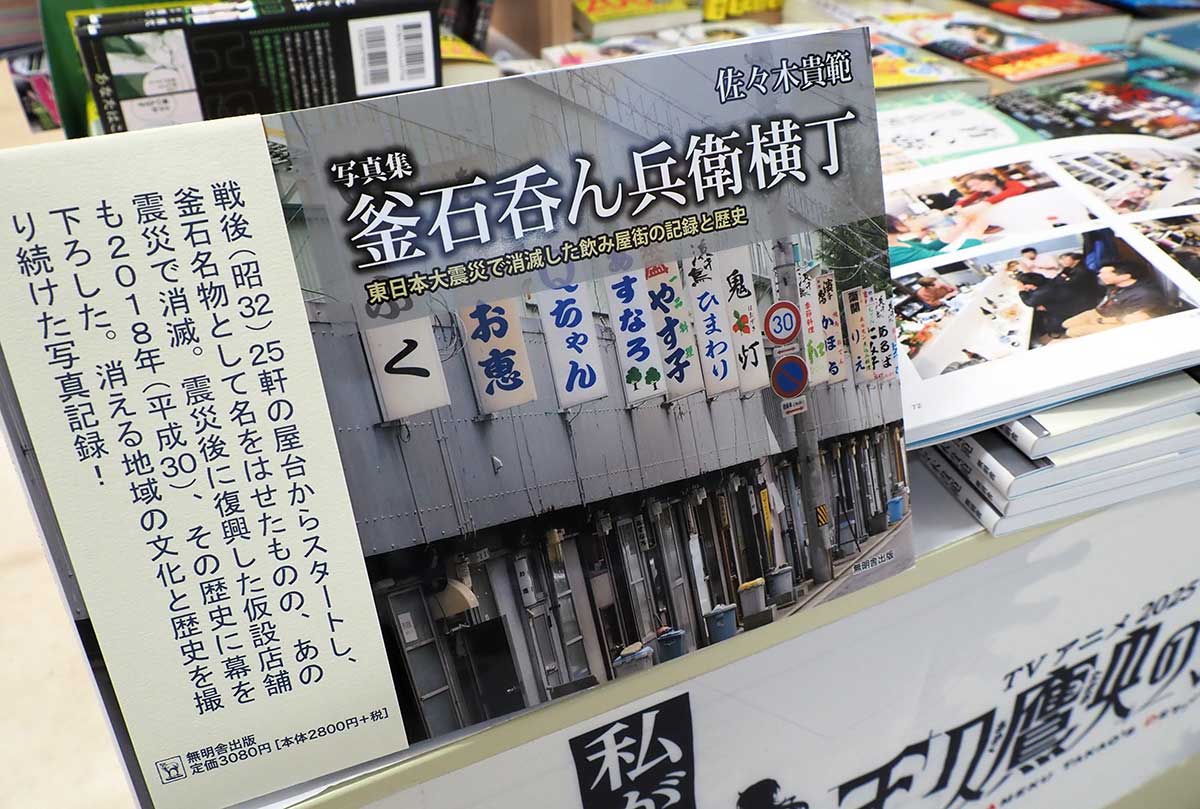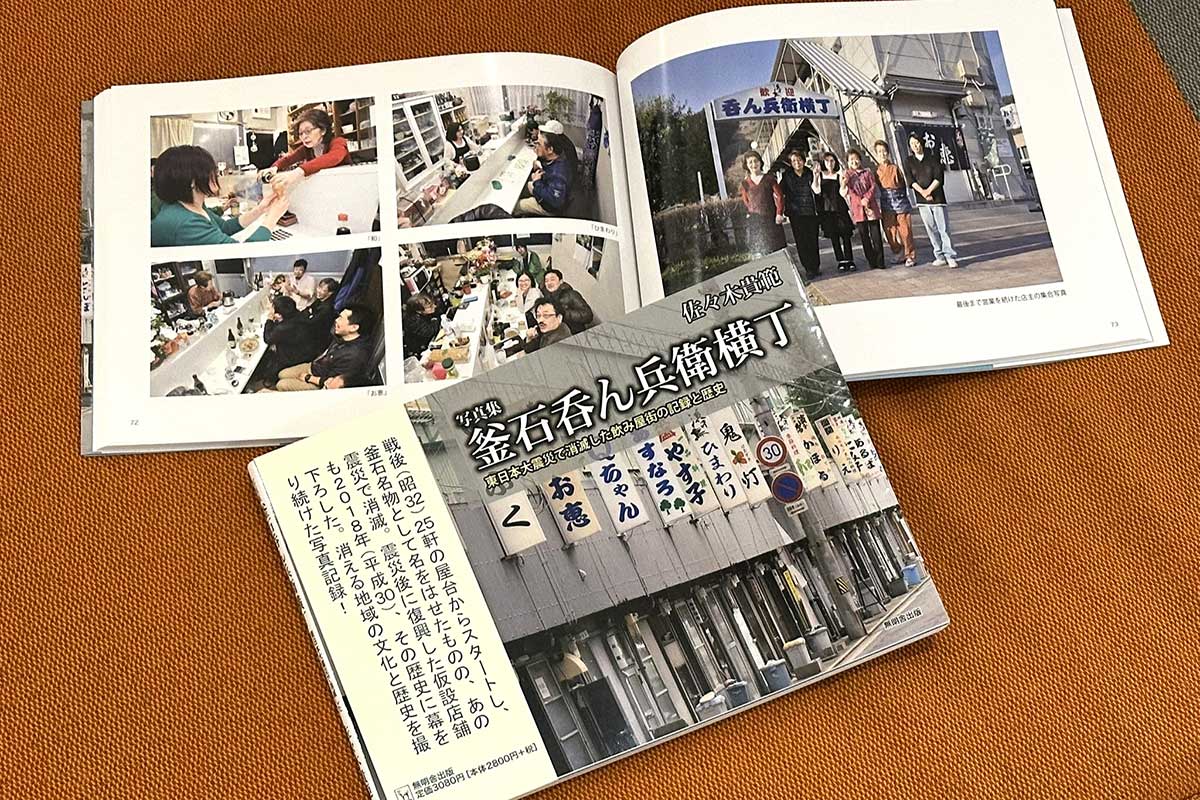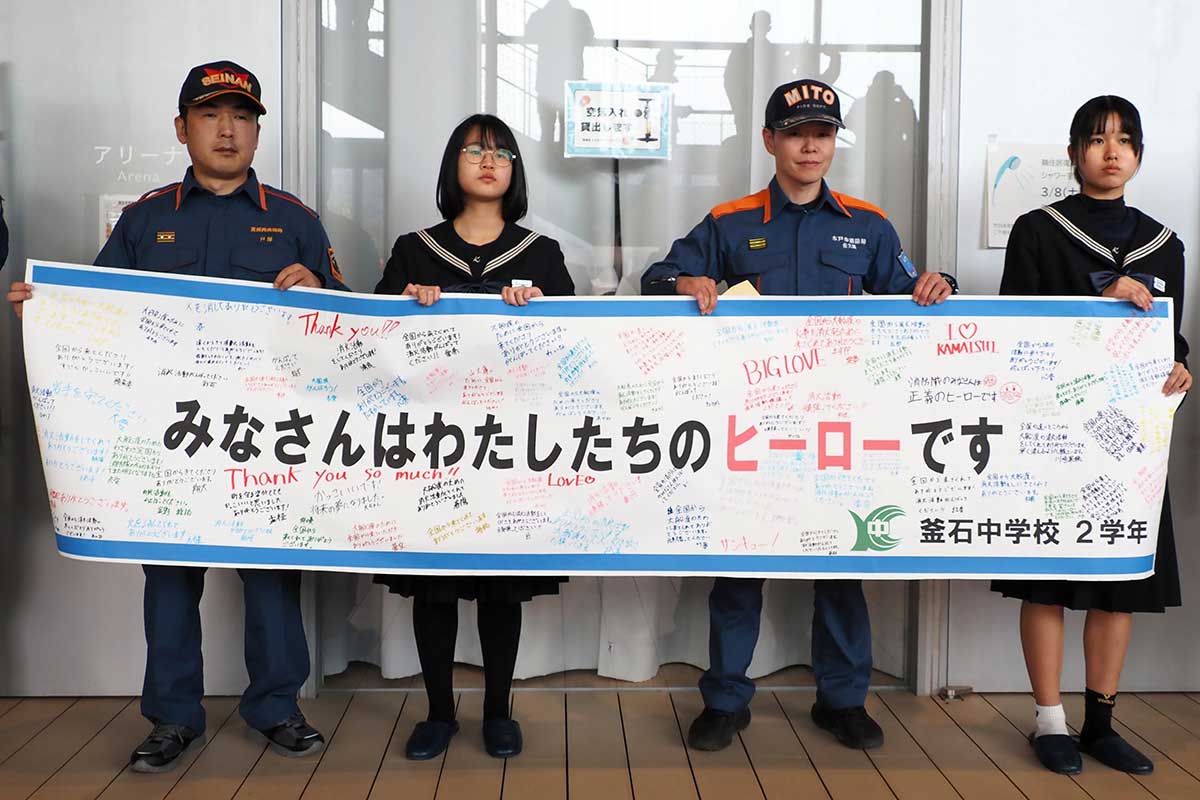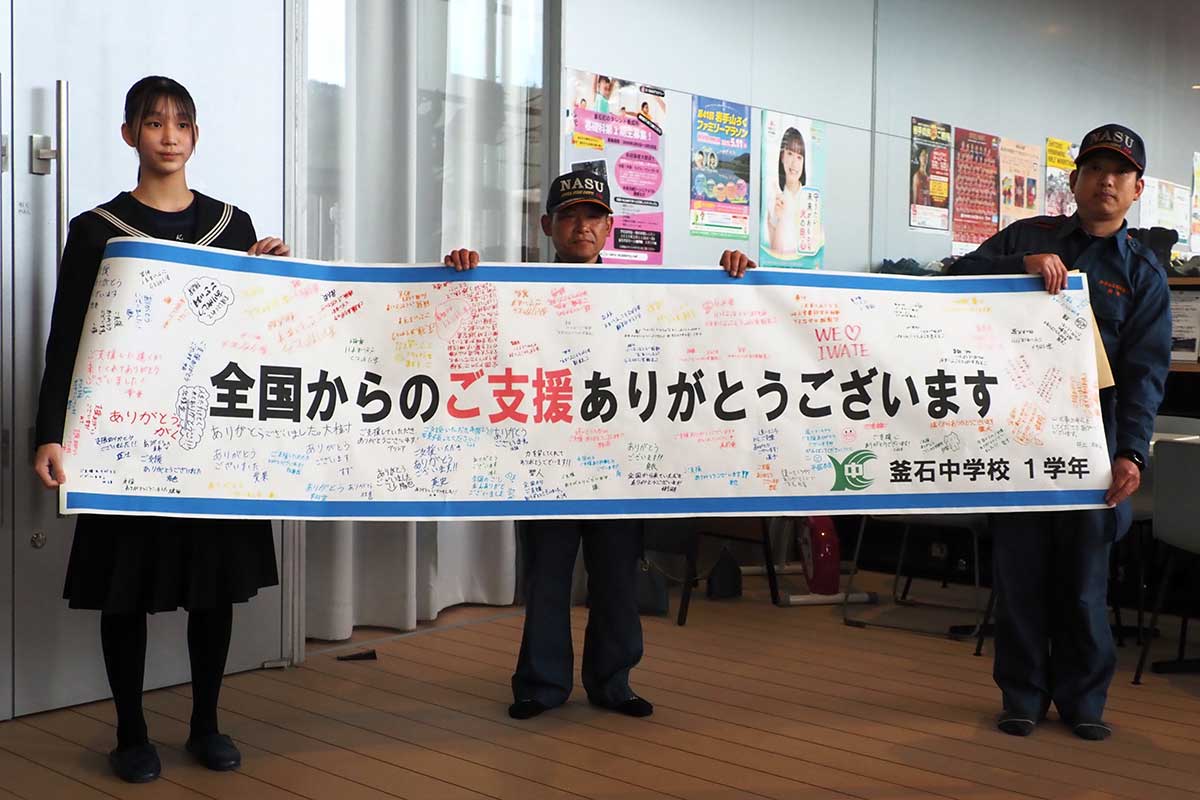大地震で被災した能登地方の新入学児童に贈るトラキーホルダー。釜石トラ作りの会が制作
石川県北部、奥能登地域を中心に甚大な被害をもたらした能登半島地震から、今日で1年3カ月―。復旧復興が続く同地域の小学校に今春、入学する新1年生を応援したいと、東日本大震災で被災した釜石市の市民グループが手作りのお祝い品を贈った。贈り主は同市平田を拠点に活動する、釜石トラ作りの会(前川かな代表、会員10人)。同市の郷土芸能“虎舞”をモチーフに制作したキーホルダーが入学祝いの品だ。「虎は千里行って千里帰る」という故事から、漁師らの無事帰還を願って古くから踊られてきた虎舞。キーホルダーには新入学児童が安全に通学し、無事に帰宅してほしいとの願いが込められる。
トラキーホルダーは、能登町の宇出津小など5校と輪島市の門前東小など3校、計65人の新1年生に贈られる。黄色のクラフトテープを編んで一つ一つ手作業で仕上げたキーホルダーには、「入学おめでとう 交通安全に気をつけてね!」というメッセージカードが添えられる。会の活動と寄贈に込めた思いを記した手紙も各学校に届けてもらう。

釜石市の平田公民館で活動する「釜石トラ作りの会」=3月9日

新入学児童に贈るキーホルダーを箱に詰める前川かな代表

トラ作りの会からキーホルダーを託される伊藤聡さん(左)。各校には手紙(右上)も一緒に届けてもらう
キーホルダーは3月27日、両市町に届けられた。輪島市を拠点とする民間のボランティアセンター「RQ能登」で昨年2月からコーディネーターとして活動する釜石市出身の伊藤聡さん(45)=さんつな代表=が、会から託された祝い品を担当者に直接手渡した。両担当者は予想以上の出来栄えに驚いた様子だったという。能登町教育委員会事務局の喜多隆志主幹は「大地震による被災で子どもたちは大変な思いをしたが、全国から温かい励ましやさまざまな支援をいただき、学校生活を送れている。皆さまからの応援は子どもたちにとって大きな力となっている」と、感謝の言葉を口にしたという。

伊藤さんからトラキーホルダーを受け取った輪島市支援調整窓口スタッフの澤田かをりさん(右)=写真提供:伊藤さん

トラキーホルダーを手にする能登町教委の喜多隆志さん(右)=写真提供:同
釜石トラ作りの会は、震災で被災した同市平田地区の住民が立ち上げた。仮設住宅入居時に行われたサロン活動でクラフトテープを使った物づくりを覚え、6年ほど前からは虎舞をモチーフにしたキーホルダーを作り、地元小学校の新入学児童に贈っている。メンバーのほとんどが同震災の津波で自宅を失うなどした被災者。全国で頻発する自然災害のニュースを目にするたび心を痛め、被害にあわれた人たちを案じてきた。会の活動が軌道に乗ってきたこともあり、「自分たちのできることで被災地の子どもたちを励ましたい」と、今回初めて能登地方の新入学児童へのキーホルダー贈呈を発案した。
仲介役を担った伊藤さんは3月上旬、会のメンバーが制作活動を行う平田公民館を訪問。前川代表(60)からこれまでの活動の経緯などを聞くとともに、発災から1年が経過した能登の現状を伝えた。伊藤さんによると、現地は倒壊した家屋の公費解体がやっと進んできたところ。地震被害がまちの全域に及び、9月には豪雨災害もあったため復旧復興の遅れが顕著で、被災者の多くは今も仮設住宅などでの避難生活を余儀なくされているという。
同会の活動のきっかけを聞いた伊藤さんは「向こうの仮設(住宅)にも手仕事の上手なお母さん方がいる。こういう活動があれば住民が集まる場もでき、孤立防止にも役立つ」とコミュニティー維持のヒントも得た様子。14年前の大震災被災の当事者でもあることから、「今回のような支援は気持ちと気持ちがつながるもの。もらった小学生は成長する過程でその意義を感じるようになるのではないか」と話した。

キーホルダーを受け取りに訪れた伊藤さんに会の活動経緯を伝えるメンバー

伊藤さんも平田出身。地元ならではの話題も出て会話が弾む
「私たちも全国の人たちから支援を受けて今がある。一人ではできなくても、みんなでやればできることもある」と前川代表。子どもへの支援を考えた背景には14年前の実体験がある。「子どもが元気だと大人も元気になれる。子どもたちの姿に親や祖父母は頑張る力をもらい、生活再建やまちの復興を成し遂げてきた。今回の贈り物が能登の子どもたちの笑顔につながれば…」。トラキーホルダーが揺れるランドセル姿の新1年生を思い浮かべながら、メンバーらは制作活動を続ける。