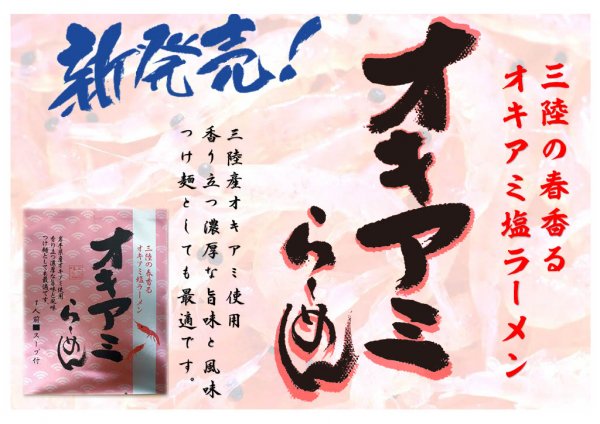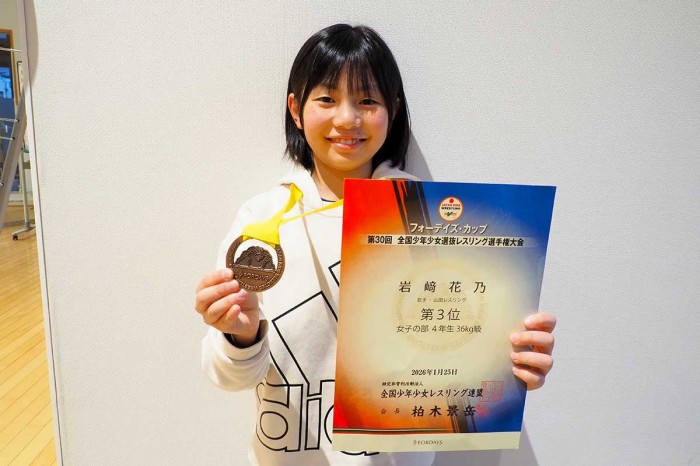おいしい「甲子柿」届けたい 釜石の生産者 冬場の管理、知識深化へ講習会

柿の木のせん定の仕方を学ぶ「甲子柿」の生産者ら
良い柿の実を作り、収穫、販売につなげようと釜石市甲子町などで1月30日、柿の木のせん定講習会が開かれた。甲子柿の里生産組合(佐々木裕一組合長)が、栽培農家の底上げを狙い、毎年この時期に実施。大船渡農業改良普及センター農業普及員の千田聡実さん(31)が講師を務め、枝切り作業のポイントを教えた。
組合員ら約20人が参加。一部でせん定作業を始めている佐々木組合長(74)の柿畑(甲子・大畑)を見学した後、甲子町松倉で柿を育てる佐野朋彦さん(45)の畑に移動して成木のせん定作業の実演を見守った。

甲子町松倉地区の畑で枝切作業の実演を見守る参加者
千田さんは「成木は実の付き、バランスを考え、樹形を整える視点が必要」と強調。ノコギリやハサミを手に収穫期に良い実を出すために軸となる枝を決め、日当たりをさえぎるような不要な枝を切っていった。「悩ましいとことは多々あると思う。二股に分かれていたり、上に向かって勢い良すぎるくらい伸びている枝は切った方がいい。幹に向かって内側に伸びる枝も」などと助言。作業しやすさも考慮し、樹高を「ほど良く」することもポイントとして挙げた。
見守った組合員らは「どこを切ればいいか悩む。なかなか切れない」と難しさをこぼした。親の代から柿生産を続ける60代女性は「大木で枝も多く、実がなると重さで垂れさがる。木を小さくコンパクトにしたいが、数が多くて大変。でも、良いものをとって届けたいから、少しずつやってみる」と話した。

「自分だったら」と意見を出し合う生産者たち

小川町の柿畑で枝切りのポイントを説明する千田聡実さん(左)
組合は現在、約30の個人、団体が加入する。昨年は30代の若手1人が加わった。新規就農者や収量アップを考えている人らの参考にと、幼木(植えて1年ほど、未収穫)のせん定方法も研修内容に組み込んだ。小川町の佐々木智勇さん(66)の畑で実演。千田さんは「幼木はまず体をしっかりつくること。よく伸び、成長させることを考えて」とアドバイスした。このほか、参加者は座学で病害虫防除についても知識を深めた。
甲子柿は、甲子地区で育った小枝柿(渋柿の一種)を煙でいぶして甘さを凝縮させた地域の特産品。真っ赤に染まる鮮やかな色味とぷるんとした食感が特長。豊富な栄養素も注目され、国の2つの制度(地理的表示[GI]保護制度、機能性表示食品)で特性が認められている。

甲子地区で育つ柿の木。実の色合いは淡い

煙でいぶして渋抜きすると、釜石特産「甲子柿」に
ただ、近年は気象や温暖化などの影響を受け、一年ごとに豊作と不作を繰り返している。組合ではブランド化を進める中、講習会の開催などで高品質安定生産に向けた栽培管理、技術向上を図ってきた。
組合などによると、2024年は夏場の気温が高めだったものの、順調に成育。ところが、収穫直前、9月の豪雨などで実が落ち、一部では落葉病など病害の影響も重なり、収量が予測より減った。実は残ったとしても、葉が落ちたことで栄養が十分に取り込めず、「甘味が不十分」と収穫を見送った農家もあったという。

仲間と情報を交換する佐々木裕一組合長(左)
佐々木組合長も、半分ほどを収穫しなかった。それでも年間収量は例年と変わらずで、「長年の栽培管理のたまものだ」という。一方で、天候などの影響で収穫が遅れ、「自然が相手」の作業に改めて難しさを感じている。
それでも、「好きだから、やれる」と笑う佐々木組合長。高齢の人には“小ぶり”のイメージがある甲子柿だが、最近はずっしりと重みのある“大ぶり”なものも増えている。「地域ならではだから残したい」。楽しみにしている人たちに季節の味を届けるべく、挑戦を続ける。