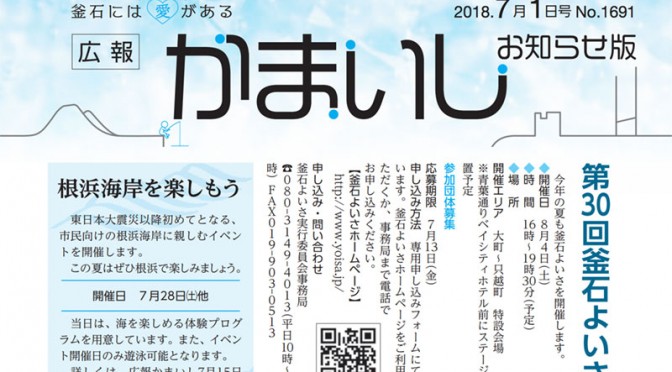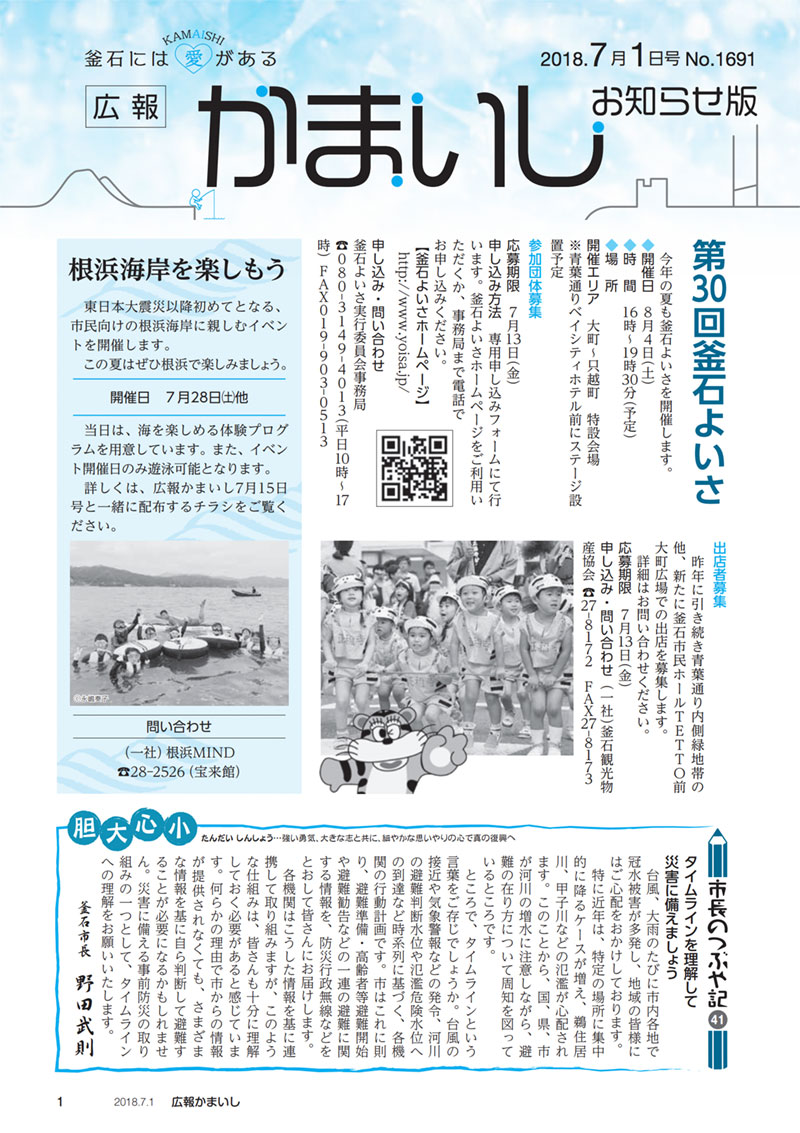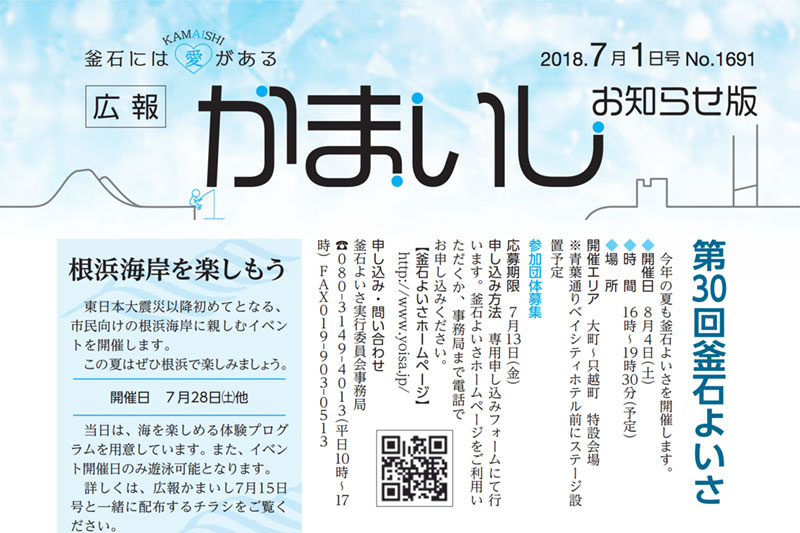東日本大震災から8度目の夏を迎えた三陸沿岸各地から、「震災後初の海開き」という嬉しい便りが届き始めています。
釜石ではまだ正式に“海開き”と言える状況ではありませんが、安全に海あそびが出来る環境が整った根浜海岸で、7月28日・29日の2日間、海で泳ぎ、海を身近に楽しめるイベントが開催されます。
イベントの主催団体(一社)根浜MINDは、ふるさとの風景を守り、未来につなげる活動を行っています。事務局の廣田一樹さん(宝来館)に、これまでの活動や今回のイベントについて伺って来ました。
ふるさとの海辺の風景を守り、未来へつなげたい

ーー根浜MINDはどのような経緯で発足したのでしょうか?
廣田さん:
きっかけは、この地域に欠かせない「観光」でした。
震災後、それまではどちらかと言うと、誰かが何かやってくれるのを待っていた状態だったのですが、お隣大槌町の浪板海岸では住民主導での海岸復活の動きがあり、観光施設などが出来上がっていく過程を見て、「このまま待っていては行けない。自分たちで何とかして行かなくては。」という気持ちが、住民やこの地域に関わる人たちの中で大きくなりました。
そして、「海辺の暮らし、風景を守って行こう」と、2016年7月に地域住民が中心となって団体を立ち上げ、代表の岩崎昭子(宝来館)を含めた6名と事務局2名で活動しています。

ーーどのような活動をされていますか?
廣田さん:
防災、減災活動として宝来館の裏山に避難経路を整備したほか、震災後に出来たご縁により英国ロンドン芸術大学からご支援を頂き、英国式レスキューボートによる住民主体の水難救助システム構築を目指し活動を進めています。
また、震災によって三陸沿岸各地では、砂浜とともにそこで見られた海浜植物なども消えてしまった地域が多いですが、根浜海岸には奇跡的に植物が残りました。岩手ではここだけだそうです。
その、ハマナス(バラ科のピンク色の花)やハマボウフウ(薬草で絶滅危惧種に指定されている)を増やして根浜海岸の原風景を取り戻し、それを守り続けて行く為に、特産品として活用して行こうという活動もしています。
これら海浜植物を増やす活動については、今年から地元の東中学校の全校生徒も一緒に取り組んでいて、種から苗を育て、海辺の清掃活動をし、秋には海岸での植栽を予定しています。

子ども達に海での楽しい思い出を
ーーイベントのチラシですが、子ども達の笑顔の写真が印象的ですね。
廣田さん:
震災から丸7年が経った今でも、“海はこわいもの”という認識を持った子ども達がまだ多いと思うのですが、子ども達にはやはり海の楽しさも知って欲しいです。
この地域の子どもは、どの世代も海と密接な関わりがあったそうですが、今はそういう機会が少なくなってしまいましたし、通学路も海を通らず山側を通るようになり、海との物理的な距離も出来ています。
先ほどの中学生の海浜植物再生の取り組みも、海岸清掃から始めて、まずは海を眺めてもらう機会を作る所からと、いきなり「海で泳ごう」ではなくて、段階を踏みながら海との距離を縮めてもらおうという側面も持ち合わせながら行っている部分もあるんです。

ーー廣田さんは関東のご出身ですが、ご自身も根浜海岸での思い出があるそうですね。
廣田さん:
母の実家が山田町で、夏休みに帰省した時には必ず一度は根浜海岸で遊びました。
その頃、この海には滑り台などの遊具が浮かんでいて、すごく特別な海水浴場だったんです。
遊具は子供では足がつかないちょっと深い所にあって、小さい頃はそこまで行くことが出来なくて、年上の子たちが遊んでいる姿を羨ましく見ながら、「早くあそこまで行けるようになりたい!」と思っていました。そして、そこで遊べるようになった時、「少し大人になったな!」と誇らしい気持ちになった事を覚えています。
今になって知ったのですが、実はその遊具は、根浜MINDのメンバーでもある前川民宿さんが毎年浮かべてくれていたものだったんです。
自分自身の楽しい思い出と、地元の方々の想いがつながった瞬間でした。
ここが好き~いつかまた地元の人たちでにぎわう海辺の景色が戻るまで
ーープログラムを提供するメンバーも多彩ですね!
廣田さん:
どちらかと言えば、外から来た人たちが多いのですが、「海が好き」という共通の想いがあるメンバーが集まっています。
それだけ、根浜の人や場所に魅力があるという事だと思います。
今回も“皆さんに楽しんでもらえる空間を”と、海で思いっきり遊ぶのはもちろん、海に入らなくても周辺で楽しめるプログラムもご用意しています!
養浜終了後には本格的な海開きが行われる予定ですが、震災から8度目の夏にこのような海を楽しむイベントを開催出来るまでになり、ようやく第一歩を踏み出せたという感じがします。
今でも海に向き合えないという想いを抱えている方も多くいらっしゃると思いますが、そこは私たちの力ではどうにもできない、踏み込めない領域です。
今はまだ海と向き合えなくても、地元の人たちが「海にふれる」という気持ちになった時に変わらない三陸の風景をみんなで作り守ってつなげていきたい、そう思っています。
2018夏 根浜海岸 海あそび 祈り、そして未来を願って

・2018夏 根浜海岸 海あそび チラシ表(JPGファイル/260KB)
・2018夏 根浜海岸 海あそび チラシ裏(JPGファイル/226KB)
開催日時
2018年7月28日(土)29日(日) 午前9時~午後4時
28日 9時30分~オープニングセレモニーで虎舞披露!!
場所
釜石市根浜海岸、根浜緑地公園
海あそびプログラム
陸の思い出ワークショップ/SUP体験/シュノーケル/ねばだるま絵付け体験/レスキューボート体験等
同時開催:根浜写真展~根浜地区の震災前~現在の写真展示
イベントのちらしは、7月15日発行の広報かまいしと一緒に配布されています。
また、詳細は以下のSNSサイトなどもご覧ください。
釜石の観光のFacebookはこちら
https://www.facebook.com/kamaishikankou
根浜MINDのFacebookはこちら
https://www.facebook.com/nebamamind/
かまいし情報ポータルサイト〜縁とらんす
縁とらんす編集部による記事です。
問い合わせ:0193-22-3607 〒026-0024 岩手県釜石市大町1-1-10 釜石情報交流センター内