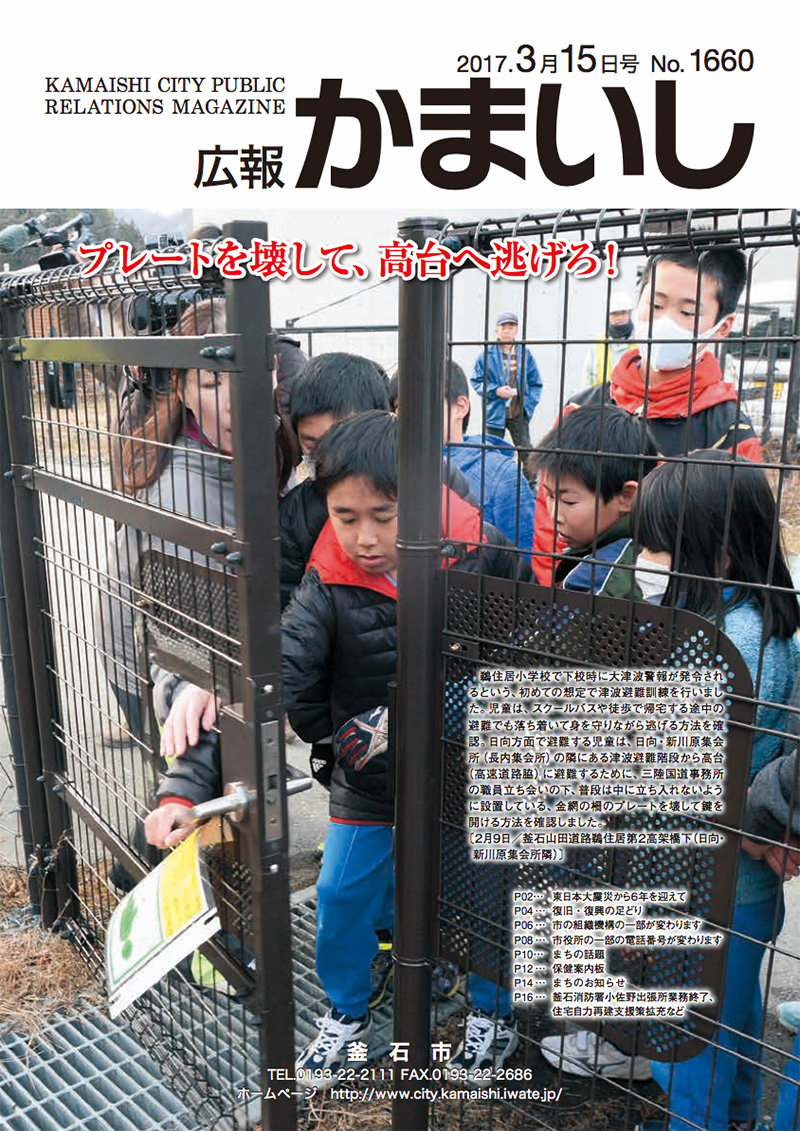今後、釜石のまちづくりに必要なことは何かを考えたパネル討論
釜石シティプロモーション推進委(柏﨑龍太郎委員長)主催の「Meetup Kamaishi(ミートアップ釜石)2017~釜石のお宝&鉄人発掘博覧会」は18日から3日間、市内各所で開催された。震災復興で育まれた市内外の人々の絆と地域資源をまちづくりの次のステップに生かそうと、フォーラムや観光体験プログラムを展開。市が掲げる「オープンシティ釜石」の実現へ官民が協働で取り組み、まちの未来像を探った。
18日、大町の情報交流センター釜石PITでは、2015年9月に国連が採択した「持続可能な開発目標(SDGs)」をキーワードにオープンシティフォーラムが開かれた。SDGsは、全ての国連加盟国がより良き未来のために、30年をゴールとして取り組むべき17の目標と169のターゲットを定めたもの。繁栄、平和、暮らしの保障を目指し、経済、社会、環境を統合的に考え行動することが求められている。
解説した法政大デザイン工学部建築学科専任講師の川久保俊さんは「この目標を自分事として捉えるため、国はまちづくりの枠組みでの実践を奨励。目標達成には世界に目を向けつつ、各地域が課題を認識し取り組む必要がある」とし、一人一人が主役であることを強調した。
「持続可能な地域とは何か」をテーマとしたパネル討論には、市内外の法人の代表など5人が出演。これまでの活動を紹介し、今後の取り組みへ意見を交わした。
地元事業者らが案内役を務める体験型プログラムを提供してきた三陸ひとつなぎ自然学校の伊藤聡代表理事は「地域が疲弊しない少人数の受け入れが持続性を生む。多様な人の協力、連携で実施できているのが今の釜石らしさ。次の世代に背中を見せていくことを意識していきたい」と決意を示した。
就労意欲を持つ子育て中の女性と人材不足の事業者を超短時間勤務(プチ勤務)という形でマッチングさせてきたWillLabの小安美和代表取締役(市地方創生アドバイザー)は「まちを成長させていく人たちがどう在りたいか。外部の人をただ受け入れるだけでなく、議論ができていくと本当のオープンシティになっていくのでは」と助言した。
@リアスNPOサポートセンターの鹿野順一代表理事は「釜石はいろいろなことが形になっていると言われるが、それをコーディネートする仕組みが無いと地域のものになっていかない」と指摘した。
最後は、釜石の地域資源を活用し起業する「ローカルベンチャー」を志す6人が事業アイデアを発表。▽根浜海岸でのアクティビティー開発など観光事業で交流人口拡大を目指す▽観光客らに個人の車を有料で貸し出す「カーシェア」で移動格差をなくす▽恵まれた自然環境を使って子どもたちが自ら考え行動する姿勢を育てる―など、地域の課題解決につながる新ビジネスを提案した。起業支援を目的としたアイデア募集には27件の応募があり、今後、支援対象者を絞り込み、6月の事業開始を目指す。
(復興釜石新聞 2017年3月22日発行 第573号より)
Meetup Kamaishi 2017 | オープンシティ釜石

復興釜石新聞(合同会社 釜石新聞社)
復興釜石新聞と連携し、各号紙面より数日の期間を設け記者のピックアップ記事を2〜3点掲載しています。問い合わせ:0193-55-4713 〒026-0044 岩手県釜石市住吉町3-3