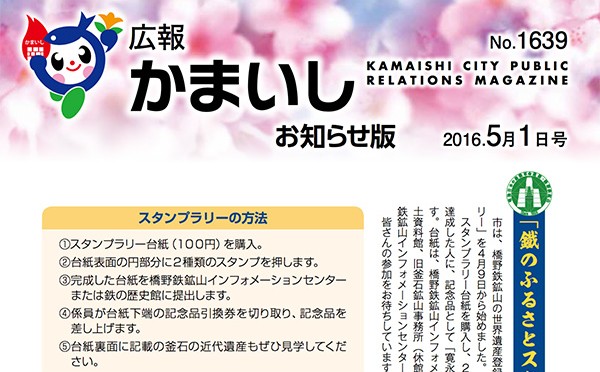出演バンドの熱いライブにこぶしを突き上げ応える観客ら
被災した中心市街地のにぎわい再生を目指す音楽イベント「Oh!マチ Music Festa(おお!まちミュージックフェスタ)」(同実行委主催)が3日、釜石市大町の青葉通りで開かれた。昨年に続き2回目。今年は野外ステージでの演奏に加え、東部地区の商業者らによる「青葉マルシェ(市場)」も開かれ、街の顔となる新たな商店街形成に向け弾みをつけた。
市内外の応募者24組から実行委の審査で選ばれた10組が出演。
通り沿いの2ホテルの前に設けたステージで、それぞれロックやアコースティックなどの演奏パフォーマンスを繰り広げた。
スペシャルゲスト2組も招かれた。滋賀県大津市出身の男性4人組バンド「climbgrow(クライムグロウ)」は、10代限定のロックフェス「閃光ライオット2014」で、1万組を超える応募の中で準グランプリを獲得した実力派。熱いライブで観客を引きつけた。

スペシャルゲストの「climbgrow」は岩手県初上陸で注目を集めた
専門学校の同級生だった山崎春紫(つくし)さん(21)=遠野市出身=と菊池結衣さん(21)=釜石市出身=は、通りがかりにイベントに出会い、「街の中心で音楽イベントがあるのは魅力的。(被災した青葉通りが)ここまで復興したのは素直にうれしい」と楽しい空間に笑顔を見せた。
マルシェでは、東部コミュニティ共同出店テントに23事業者が商品を提供。被災し再建を果たした店や本設を目指し仮設店舗で営業中の店が、グルメ、美容、雑貨など自慢の一品を持ち寄った。タウンポート大町の共同出店やかまいしキッチンカー、市民らによるフリーマーケットなどもあり、幅広い年代の購買意欲をかき立てた。

さまざまな店舗が出店し青葉通りににぎわいを生んだマルシェ
新里耕司実行委員長(大町商店街振興組合理事長)は「マルシェ効果もあり青葉通り内に人の流れが生まれ、昨年より人出が多い」と効果を実感。中心商店街について、「被災店舗の再建も少しずつ進んでいるが、商店街の街並みが出来上がるまでには時間がかかりそう。復興住宅が完成し住民が戻ってくれば、商業者の再建もさらに進むのでは」と期待し、目抜き通りだけではない広域での商店街展開を未来の姿として描いた。
会場では熊本地震の義援金募金活動も行われた。
(復興釜石新聞 2016年5月11日発行 第485号より)

復興釜石新聞(合同会社 釜石新聞社)
復興釜石新聞と連携し、各号紙面より数日の期間を設け記者のピックアップ記事を2〜3点掲載しています。問い合わせ:0193-55-4713 〒026-0044 岩手県釜石市住吉町3-3