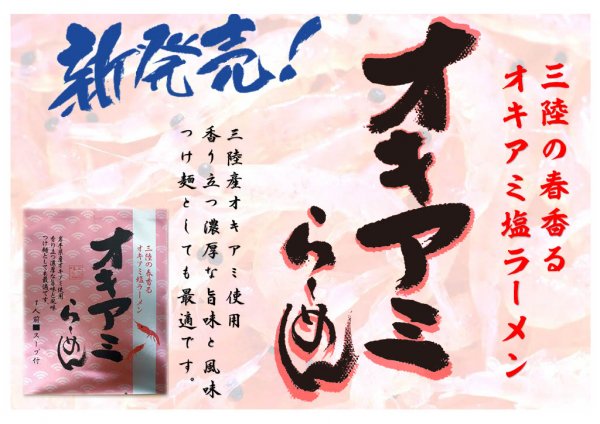つなぐ「あの日」の記憶 釜石出身・2人の演劇人「忘れない」 震災題材の舞台2本立て上演

演劇で震災の記憶を伝える小笠原景子さん(左)、内沢雅彦さん
東日本大震災の記憶をつなぐ舞台「あの3月11日を忘れない 一人の芝居」は8~10日、釜石市で上演された。地元の劇団もしょこむの小笠原景子さん(39)、東京の劇団黒テントの内沢雅彦さん(63)による一人芝居2演目。演劇という表現でつながる同郷の2人は、それぞれ地元ゆかりの作家が紡いだ物語やつづった言葉に思いをのせ発信した。毎年巡ってくる“あの日”をどのような日にするか。自らに問いかけ、感情をそっと抱きしめるように。観客と語り合う時間もあり、気持ちを重ねながら地域を見つめた。
この公演は内沢さんが企画した。震災当時に「古里の力になれなかった」という思いを持っていたが、ある物語との出合いで「今こそ、演劇で」と背中を押され、あの日から12年となる昨年、古里公演を実現。「演じることで同郷の人、気持ちと向き合えた」と、今年も続けることにした。今回は、女性目線の震災も伝えようと、小笠原さんにオファー。会場は大只越町出身の内沢さんにとって「抱きしめたくなるような思い出が詰まった地」、青葉通り(大町)に古くからある2つの店を選んだ。

ジャズ喫茶タウンホールで朗読劇を披露する小笠原さん(右)
昼、夜の部合わせて計5公演。小笠原さんは3公演を担当し、8日夜はジャズ喫茶タウンホールで約20人の観客に朗読劇「釜石の風」を届けた。原作(同名著書・コールサック社刊)は、釜石高の教諭だった照井翠さん(俳人)のエッセー。震災後に市内外の被災地を訪ね、見聞きしたこと、感じたことを記す。

「釜石の風」を上演する小笠原さん。言葉に感情をのせ伝える
「被災地では、私達は三月を愛さないし、三月もまた私達を愛さない」。鵜住居地区防災センターの惨劇をつづったこの文章では深まる苦悩や絶望を色濃く映し出す。〽三・一一神はゐないかとても小さい――。「震災とは」という思索の中で「悲しみは薄まらないし、心の傷も癒えない」と気づかされる。
だが、それだけではない。復興に向かうまちの様子、自然の営みといった希望も伝える。自然災害を「地球のリズム」と表し、太平洋戦争末期にまちを壊滅させた「釜石艦砲射撃」にも触れ、確信を込める。「幾多の悲劇を乗り越え、壊されても喪っても不死鳥のように蘇る釜石の人々。(中略)ここ釜石は、命の尊さを学び、平和を希求する者の聖地なのだ」
小笠原さんは目の動きや表情、声の強弱で言葉に感情をのせた。ショパンの「雨だれ」を挿入歌として聴かせる演出も。短い文章の中に凝縮された思いに触れた観客は「震災を経験していないし、東京にいると、3・11に何か思うことはなかった。けど、いろんな感情を見せてもらった」「感情は人それぞれだが、次の悲劇が起こらないよう語り継いでいくべきだ」などと気持ちを吐き出した。

上演後には来場者と語り合って感情を共有、気づきを得た
「当事者がいる中で悲惨さだけを押し出したくない」と小笠原さん。この地に暮らす自身も当事者であって、今でも跡地を見たりするとフラッシュバックする。被災地で震災の記憶に触れて演じることに迷いはあるが、各地で自然災害が続く今、やはり伝えなければとも思う。「復興の過程という背中を見せていければ。移り変わる心も伝えられたら。それができるのが表現という方法の価値だと思う」と熱く語った。

観客でいっぱいの喫茶かりやで一人芝居を上演する内沢さん
内沢さんが見せたのは、鵜住居町出身の小説家沢村鐵さんの短編「もう一人の私へ」を原作にした一人芝居。岩手県出身作家12人による震災をテーマにした短編小説集「あの日から」(岩手日報社刊)に収録されている。この作品が古里公演を決意させ、今年も演目は同じ。9日午後の喫茶かりやは、約40人の客でいっぱいになった。
物語の主人公は、鵜住居町出身の作家。転機を求め郷里に戻った直後、まちは津波にのみ込まれた。偶然か、遠野市で暮らしていた母が亡くなり、葬儀のため鵜住居を離れていたことで命をつないだ。「砂漠のような」更地の光景が広がるまちで生活し続け4年。息子に手紙をしたため、そこにある思いを語りかける形で舞台は進む。

「もう一人の私へ」。同郷の表現者へ共感を込め演じる内沢さん
「あの震災の記憶に触れるときに平静でなどいられない。脚色が不要どころか、悲惨すぎてぼかすことが必要な現実なのだから」「母が生きていれば自分は鵜住居にいて、津波にのまれたはず」「隣の宇宙では、海の底で死んでいる自分がいる」―。複雑な胸の内、あったかもしれない過去や並行世界(パラレルワールド)を思案しながら独白していく。
小道具の手紙に書き込んだ文字を声にする。防災センターで多くの人が亡くなった。「到底『悲劇』では収まらない」。同じ町で小中学生が見せた避難行動に触れ、「この町の光と影は落差が大きすぎる。その光で影を吹き払うことはできない。あまりに濃い影だからだ」。目を赤らめ、言葉を詰まらせる内沢さん。観客の真剣なまなざしを受け、言葉を絞り出す。「奇跡も悲劇も要らなかった。できるだけたくさん生き残ってくれていたら…それでよかった」「便利で安易な言葉は本質を小さくしてしまう」。沢村さんがブログにつづった思いを紹介し、幕を閉じた。

上演後の触れ合いタイム。演者も来場者にも笑顔が広がる
「災害を生き残った一人の小説家の曖昧ながらも生きていく姿勢が、震災後に『自分に何ができるか』と無力感に襲われた自分に重なった」と内沢さん。そして演じてみた。今も、これが何になるのだろうと思う時もある。「でもやるしか、語るしか、演じるしかない。毎年巡ってくる新たなその日、3月11日を古里の人たちと迎える場所ができたらいい。その日にだけ思い出すのでなく、その日に向けみんなで語り合う、そんな日になってゆくのでは」。来年もまた記憶を共有する空間をつくろうと動き出す。

小笠原さんと内沢さん「演劇を通じて感情を伝え合う時間を来年も」

釜石新聞NewS
復興釜石新聞を前身とするWeb版釜石新聞です。専属記者2名が地域の出来事や暮らしに関する様々なNEWSをお届けします。取材に関する情報提供など: 担当直通電話 090-5233-1373/FAX 0193-27-8331/問い合わせフォーム