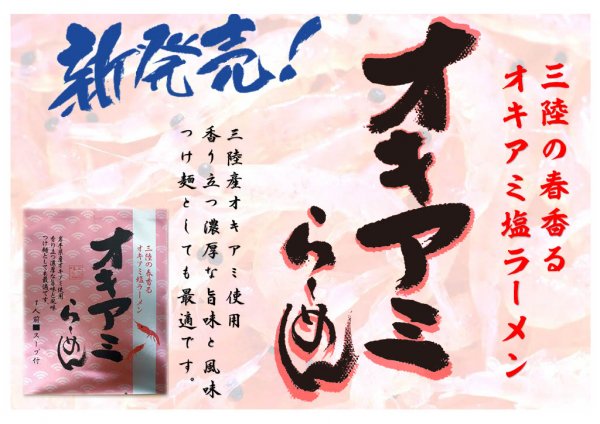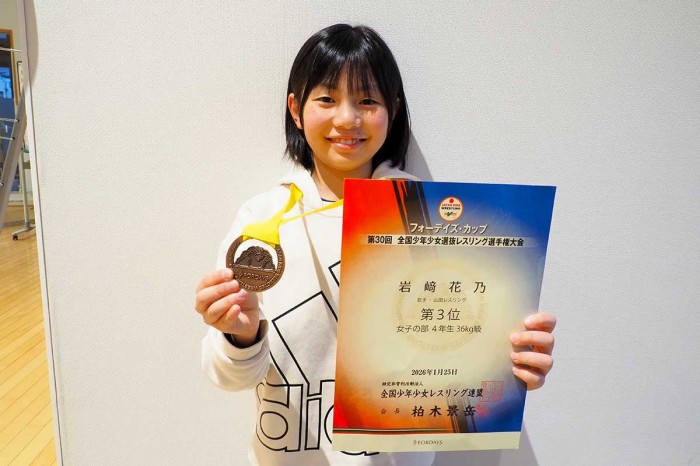「危機対応学」めぐり意見交わす、東大社会科学研究所〜意識調査を市民生活向上に

暮らしと復興の意識調査について結果を報告する神戸大の平山教授(右)と東大の佐藤教授(中)
「危機対応学」をテーマにした公開シンポジウムが26日、釜石市大町の情報交流センター釜石PITで開かれた。2005年から釜石を舞台に「希望学」の研究に取り組んできた東京大学社会科学研究所が、16年度から新たにスタートした全所的プロジェクトの一環。東大と神戸大を中心とする全国の研究者グループが、東日本大震災で被災した釜石市民を対象に11年度から実施した暮らしと復興についての意識調査の結果を報告。被災者や市民の生活向上へ、どのように役立てるか意見を交わした。シンポジウムには市民ら約90人が参加し、耳を傾けた。
調査は被災者の生活再建に向け、被災の実態、住まいや生活の状況と今後の見通し、考え方を明らかにするため11年から5回にわたって実施。仮設住宅、みなし仮設住宅、復興公営住宅で暮らす延べ5500人から回答を得た。
シンポジウムでは、調査グループの共同代表を務めた東大の佐藤岩夫教授と神戸大の平山洋介教授がそれぞれ、調査で浮き彫りとなった問題点などについて報告した。
佐藤教授は、昨年行った5回目の調査について「復興が進む中で、将来に向けた希望や明るい見通しは傾向が大きく分かれるが、『復興』の言葉が用いられるのは意外に少ない。震災の記憶がうまく継承されていないのではないか」と説明。その背景には、思うように進まないことへのいらだちがあることを指摘し、「見通しの不透明さが生む不安や不満がある。被災経験には複数の時間が流れている。この流れを量的ではなく、質的に捉える見方も必要ではないか」と示唆した。
阪神大震災を経験した平山教授は、今回は住まいの再生を重点に調査。被災者の間に孤立化や高齢化への不安が広がっていることを指摘し、「被災者の生活再建に揺らぎが見える中で、過去、現在、未来をつなぎ合わせる住まいの改善が求められる。被災者の実態を踏まえた制度改善を」と訴えた。「住宅再建の補助は、1回きりをせめて2回に」と持続的制度の必要性も指摘した。
参加した市民の中からは「津波災害からの復興の歴史と見比べると、今回の震災では他人の力を求め過ぎている気がする。地域全体で〝自力力〟を持たなければならないのでは」という声もあった。
佐藤教授は「どうにもならない場面もいろいろある。個人の努力も要るが、手助けする社会の仕組みづくりは必要だ」、平山教授は「ともかく現場に足を運ぶことが支援になる。多くの人に現状を見てもらうことが被災者の力になる」と強調した。
(復興釜石新聞 2017年8月30日発行 第617号より)

復興釜石新聞(合同会社 釜石新聞社)
復興釜石新聞と連携し、各号紙面より数日の期間を設け記者のピックアップ記事を2〜3点掲載しています。問い合わせ:0193-55-4713 〒026-0044 岩手県釜石市住吉町3-3