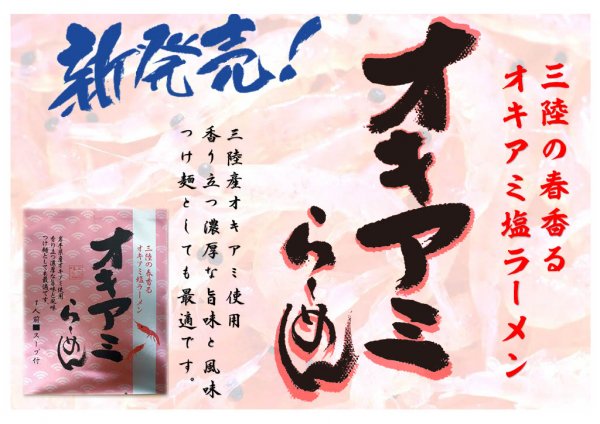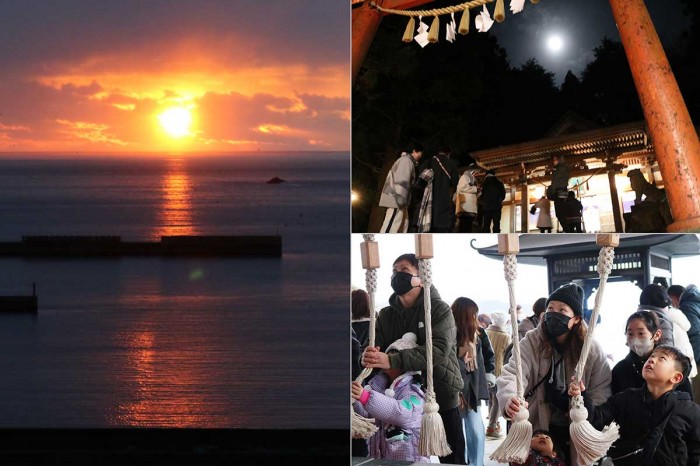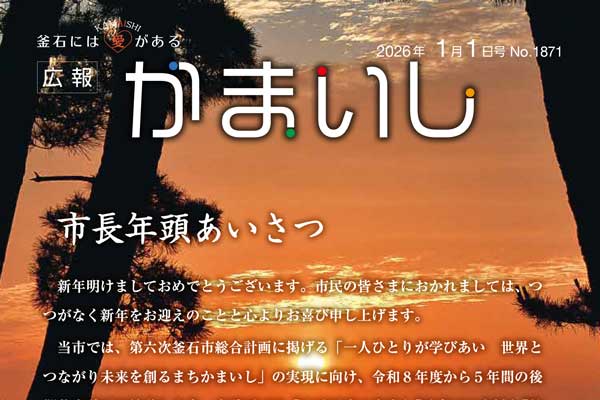「鉄の町」の歴史知る 釜石の中学生が製鉄体験 ものづくりの熱、体感「最後まで全力で」

「近代製鉄発祥の地・釜石」で鉄づくり体験に挑む中学生=3日
国内初の洋式高炉による製鉄(連続出銑)を成功させるなど「鉄の町」として発展してきた釜石市(岩手県)。市はその歴史を知ってもらおうと、市内の中学1年生を対象に鉄づくり体験を実施している。生徒は古くから伝わる、たたら技法による作業に取り組むことで、地域に根づくものづくり精神に理解を深めている。チームワークやコミュニケーション力を磨く機会にもなっており、今年度も継続。2、3の両日には釜石東中(髙橋晃一校長、生徒86人)の1年生33人が挑んだ。
体験の場は、同市甲子町大橋の旧釜石鉱山事務所前。この地は日本最大の鉄鉱山として栄え、豊富な資源を基に国内で初めて洋式高炉による連続出銑に成功し、「近代製鉄発祥の地」として知られる。

仲間と協力して炉造りに取り組む釜石東中の1年生=2日
3班に分かれた生徒は初日の2日、炉づくりに取り組んだ。コンクリートブロックを基盤に耐火レンガ約100個を積み上げ、湯出し口や送風管を固定。鉄製の煙突を取り付けた高さ約2メートルの炉を造った。
写真が添えられた平面の設計図から想像し、立体的な炉を造る過程に生徒たちは苦戦。指導する市教育委員会事務局文化財課の加藤幹樹さん(40)は図を読み解く力を養ってもらおうと、「ものづくりは図面が命。よく見て」と言葉少なく助言した。

助言、相談、にらめっこ…平面図と写真をもとに炉を組み立てる
翌日の3日に火入れ。釜石で産出した鉄鉱石10キロと木炭や石灰を投入した。原料は10回に分けて入れるが、燃焼が進むと炉内だけでなく炉の周辺も熱くなることから、作業時に防火手袋の着用は必須。「ちゃんと着けてから」と指摘した生徒に対し、加藤さんは「そう!ものづくりは事故をなくすためルールを徹底すること」と評価した。

完成した炉に木炭を投入。本格的な製鉄体験に取り組む生徒=3日

鉄鉱石と石炭を混ぜたものを投入。「鉄ができますように」
6回目を投入する前に「ノロ」と呼ばれる不純物の排出作業を行い、生徒が見守った。鉄鉱石の主成分の酸化鉄に、炭素を混ぜて高温で熱すると一酸化炭素や二酸化炭素となって気化し、純度の高い鉄が残る。そうした化学反応が「還元。酸化鉄から余分な酸素が抜けている状態」と加藤さんは説明した。

炉内から不純物を取り出す「ノロ出し」と呼ばれる作業に興味津々

ノロ出しを見守り、鉄づくりが順調に進んでいるのを確かめた
作業開始から約4時間後に解体した炉から鉄の塊(粗鉄、ケラ)が現れると、生徒たちは「よし」と歓声を上げた。加藤さんによると、地元産の鉄鉱石に含まれる鉄の含有量は6~7割程度で、たたら製鉄では10キロの鉄鉱石から2~3キロの鉄ができるという。今回はどの班も3キロ以上あった。

炉を解体すると鉄の塊が出現し、生徒は“ほっと”ひと息

塊を磨くと火の粉が舞い、鉄づくりの成功を実感する生徒ら
6キロのケラを得たA班リーダーの新屋碧さんは「本来のたたら製鉄は七日七晩続いたと聞き、鉄づくりに熱を込めた昔の人の心を感じて頑張ろうと思った。トラブルを互いにカバーしながら、最後まで全力でやれた」と振り返った。学級委員長を務め、チームづくりの大変さを感じていたというが、「仲間とのコミュニケーションやまとめ方が何となくわかった。協力の大切さも感じた。忘れずに引っぱっていきたい」と学び取った。
“近代製鉄発祥”と言えば、7月は同市橋野町青ノ木の「橋野鉄鉱山」が明治日本の産業革命遺産(8県11市23資産)の構成資産の一つとして、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界文化遺産に登録されてから10周年となる。
学区内に遺産があることで小学生のころから鉄の学習を続ける小林彩恋(あこ)さん(栗林小卒)は「鉄づくりを体験することで、座学とは違う歴史を感じられて面白かった。一から作り出すのは大変だけど楽しい」とにっこり。橋野鉄鉱山は地域の誇りであり、大切にしていきたい宝物で、「鉄の歴史が釜石から広まったことをもっと発信したい」と愛着をにじませた。

にじむ充実感。製鉄体験を終え、集合写真をパチリ
加藤さんは「ものをつくるのは苦労や難しさがあり、試行錯誤の繰り返し。基礎、小さなものを積み重ね、大変な思いをしながら生み出すのがものづくり。みんなが使っているもの、全てがものづくりによるもの。そのことを忘れないで」と思いを伝えた。中学生向けの製鉄体験は全5校が2022年から学校行事として取り入れる。今年度、他4校は8~9月にかけて開催する。
橋野鉄鉱山・世界遺産登録10周年、記念行事も
市は世界遺産登録10周年の機運を盛り上げようと、12日に同市大町の市民ホールTETTOで記念式典(午後1時半~)とシンポジウム(同2時10分~)を開く。シンポジウムでは歴史作家で多摩大学客員教授の河合敦氏が基調講演。岩手大学理工学部准教授で釜石市立鉄の歴史館名誉館長の小野寺英輝氏をコーディネーターとし、歴史の活用をテーマにパネルトークも行われる。
13日には橋野鉄鉱山周辺でマルシェ(午前11時~午後3時)を開催。飲食のキッチンカーや手作り雑貨などの出店が集結するほか、森の音楽会・バイオリンミニコンサート、ラベンダーの鑑賞・摘み取り体験なども楽しめる。
「明治日本の産業革命遺産」橋野鉄鉱山世界遺産登録10周年記念シンポジウムを開催します | 釜石市
「明治日本の産業革命遺産」橋野鉄鉱山世界遺産登録10周年記念 橋野鉄鉱山マルシェを開催します | 釜石市

釜石新聞NewS
復興釜石新聞を前身とするWeb版釜石新聞です。専属記者2名が地域の出来事や暮らしに関する様々なNEWSをお届けします。取材に関する情報提供など: 担当直通電話 090-5233-1373/FAX 0193-27-8331/問い合わせフォーム