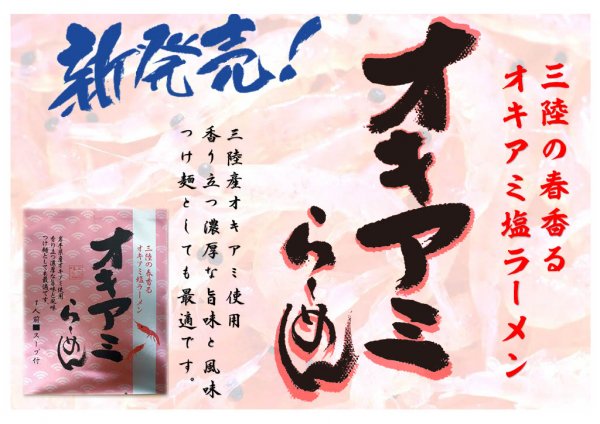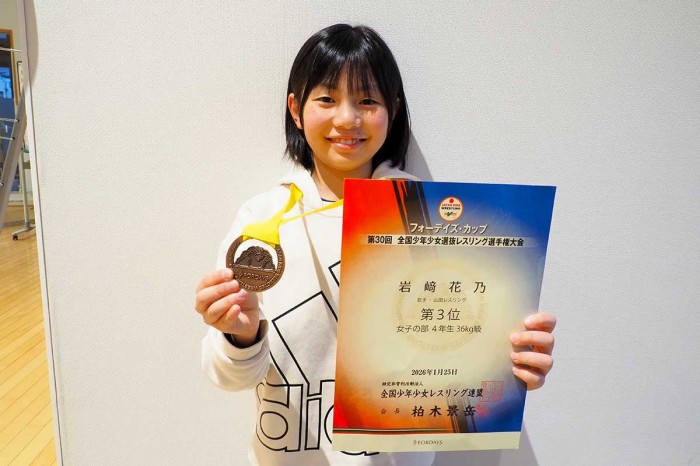「釜石呑ん兵衛横丁」写真集出版記念トークイベント 地元出身の写真家と元店主、記憶伝える

写真集「釜石呑ん兵衛横丁」の出版を記念して行われたトークイベント
写真家の佐々木貴範さん(58)=埼玉県所沢市=は3月29日、釜石市の歓楽街「呑ん兵衛(のんべえ)横丁」を記録した写真集の出版を記念して古里・釜石でトークイベントに参加した。「横丁の歴史を一冊で分かるようにして、消えていく釜石の文化を記録しようと思った」。市民ら約30人を前に、制作の裏側や込めた思いを語った。横丁で営業していた店主2人も加わり、歴史を振り返りつつ記憶を共有した。
横丁は戦後の焦土から立ち上がった屋台を起源とする。1957年ごろ、市中心部・大町の長屋に30店舗以上が軒を連ね、製鉄業で活気づく街の夜を照らす名所として親しまれた。2011年の東日本大震災の津波で建物は全壊。鈴子町の仮設店舗に移って営業を続けながら横丁の再建を模索したものの、仮設廃止に伴い、18年に約60年の歴史に幕を下ろした。その後の店主らは独立したり廃業したり、それぞれの道を歩んだ。
イベントは大町の桑畑書店が主催。現在は大町の親富幸通りで居酒屋「お恵」を営む菊池悠子さん(86)、鈴子町のサン・フィッシュ釜石内に店を構える「とんぼ」店主の高橋津江子さん(83)とトークを繰り広げ、消えてしまった横丁への思いを紡いだ。佐々木さんの親戚で、横丁の常連客でもあった大久保孝信さん(66)が進行役を務めた。

写真集に込めた古里への思いを語る佐々木貴範さん
写真集「釜石呑ん兵衛横丁 東日本大震災で消滅した飲み屋街の記録と歴史」(無明舎出版)は震災の2年前の横丁の店頭に立つ店主たちと、震災後の姿を写している。店主も客も笑顔。楽しそうな雰囲気が伝わってくるカットが満載の一冊だ。横丁の歴史についても詳しく記述しているが、「苦労した」と佐々木さん。横丁には運営の母体となるような組合はなく、あくまで任意的な集合体で、店主らの頭の中に残る「記憶」が頼り。市内の図書館で横丁に関する記事を手繰り、つなぎ合わせ、記録としてまとめた。

横丁にまつわるトークでは話し手も自然と笑顔になる
店主2人は「よくここまで調べてくれた」と感謝した。菊池さんは、作家井上ひさしさんの母マスさん(1991年死去)の店と隣り合わせだったことから、思い出話を交えて紹介。「毎日が本当に楽しかった。仮設の時も同じ。お客さんに教えられることもたくさん」と笑った。高橋さんは「苦労…ない。嫌なことがあっても、去れば忘れる。あの頃の苦労のおかげで、今でも商売ができる」と受け流す。一方で、いい思い出が多いからこそ、「横丁を残せなかったのが悔しい。次につなげようと頑張ってきたのに…」と視線を落とした。

横丁での記憶をつなぎ合わせる菊池悠子さん(右)と高橋津江子さん

会場には横丁で営業していたママさんたちの姿も。思いをポロリ
釜石で生まれて4歳まで育った佐々木さんは、大人になって帰郷のたびに街の様子を撮るようになった。「戦後の復興に貢献し、釜石の名物だった横丁。それは街の個性であり、文化だった」。そう感じてきたものは消えてしまったが、「釜石生まれの写真家として、記録をつなぐ役目がある」と取り組んだ。写真集を見て「懐かしんでもらえたら」と期待をするが、「文化とは何か。祭りや伝統行事、たくさんある。もし、消えそうな状況になったら、どう残すか」と問いかけもする。「あって当たり前と思ってはいけない。危うさに気づいた人が声を発信していくしかない」と見解を示した。

サイン会で参加者と交流する佐々木さん。古里をテーマに撮影を続ける
サイン会では「故郷礼賛」と記した佐々木さん。「何があっても、いとおしい。古里だから」と思いを込めた。釜石応援ふるさと大使を務めており、これからも「釜石」をテーマでカメラのシャッターを切り続ける考え。「震災20年の時に写真展をやりたい」と思い描く。

釜石新聞NewS
復興釜石新聞を前身とするWeb版釜石新聞です。専属記者2名が地域の出来事や暮らしに関する様々なNEWSをお届けします。取材に関する情報提供など: 担当直通電話 090-5233-1373/FAX 0193-27-8331/問い合わせフォーム