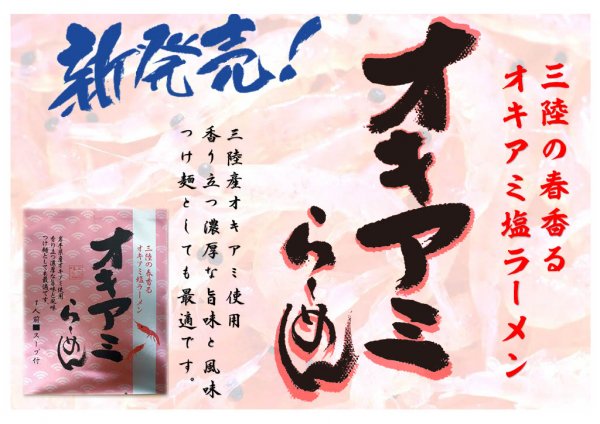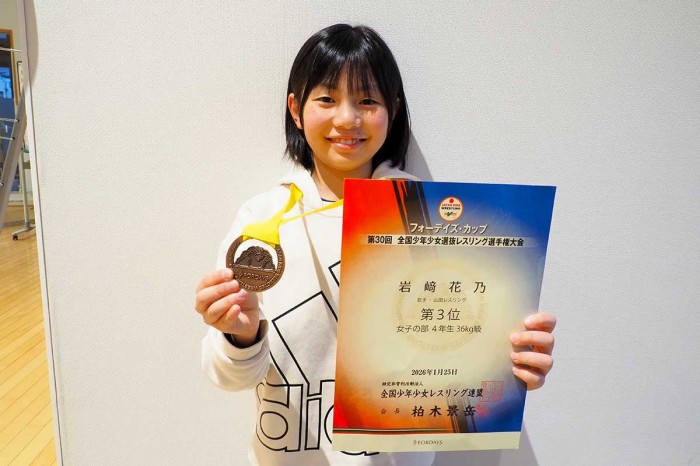震災14年 それでも歩み続ける 「あの人」への思い、心にとどめ 支え合って未来へ

地震が発生した午後2時46分、釜石祈りのパークで手を合わせる遺族ら=11日
東日本大震災は11日、発生から14年となった。釜石市全域の犠牲者は、関連死を含め1064人(うち行方不明者152人)。平穏な暮らしを一変させたあの日―。命をつないだ人々は深い悲しみと向き合いながら懸命に生きてきた。今年も巡ってきた“3.11”。市内では犠牲者の鎮魂と冥福を祈る人たちが各所で手を合わせ、故人に思いを伝えた。

「支え合って生きていく」。追悼の言葉を送った宮田キナヱさん
「元気に頑張っています」。鵜住居町の追悼施設「釜石祈りのパーク」前広場で開かれた追悼式で、遺族代表の宮田キナヱさん(76)は夫光行さん(当時70)と長男豊さん(同32)に語りかけた。遺体安置所に行った時、思わず大声で泣いた。がくぜんとする中でも「なくてはならない業種だから」と亡き夫が経営し、長男が継ぐはずだった廃棄物収集運搬会社を引き受け、事業を再開。避難所のごみ収集に携わった。多くの支援があったことを報告し、「恩返しのつもりで、精いっぱい仕事をします」と前を向いた。「安心してください。そして、これからも見守って」
遺族や縁故者ら約120人が出席し、市合唱協会員が「いのちの歌」など2曲を献唱。1003人の名を刻んだ芳名板が並ぶ祈りのパークの献花台に白菊を手向け、手を合わせた。

祈りをささげる歌声が大切な人をしのぶ女性に寄り添う

芳名板に記された文字をなぞり、花を手向け、手を合わす
千鳥町の会社員鬼頭美憲さん(50)は長男佑介さん(22)と訪れ、刻まれた2人の名に手を伸ばした。「時間や年数は経っていくが、気持ちはあの日のまま。捜し歩いた日がよみがえる。下を向く、足を止める時間も必要…だけど、歩いていかないと」。複雑な心境を吐き出す一方で、会社の同僚や市民劇の仲間たちが「顔を上げる力をくれる」とありがたく思う。亡き妻里絵さん(当時34)、長女美佑里ちゃん(同2)に向き合い、心の中でつぶやいた。「(佑介は)たくましく強く育ったよ」「そばにいると思って生きてくよ」

「それしかできないから」。魚河岸の岸壁から海を見つめる漁業者
祈りのパークの場所には震災時、鵜住居地区防災センターがあった。多くの住民が逃げ込み津波の犠牲となった。「親戚がそこで…」と話したのは、浜町の70代女性。魚河岸の市魚市場近くの岸壁で干物づくりを終え、唐丹町で暮らす実弟(60代)と海を眺めていた。女性は津波で自宅を失ったが、ほぼ同じ場所に再建。漁師の夫は「海しか見えない」とこぼしつつ、自身も「小さい頃から見慣れているから、海がないとね」とうなずく。“夫婦漁師”は「あと数年かな」とぽつり。「だんなと一緒に過ごせたらいい」

花や菓子を供えて墓参りする遺族=11日昼ごろ
市内の墓地には朝から、遺族らが墓参りに訪れた。大平墓地公園で、亡き夫栄蔵さん(当時67)に手を合わせた佐藤昌代さん(81、大船渡市)。震災時は釜石市浜町に暮らし、夫婦で自営業を営んでいた。「俺、車よけてくっから」。配達から戻った夫の最後の言葉が今も耳から離れない。周りに促され、先に避難所に向かった。「(夫も)きっと逃げているはず…」。迎えにくると信じていたが、安否は不明のまま。2週間後、がれきの下から見つかった。「自分の持ち物には何でも名前を書く人だったので…」。身元確認に行った遺体安置所で対面した夫は別れた時のままの服装だった。仮設住宅に入ったが、「しばらく笑い顔ができなかった」。後に、出身地で妹らが暮らす大船渡市への移住を決めた。

「会いに来たよ…」。故人への思いを胸に手を合わせる
昌代さんと墓前を訪れた長女船野有紀子さん(54、宮城県)は、墓石をなでながら家族の近況を報告した。「父は働き者。朗らかで家族思い。私たち娘も5人の孫も、とてもかわいがってくれた」。14年という時の経過はあっても「忘れることは一日もない」。家族が集まると、必ず話題になるのは父のこと。「14年か…。会いたいな」。思い出は決して色あせない。「今は気ままにやっているから」と話す母。近くにいてくれる叔母らに感謝しながら、母が元気でいてくれることを願う。

身元不明の遺骨を安置する震災物故者納骨堂(大平墓地公園)で行われた供養
大平墓地公園内には、身元が分からない犠牲者の遺骨を安置する納骨堂がある。全身骨5柱、部分骨4柱が眠る。今年も市関係者、一般市民らが参列して供養が行われた。黙とう後、釜石仏教会(大萱生修明会長、17カ寺)の僧侶9人が読経し、参列者が焼香。いつか家族の元に戻れるよう祈りをささげた。
2018年に納骨堂が完成するまで遺骨を預かり、供養を続けてきた仙寿院(大只越町)の芝﨑恵応住職は「一生懸命生きたはずの皆さんが(震災で)どこの誰かも分からなくなり、遺骨には数字しか並んでいない。非常に悲しい現実がある」と吐露。参列者は「早く見つかってほしい。それまではみんなで供養していく」と思いを寄せた。

地震発生時刻に海に向かって黙とう=午後2時46分、鵜住居町根浜
午後2時46分―。14年前の地震発生時刻を告げるサイレンが市内に鳴り響く。それぞれの場所で目を閉じ、祈りをささげる人々。あの日、津波に襲われた鵜住居町根浜の旅館「宝来館」には遺族や地元住民、ボランティアの大学生など多くの人たちが集まり、追悼行事(3.11祈りと絆「白菊」実行委主催)が行われた。
市内全小中学校14校の児童生徒から寄せられた追悼と未来へのメッセージを朗読。犠牲者、被災者への思い、自分を生み育ててくれた両親への感謝、命を守る行動への誓い…。震災の記憶、経験がない子どもたちが紡いだ言葉の数々が集まった人たちの心に響いた。

さまざまなメッセージを記した風船を大空に放つ

能登半島地震、ウクライナとロシアの戦争…。小中学生からは他地域の被災者らに向けたメッセージもあった。復興や平和への祈りが続く
津波で両親を亡くした同町出身の民謡歌手佐野よりこさんは「今でも悪い夢であってほしいと思う。大切な人を亡くした悲しみは一生消えることはないだろう」と遺族の気持ちを代弁。「犠牲になった人たちの分まで、一日一日を大切に前を向いて歩いていく」と誓った。天を仰ぎ、“津波てんでんこ”“南部木挽唄(オーケストラバージョン)”を献唱した。

佐野よりこさん(右)は津波犠牲者らの冥福を祈り2曲を献唱。古里の海に眠る故人の魂を慰めた
穏やかに寄せては返す波―。祈りの場となった根浜海岸はこれまでにない静けさをたたえた。夜に予定されていた鎮魂の花火「白菊」は、大船渡市で発生した大規模山林火災を受け、6月に延期された。毎年、同花火打ち上げの手伝いなどボランティアで訪れている奥州市の小笠原徹さん(46)は小学2年までを鵜住居町で過ごした。「震災から2カ月後に来た時は衝撃で言葉にならなかった」。釜石には妻と息子も一緒に。「震災を忘れてはいけない。風化させないよう子どもにも徐々に伝えていきたい」と話した。

鎮魂、復興、記憶、希望の4つの言葉が刻まれた「釜石復興の鐘」を鳴らす。大船渡市の山林火災被災者にも思いを寄せて…
追悼行事は夜まで続いた。鈴子町の釜石駅前広場では夕方、「釜石復興の鐘」の打鐘が行われた。主催した、かまいし復興の祈り実行委の八幡徹也代表は震災と大船渡市の山林火災を重ね、「“まさか”は突然やってくる。私たちは大震災とコロナ禍、2つの“まさか”を乗り越えてきた。大船渡の被災した方々にも心を寄せ、鐘を打ち鳴らしてもらえれば」とあいさつ。招待者に続き一般市民らが鐘を鳴らし、鎮魂と復興への祈りを込めた。長年、鈴子町内会長を務めた澤田政男さん(76、宮古市)は「鈴子は釜石の玄関口。この場所に復興の鐘があることは大きな意味を持つ。訪れた人が震災を思い出し、忘れないための一助になれば」と願った。

釜石新聞NewS
復興釜石新聞を前身とするWeb版釜石新聞です。専属記者2名が地域の出来事や暮らしに関する様々なNEWSをお届けします。取材に関する情報提供など: 担当直通電話 090-5233-1373/FAX 0193-27-8331/問い合わせフォーム